|
生活共同体CCRC (Continuing Care Retirement Community)とは、「アクティブシニアタウン」と言い換えることもできる。この集合住宅の考え方は、1970年代のアメリカで始まったとされているが、長寿社会の日本にも、政府のリーダーシップで導入のための準備が進められているという。
長寿社会となり、定年退職した人達が、大都会でふらふらとして朽ちていくと、医療費ばかりが掛かるばかりでなく、活力のない社会が造成されてゆく。健康である内に農村に移住し、農業体験を通して地域社会に溶け込んでゆき、地方創生の担い手になる。
古来より、農耕民族である日本人は、宗教的な色彩を持つまでに農耕を尊ぶ。土を手にすることにノスタルジーが有り、収穫は達成感に通じている。したがって、私は、此処に来て、シニア層が中心となり、農耕地に向けての、民族大移動が起こるのかと想っていた。
検索サイトで覗いてみると、稲毛市や南魚沼市では、市の活性化対策として洋々たるものがあるらしい。
「稲毛市では、高齢者が健康時から介護時まで移転することなく継続的ケアが保証されるコミュニティーを指す。分譲型マンションに約700名が暮らし、クラブハウス・娯楽施設併用のコミュニティー施設は約1000人が同時に過ごせる大規模なもの。2万坪以上のグラウンドを備え、ゴルフ、野球、サッカー、テニス、ジョギングなど多様なスポーツ利用が可能だ。」
「南魚沼市には国際大学という比類のない地域資源があり、ここへ移住するアクティブなシニアと留学生との交流や、国際感覚を有する人材育成などのプログラムが展開されることで、国際交流の推進や南魚沼市へのグローバル企業誘致等、この地における国際ビジネス環境の創造に繋がる可能性が広がる。」
「日本版 CCRC」とあるが、あれあれこれはどうしことか、遊ぶ施設や、俗に言う、リゾートマンションばっかり。国際大学とかいうものの名前がある。教育を売り物にすれば、形が取れる。通信教育の英語でも何でも一緒だが、もとより、それを習ったとて通訳になる道が開けるわけではない。日本人は教育に弱い。学ぶことは善である。しかし高齢者になって、語学を習って、今更何に使おうというのか。
で、農業のことには触れてはいないが、設立場所から考えて、近くのコミュニーと接触して、そこで土地を借り、耕しながら農業を学び、耕すことにはなるとは思うのだが、私の頭では中心に位置する農作業は、これらの企画にあっては、オプション(追加希望)扱いなのが気に食わない。
農業を生活の中心に置いた人間の生き方に就いては、トルストイの宗教的、禁欲的なもの、その流れを汲む、武者小路実篤の「新しい村」構想などを、これまでに何だかの形では読んできたが、むろん私の身には付いていない。
二つ程度の「おにぎり」で十分である。その「おにぎり」に、朝は味噌汁。昼はコロッケ。夜は肉ジャガが付いておれば十分である。畑仕事で肉体を動かすから、飯がうまい。卵に感謝、干し魚に感謝である。
疲れているから、夜は好く眠むれる。糖尿病の薬も睡眠薬もいらない。薬アレルギーにならないから、体もかゆくない。これが自然の生活である。
仕事は単純であるが、畑が連作にならないように、限られた土地の中、作物のローテーションを考えながら、播種、植え付けをしなくてはならない。植え付け時期は、その土地に固有の法則があるに違いない。ここで、頭を悩ますから、実際に体を使うからか、耕作する人には認知症になる人が少ない、といわれている。
植物は、水と肥料の窒素成分を吸い上げ、太陽エネルギーを得て、自らの葉緑素で空気中の炭酸ガスを同化するのだが、その意味では、土は、植物の根と、水と肥料をうまく保持する触媒のようなものである。とすれば、日頃から土の肥やし方には一番力を注がなければならい。鳴門金時というさつま芋は甘いことで有名だが、芋ができる20〜30cmの深さではなく60 cmの深さにまでも土壌を柔らかく作り込む必要がある、といわれている。
水利、田畑の土木工事にはトラックターや耕運機の扱いにも慣れておかなくてはならないが、何を措いても、先ずは体力である。パソコンにあるエキセルを使った作表は、仕事のまとめ、収穫、売り上げ管理には強力な武器になるかもしれない。しかし、農作業に就いたからには、あまり計算などの事務作業に力を入れず、机から離れることを心がけて措かなくてはならない。
正に、人間復活である。これを、人間70歳からやるのである。
このように考えると、「日本版 CCRC」に有るオプション農業で、本格的な農耕中心の生活ができるかどうかは、全く、疑わしくなってくる。よほど本人の意思が固くなくては、強制力ない企画に乗り続けることは難しい。
今その気があったら、例えば、岡山の農村地帯に入ってみる。農家の働き手は老い、跡継ぎが見当たらないのが現実である。その結果、耕作地放棄の事態が生じている。先祖伝来の田畑を荒らさないためには、使い続けることが必要なわけで、所有権の移転がないなら、「どうぞ、無償で田畑をお貸しします、どうぞ使ってください。」が、世の流れである。
今から20年前、私の弟は、サラリーマン生活をやりながら、果樹園を夢見たのである。
岡山の果樹園の持ち主には跡取り息子がいるが、当面、家には帰ってこない。その間、ピオーネを作る葡萄畑を荒らしてしまわないように、とにかく10年、いゃ、20年程は管理を続けて欲しい。その代償として、持ち主が葡萄畑の作り方の指導はする、肥料や修理用材は弟が持つが、収穫物は、基本的には、全て弟の取り分となる。
居住する西宮と、果樹園の岡山熊山との距離は70km、収穫物に価値が付いても、全ては高速料金などで消える。弟の労働力が、果樹園作りのノウハウの獲得と日曜菜園の喜びでチャラとなっていた。この間の私の試算に就いては、(エッセイ19)果樹園 に書いたところである。もし、果樹園の傍に家があり、日曜だけの仕事で、肥料、袋代消耗品の費用を考えると、収穫した葡萄の半分ぐらいが、労働の成果物として確保されるというところであるから、農耕から、何らかの利益を生むなどといいうのは凡そ、机上の空論である。
この弟の計画は途中で頓挫した。10年ぐらい経って、持ち主の息子さんが、故郷に帰って、片手間で葡萄をやるということになったらしい。が、弟は既に、岡山の地には馴染んだのであろう、他の家から、家の田畑をやってくれないか、という申し出が多くあったという。従って、定年後は、その地に古家を買い、申し出のあった田畑を耕作して暮らしている。
第二の人生が、果樹園と共に有るという優雅な生活ではないが、別宅と称する生活基盤と、借用する耕作地があって、労働力を代償に自給自足生活が送れるならば、地域との義務、交流もできる後期高齢者の基盤ができたことになる。
私自身は、「さつま芋」を作るとは言いながら未だにその農耕地の確保ができていない。「さつま芋」を作るというが、その背景には当然、体力のある健康な自分の姿が有る。しかし、自分が健康である内に実行に移すとすれば、スタートは、この一、二年に限られる。追い込まれてしまった。「さつま芋」というのは、終戦後の食糧難を象徴するキーワードである。「さつま芋」と聞けば、戦争を体験してきた人間には、戦後の飢え、困窮の様子がありあり思い浮かぶのである。
今、私は、椎茸を作っている。かれこれ20年近くにもなる。
椎茸のほだ木として有効な小楢の木は、関西では数多く生育している。我家にも幹の太さが40cmになるものが10本ほどあるが、生長が早いので、放っておけば、その枝が、直ぐにも家屋を覆い隠すようにする。従って、何時も、枝切りには留意することになる。そこで、切った枝の処理方法として、椎茸の栽培に目を付けたのである。
二月に入って、小楢の木にはしごを掛けて、大きな枝を切り落とす。直径15cm位のものが良い。直径5cm位のものは椎茸の発芽は早いが、2,3年で朽ちてしまう。直径20cmになると、木は長持ちするが、椎茸の収率は悪い。毎年、長さ60cmのものを40本ほど準備する。
だいたい2週間ほど自然乾燥させた木が好いようである。椎茸菌が活着するほだ木にはある程度の水分は必要らしい。枯れて朽ちた木では椎茸が発生しなかった。
椎茸の種類は、森産業製である。2月に、この駒菌をホームセンターで買ってきて、上述の整えた木にドリルで穴を開け、そこに駒菌を打ち込む。この椎茸菌は二夏を越して始めて椎茸が発生する。
ほだ木としたものを木陰に並べる前には、3ヶ月ほど、束にして横に寝かして上に幌を掛けておく。伏せ木の工程である。6月、ほだ木の切り口に菌糸の菊模様が広がる。このほだ木を木陰に立てて置けば基本的な作業は全て終わりである。あとは雨が少ない季節など適当に水を散布してやればいい。秋、春に、傘の径が10〜20cmの、かなり巨大な椎茸ができる。
今般、街で売られている椎茸は菌床栽培(大鋸屑に椎茸菌を混ぜたもの)が多い。従って、私の作る椎茸は原木栽培だから味がいいと、送った友人の評判は上々である。趣味でやるのならば全く問題ない。エコで、仲間に喜んでもらい、自分は健康が貰える。
しかし、もしこの椎茸栽培を「日本版 CCRC」にするとならば、収支計算はしておかねばならない。場所、原木材は無償としても、駒菌1600個は\8,000 、雑消耗費\5,000 ほだ木の耐久年数は4年。この間、打ったコマ菌の20%だけが椎茸発生があるとすると、1個\50として、¥16,000。収支バランスとしてはとんとんというところ。健康とリクリエーションにはなる。長寿社会の生き方としては、儲けはなくとも良いから、楽しく身体が動かせ、新しいものに挑戦できているという感覚があれば、よしとしょう。だが、インターネットにある知識を参考に、独学では、習い憶えるのに10年は掛った。
もし、貴方が、高齢化時代の活性化を農業に求めるとあらば、公的な支援は待たず、自ら突破口を切り開いていくのが得策かも知れない。70歳辺りで元気で居られる華の期間は案外短いかも知れないのである。
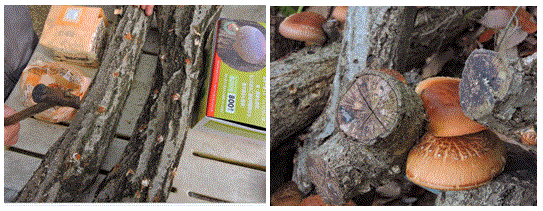
< 写真 駒菌を打ち込む 写真 椎茸>
(2017.04)
|

