|
◇「戯作三昧」◇
倉本 聰(くらもと そう)は、富良野を舞台にした家族ドラマ『北の国から』の有名な脚本家である。その中に、田中邦衛という個性的な俳優がいた。とまでは知っているが、私は、『北の国から』のドラマは一度も見たことがない。
その倉本 聰さんの作家生活を取り上げたテレビ番組があった。夜、書斎にて居住まいを正し、香を焚き、朝4時ごろくらいか、作品が降りてくるのを待つのだという。自分の意識から離れた別の次元から、閃きのようなものが遣ってくる。
私の高校時代の国語の時間だった。芥川龍之介の「戯作三昧」が教科書にあった。滝沢馬琴が、突如降臨した文脈を見失うまいと、老いた体が追随できなくなることを恐れつつ、その啓示に筆を走らせる様が描かれていた。いわゆる芸術のインスピレーションだと、大野先生は言った。因みに、「戯作」とは江戸時代の「物語」のこと、「三昧」とは夢中になること。
高校2年生が終わる早春の頃、クラス誌に出すとは決心したが、書けもしない小説に悩んでいる私に、明け方、突如、あの「戯作三昧」の状況が訪れたと思った。今まで、考えても出てこなかった文節が、何の脈絡もなく現れるのである。接続詞が無くても、文章がつながってゆくのである。確かに、今を措いては絶対に書けないなと、その時思った。((エッセイ10)小説家になる /続 小説家になる 参照)
その後、この種のインスピレーションは私に訪れたことはない。が、以降、私の回りで、何かの折にふれて出される文集には、必ず応募してきた。大学でも、就職してからでも。「戯作三昧」の状況を経験したことで、私には、小品をものにできるという、自信のようなものが備わったのである。
インスピレーションが天から、突然訪れるという現象は、文学、絵画、音楽家など、芸術家にはよくあることかもしれないが、普通のエンジニアにも、確かにあるのである。
化学史の発展で有名なケクレは、炭素原子同士が結合して鎖状化合物を作ることを提唱していたが、ベンゼンの構造説明には悩んでいた。が、ある日、ヘビが自分の尻尾を噛んで輪状になっている夢を見てベンゼンの六員環構造を思いついたといわれている。
ケクレでなくっても、油にまみれたエンジニャーなら、何かしら、やり続けている内に、思いもしない解決方法に辿り付ける事は、皆よく知っている。絶えず考えやり続けることによって、インスピレーションはやってくる。だから、真面目にやり続けることが肝心と、親方は新人に語りかけるのである。
研究部の新人として結晶化板ガラスの製造に従事していた若造だった頃の話。溶融ガラスを板にする工程で、水冷ローラー迄きた熱いガラスが、徐々にだが、できた結晶体に阻止されて、対のローラーの間隙から板として流出できなくなると、やむをえず、板ガラスの製造を中止する状態に陥ることが度々あった。しかし、度々機械が止まると、結晶化ガラス建材開発事業の中止へとつながる。
ある夜勤の時、ローラーの前で徐々に成長してゆくガラスからの結晶を、小さい内に取り除こうと、熱いガラスの流れに鉄のへらを入れていたが、結晶はどんどん大きく成長を始め、もう少しでガラスの流れを止めるところまでいった。焦った私は、鉄のへらをローラーの間隙に挟ましてしまった。大失態である。ローラーの動きが止まるかも知れない。
鉄のへらは幸い、ローラーの間隙から出てきた。驚いたことに、成長しつつあった結晶体が、鉄のへらに誘導されて、次に、ローラーの間隙から出てきたではないか、そうか、ガラスの流れを止めるまでに大きく成長した結晶でも、そこにへらを差し込み、へらをローラーに噛ませると、成長した結晶体ですら、上手くローラーに噛み込ませ除くことができることが分かったのである。
失敗が一転、問題の解決につながった。私は、神が現れたのかと思った。それぐらい感激した。
例えば、私のエッセイ集(エッセイ112):「続 或る日、突然に分かる(旧約聖書と新約聖書と「行」)」を例に取れば、「旧約聖書」と「新約聖書」の違いは、神との‘契約’時期の違いだと聞いて、神と人類がことを‘契約’すると言うことも驚きなら、カソリックもプロテスタントも、その二つの聖書を厳然として、教典と見なしていることも、不思議と言えば不思議であった。と、エッセイを書き出して、実は、どういった結末になるかは分からないのであるが、その納まりは何と、日頃あまり考えもしていない、仏教のこととなり、自分が宗教とどう関わり合っていくかという、一つの切っ掛けを見つけたような格好になってしまった。
実は本当に不思議なのだが、エッセイを書きはじめたものの、結末までは殆ど予測できない、しかし、どこかに収まるだろうとの自信のようなものがある。こんな事が時々はあるのだ。そして確かに、この時も、自分の予想もしない形に何とか収まってくれて、書いている自分が、その結末に「へえ、そんな風になるの」と、驚いている。
(2017.06)
◇面白い小楢の伐採方法◇
4,5年前、京都の山で「楢枯れ」が発生しているとの話を聞いた。小楢は日本を代表する雑木であり、秋にはどんぐりの実を落とす。椎茸栽培のほだ木に使われる。その楢枯れは、京都にある私が勤める学園内の木にも及んでいて、幹にはビニールシートが巻かれるようになった。殺虫剤を注入すると同時に幼虫の飛散を防ぐためらしい。
2年ほど前から、奈良の周辺の山々にも楢枯れは及んできて、山々を見れは所々に褐色の斑点が見えるようになった。山道を歩いていると、黄土色の粘土かと見まちがうほどの大量の土が盛り上がって、道端の大木の根元にある。樹皮にできた小さな穴から出てきたようで、雨水で根元に集められたもののようだ。
根元の直径が30cmはあろうかという太い木がやられるが、それも20日程で、あっという間に葉が枯れてしまう。原因は分かっていて、体長4,5㎜のカシノナガキクイムシが進入し、ナラ菌を持ち込む。そのナラ菌に感染した部分の細胞が死ぬと、木の道管が目詰まりを起こし、通水障害を起こして、木が枯れてしまう。だがよくしたもので、全部の木が枯れるという訳ではない。よく見てみると、カシノナガキクイムシが入り込んだ穴から黒い液を出してる木がある。リグニンが変性したタールのようなものである。
枯れた木の高さは15m位はある。枯れ枝の落下は遊山に来る人を殺傷する。山道を歩いていて、急に太い枝が上から墜ちてくるといけないので、道に落下した小枝が散乱している個所では、振り仰いで、木立の劣化具合を目で確かめてから、通り過ぎることになる。
大阪府民の森では、枯れた大木をとにかく切断し、取り除くのに多大の労力と金を使っている。公園内であれば、チェーンソウでただひたすらに切り倒すだけであるが、問題は、個人の庭の枯れ木の除去である。日常の生活圏に頭上から太い枯れ枝が落下するのは危険極まりないが、切断除去は、切断した木が、例えば、屋根に落ちたり、大切な植木を傷つけるので、野山の樹木ほどには簡単ではない。
枯れ木の蔓延を防ぐために、生駒市は補助金を出して、個人の庭にある枯れた小楢も積極的に切らすことにしている。我が家でも2本が楢枯れに襲われたが、業者見積もりによれば、一本30万円ぐらい掛かるらしい。リフト付きの高所作業車を入れることができないので、人が縄ばしごなどを掛け、限られた空間での作業に当る、作業者の労災保険も高いらしい。たとえ、市からの援助が3割程度はあっても、2本40万円は我が家からの持ち出しである。
高所作業車が入れば5万円もあればできる仕事ではないのか。この場合、リフトに乗った作業者が、片手で担げる大きさで、上部の周囲から順に枝を切ってゆく。幹は最後に上部から、やはり担げる大きさに、チェーンソウで切ってゆくのである。
40万円は痛い。加えて、家の木を伐採するのは自分のリクリエーションである。自分でやることを考えた。木の枝を鋸で上手く切り取ってゆくのではなく、枯れるだけ枯らして措いて、枝にロープを掛けて、引きちぎっていくのはどうか。金属ロープで引っ張るウインチを買った。ウインチというのは、トラックの荷台でロープを締める、てこのようなものだ。
一方向にロープを掛けておいて、40㎝直径の幹を切り倒すことは、それほど難しくはないが、枝を先ず払って、一本立ちの姿にしておかないと切り倒すことはできない。枝が回りの木に掛かると、中途半端な形でとどまった木の処理はいっそう難しい。張り出した枝をロープでどう引きちぎるか。
図は、ロープ掛け器を木に引っかけて、木の枝にロープを掛けた状態を示す。写真は、このロープ掛け器を使って、枝を引きちぎった、枯れた小楢の立ち姿である。
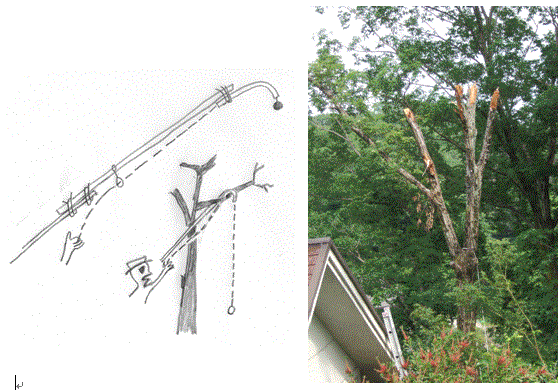
太いロープにつなぎ変え、そのロープをウインチで牽引して、枝を引きちぎった。枝の又から一定距離へのロープの移動とか、やっている内に閃いたアイデァーとかが色々あるが、ここには書かない。あわよくば、木折り業者となって、枯れた巨木に困っている家庭からお駄賃をいただく将来構想もあるからである。
ポイントは、枝へのロープの掛け方である。ゴム・パチンコのようなもので、パチンコ玉に細い糸を付け、枝をオーバーさせた細い糸を、順に大きなロープに代えて行く手もあるらしい。森林の小枝の中を動き回ることを、今流行のドローンができるのなら、これは有力なロープ掛け機材となるので、着目である。好きな森林作業で、お金が入ってくるなどと考えると、この老いの将来が明るく見えてきた。
(2017.06)
|

