|
昔から不思議に思っていることがある。文字の発祥に関することである。
日本には、朝鮮から漢字という知識がもたらされるまでは、漢字はおろか、文字というものがなかったというのだ。古事記(712年)によると、応神天皇(300年頃)の時代に 朝鮮半島の百済から王仁博士が渡来し、『論語』や『千字文』をもたらしたとされている。
それでは、文字なくして、日本の人々、いや倭、卑弥呼の時代、弥生式、さらには縄文式の時代の人々は、話し言葉はともかく、過去の経験、伝聞なるものをどの様な手段で伝え、事実を記憶に留めてきたのか。
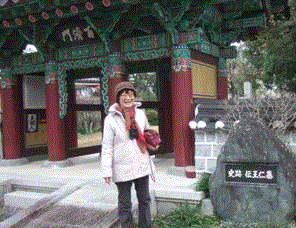 私の住む生駒市のごく近くの、枚方市に 王仁博士の墓がある。住宅地の一郭にあるのでちょっと解りにくいが、車30分を飛ばして行ってみた。お墓といっても顕彰碑に近く、資料館が置かれているわけでもないので、取り上げて文字発祥の史実を知る手掛かりは何もない。もっとも、王仁博士の墓、顕彰碑は全国に多数あるようで、東京・上野公園の清水観音堂の裏手に建つものも、その一つであるらしい。
私の住む生駒市のごく近くの、枚方市に 王仁博士の墓がある。住宅地の一郭にあるのでちょっと解りにくいが、車30分を飛ばして行ってみた。お墓といっても顕彰碑に近く、資料館が置かれているわけでもないので、取り上げて文字発祥の史実を知る手掛かりは何もない。もっとも、王仁博士の墓、顕彰碑は全国に多数あるようで、東京・上野公園の清水観音堂の裏手に建つものも、その一つであるらしい。
写真は、枚方市藤阪東町2丁目にある王仁博士の墓の百済門前の外観である。
現存する書物で、最も古いものは「古事記」だという。稗田阿礼の持つ伝承の記憶を、平城京の文官で漢字を習得していた太安万侶(おおのやすまろ)がその漢字を使って記録したとある。
そもそも「古事記」(712年)とは何か。奈良時代から見てその古に起こったこと、即ち、神話及び、歴代天皇の業績を書物にして、国土統一の由来、天皇制の正統性を定着化させる事業の一環であったと、される。
天照大神が天岩戸に引きこもる話し、大国主命が兔(うさぎ)を助ける話、日本武尊(やまとたける)が八つの頭と八つの尾をもつ大蛇を退治する話などが書かれている。太安万侶は、稗田阿礼から聞く話を、漢文(中国語)では書かず、漢字を借りて当時の日本の口語により沿った形で書いている。
例えば、大国主命が兔を助ける場面では、
於是大穴牟遲神 教告其菟今急往此水門以水洗汝身
於是(ここに)大穴牟遅の神(大国主命)、其の菟に教(をし)へて告(の)たまはく「今急ぎ此の水門(みと)に往(ゆ)き、水を以ちて汝(な)が身を洗へ
即取其水門之蒲黄 敷散而輾轉其上者汝身如本膚必差
即(すなは)ち其の水門(みと)之(の)蒲黄(かまのはな)を取り、敷き散らして[而]其の上を輾(めぐ)り転(まろ)べ者(ば)汝(な)が身(み)は本の如(ごと)きに膚必ず差(い)ゆべし
(引用:ホームページ 「古事記をそのまま読む」)
「古事記」ができた奈良時代より、時代は一つ前の、飛鳥時代、604年(推古十二年)、聖徳太子の十七条憲法がある。この用語は原則、漢文(中国語)でできている。
一曰。以和為貴。無忤為宗。・・
一にいわく。わをもってとうとしとす。さからうことなきをむねとす。・・
(一、調和する事を貴い目標とし。道理に逆らわない事を主義としなさい。・・)
( 引用:ホームページ:眞實一路の旅なればby 三瓶 精二)
竹を短冊状に切った木簡は、納税荷の伝達などに使われたもので、大阪市中央区の難波宮(なにわのみや)跡で発掘されたものが資料として残る最古のものである。前期難波宮の完成の頃(652年)漢字を使った当て字を使い、口語読みにできる文字が墨で書かれている。
「皮留久佐乃皮斯米之刀斯」、
「はるくさ(春草)のはじめのとし」
(ウイッキペディアを参照)
即ち、(300年)頃に 朝鮮半島の百済から王仁博士が渡来以来、(604年)聖徳太子の十七条憲法は漢文で書かれたとしても、木簡、「古事記」そして、「万葉集」の万葉仮名などでは、漢字を借りて時の日本語を何とか表現しょうとの試行期間には入っているが分かる。
また、それより前の時代の300~500年の古墳時代にも日本語への漢字の当て字は徐々に始まっていたのであろうが、この時代を代表する書き物資料は現存しない。しかし、朝鮮出兵や、中国との交流はあったのだから、何らかの形で漢文を学び使っていたことは想像に難くない。
443年 宋・文帝に朝献して、「安東将軍倭国王」の称号を得とされる。(『宋書』夷蛮伝)
413年 高句麗・倭国及び西南夷の銅頭大師が安帝に貢物を献ずる。(『晋書』安帝紀、『太平御覧』)
(ウイッキペディア参照)
古事記編纂の稗田阿礼については、判かっていることが少なく、舎人(皇族や貴族に仕え、警備や雑用などに従事していた者)というだけで、女性説もあるという。私は、稗田阿礼が、古の事柄を全て暗記しているから、この編纂に参加しているのかと思っていたのだが、稗田阿礼は、2篇の歴史書(「帝紀」「旧辞」現存しない)を予め先に暗誦することも天皇から命じられている。この2篇の歴史書の内容が必要なれば、太安万侶がそこから内容を写しながら書けばよいのに稗田阿礼の助けを借りている。何故、稗田阿礼の暗記力を借りる必要があったのか。
私は、稗田阿礼の頭にある伝記も必要であったが、ひょっとして、稗田阿礼は通訳能力があり、漢文を読んで、直ちに日本の口語に訳せる能力があったと見るのである。
私はまた、稗田阿礼が暗誦している物語の量には当然限度があるし、それも書物何冊に及ぶほどではあるまいと考えていた。しかし、盲目のピアニスト辻井伸行さんを見て、多分、LPレコード盤なら100枚、200枚も暗譜できている(いや、我々が想像するのとは別の暗誦方があるのかも知れないが)、研ぎ澄ました人間にはそれほどの能力が備わっているのだと思うようになった。百科事典の一つや二つ、いや、この凡人の私ですら、この「ゴンちゃん倶楽部」のエッセイの200件やそこら、確認で別の図書を調べることも多いが、ほぼ、昔の記憶を引っ張り出しているだけである。まして、稗田阿礼の時代には、想い出しの切っ掛けとなるキーワードなどには、辻井伸行さんとは違って、既に、漢字などの文字の使用も可能だったのである。
伝統を伝える人間の記憶容量というものは、想像以上に、書物の数巻と同じぐらいには莫大なものなのかも知れない。
それでは更に遡って、
(300年頃)王仁博士が渡来する前の、卑弥呼の時代、さらにその昔の弥生式時代にはどんな文字が使われていたのか。
徐福伝説というものがある。
紀元前219年、徐福は始皇帝に東方に仙薬を求めて渡海することを上申した。徐福は幾日もの航海の末、辿り着いた先で『平原広沢』得て、中国には戻らなかったとされている。一説には、辿り着いた『平原広沢』が日本であり、農耕・製紙などの技術を伝え、日本の発展の大きな礎を築いたと言われている。
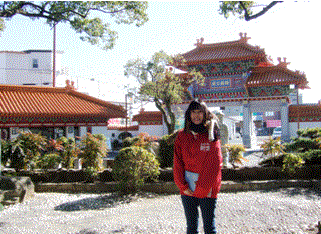 写真は、和歌山県新宮市にある徐福公園内の写真である。私が、熊野速玉大社と前岡選手がいた新宮高校を見たいと思い、車を走らせている途中に、偶然見つけた観光スポットであった。施設の雰囲気は、前出の王仁博士の墓のあった公園とよく似ている。お墓と称するものはあったが、徐福の業績に関する展示物はなかった。
写真は、和歌山県新宮市にある徐福公園内の写真である。私が、熊野速玉大社と前岡選手がいた新宮高校を見たいと思い、車を走らせている途中に、偶然見つけた観光スポットであった。施設の雰囲気は、前出の王仁博士の墓のあった公園とよく似ている。お墓と称するものはあったが、徐福の業績に関する展示物はなかった。
(因みに、前岡欣也投手とは大阪タイガースが獲得したものの、当時の幹部藤村富美男などが育成することができず、今の大谷翔平ぐらいの逸材がみすみす潰されてしまったという、65年前の悲劇のヒーロである。)
秦の始皇帝は紀元前221年に中国を統一、使用文字でも、新しい書体、篆書(てんしょ)を制定しているので、徐福が今の新宮市に渡来してきていたのなら、当然、漢字の篆書タイプのものが、弥生式時代の真っ只中の、時の日本国に伝わったはずである。が、この大切な点の証拠が今のところ何もないのである。
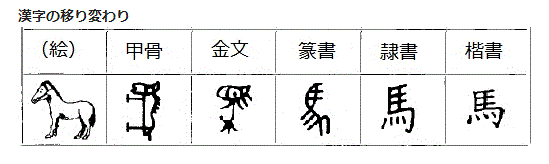 (ウイッキペディアを参照)
(ウイッキペディアを参照)
即ち、紙や墨汁痕は遺跡からは出てくる確率は低いが、古代文字の多くは焼き物の壷などに残されている。象形文字に近い篆書の自体が、弥生式土器に刻まれておれば、それはそれで、徐福の渡来を間接的に照明することになると思われるが、今は未だその事実は日本の公の歴史には登場していない。
しかし、倭の奴国は、以降も中国との接触はあった訳で、中国が魏の時代、卑弥呼の朝貢に応じて付与されたとする「漢委奴國王」と刻んだ金の印章が、九州志賀島で発見されている。
西暦238年、魏の皇帝・曹叡から邪馬台国の女王・卑弥呼に対して、金の印章を与えたとの記録が『三国志』東夷伝倭人条(『魏志倭人伝』)に記述されている。
卑弥呼が後の大和朝廷に近い処に宮殿を構えていたとすれば、何故に九州の片田舎の、遺跡の一つもない志賀島で、正にその金の印章が発見されたこと自体が謎で、未だに卑弥呼、即ち邪馬台国立地の論争の的になっているのは周知の通りである。
本稿では、文字が、こと伝達手段を果たすものとして日本民族に認識されておれば、金印が何処で発掘されても、それで十分なのである。文字を意志、古事の伝達手段として活用するためのシスティマティックな学習は、王仁博士の渡来に待つとしても、当時としても、文字の有効性とその活用の模索はあったとしてもよいのではないか。
2020.2/3朝日新聞によれば、松江市の田和山遺跡で国産の硯と推定されるものが見つかっている。
最近、弥生式時代の硯とする石製品の出土が目立つ。もしも本当に硯ならば、弥生式時代にも、墨で文字が書かれていた可能性がでてくる。字の形はなくとも、筆の遺物などあれば、文字が使われていた信憑性に拍車が掛かる、という訳である。
日本の文字の発祥に就いて、私が不可解とする部分は、年代的には更に遡る。
縄文時代の狩り中心の生活環境から、水田稲作の弥生時代への移り変わりは、何か大きい異変、外からの農耕民族の来襲と、その文化圏ができたと思われるが、それが紀元前500年頃とすると、朝鮮半島からやって来たその集団Aは、本当に文字を知らなかったのか。
当時、朝鮮半島の隣国は秦であった。当然交易はある。文字でも、記号でも好いのだが、それなくしては、現物を見せる以外に、凡そ、自分の経験を他人に伝えることはできないし、ましてや、世代を超えての継承は難しい。
多分、今の日本人は、その集団Aの子孫であるが、何でも模倣してしまう私達日本人の性格から看るのに、この集団Aが、同じ大陸にあって、その隣人にあった中国の周、秦の文字文明を知らぬはずがないと、私は考える。
この農耕民族の集団Aの子孫である現代の私達が、今、朝鮮語を話していないのは、集団Aが旧日本人(縄文式土着民)の大きい集団の中に同和、吸収されていった結果なのであろうが、漢字(篆書?)に相当する貴重な文字文明がその時代で消えていったのは、どうした結果なのであろうか。
朝鮮半島にあっては、漢文は、多分、今で言う第二外国語、英語だったのである。交易で、隣国の中国につながる共通語で有用であったのである。しかし、ガラパゴス状態の旧日本人集団の間に入ってしまうと、この漢文は何の役にも立たず、弥生式時代が進行する中で、この無用の長物は消滅していったのではないか。漢字という大文明が有効性を発揮するためには、大和朝廷でのようなシスティマティックに受け入れる態勢が整っている事が必要だったのである。と、私は勝手に想像するのである。
王仁博士は時の応神天皇の求めに応じ、皇太子の教育のために、論語と千文字を携え(300年頃)やってきたのである。それが解釈され、木簡に書かれ、万葉仮名となり、古事記(712年)で口語体に近く書かれ、日本の文字として定着するためには、実に、400年を要しているのである。
それでは大勢を占めた旧日本人はどんな文字記号を伝達手段として使用していたのか。興味に委せて、インターネットを繰ってゆくと、「ホツマ文字」が出てくる。日本固有の神代からの文字として、一部の学者の主張するところとある。が、今回はこれ以上には、話しを深めないこととする。
今の私達、良い技術があると知ると、コピーして直ぐに取り込んでしまう、小賢しい性(さが)に支配される勤勉な日本人であるが、過去においても、この有用も有用なる文字媒体を見逃すはずはない。だから、私は、古代日本には文字がなかったと書かれている歴史書と、私達の性(さが)との整合性には、こんな風に考えてゆかなければ、どうしてもガッテンが行かないのである。
(2020.04)
(2020.08 訂正:藤村富雄-->藤村富美男)
| 
