|
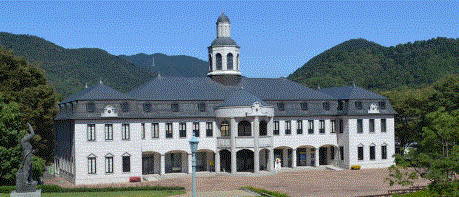 淡路島の鳴門大橋を通り過ぎて、高松自動車路を20キロ走った処に「ドイツ村」がある。山間の集落に忽然と瀟洒な西洋のお城のような建物が現れる。パンフレットには、ドイツ人捕虜の収容所と有るから、私は、シベリヤ抑留の日本人が収容されていた場所とか、「戦場に架ける橋」で見た欧米兵の収容施設の、煉瓦作りの平屋を想像していた。
淡路島の鳴門大橋を通り過ぎて、高松自動車路を20キロ走った処に「ドイツ村」がある。山間の集落に忽然と瀟洒な西洋のお城のような建物が現れる。パンフレットには、ドイツ人捕虜の収容所と有るから、私は、シベリヤ抑留の日本人が収容されていた場所とか、「戦場に架ける橋」で見た欧米兵の収容施設の、煉瓦作りの平屋を想像していた。
このイメージと、現物の景色に融け込んだ白い洋館とのギャップに頭の整理が追い付かないうちに、綺麗な建物内に入り、設けられた展示物の順路に沿って廻るのだが、パン工房があって、板東村の住民が教えられたとか、ベートーベンの第九交響曲を日本で初めて演奏している姿の人形があったりで、およそ、捕虜の悲惨さを再現している展示は何もない。今は日独の友好関係の絆に貢献しているとあって、「浮虜」と「捕虜」違いなのかと結論づけて、そこを退出することとなった。
後日詳しく調べてみると、「浮虜」と「捕虜」の意味は全く同じ、実は、この「板東浮虜収容所」は敵国捕虜の収容施設としては、後世にその名を残こすほどの特異な施設であったらしい。
以下、『ドイツニュースダイジェスト』や『ウィキペディア(Wikipedia)』を参考にしながら「板東浮虜収容所」とは何かと、調べてみた。
1914年に第1次世界大戦が勃発すると、日英同盟を結んでいた日本は、それを理由に中国・青島を拠点としていたドイツに宣戦布告した。この戦い、圧倒的な兵力の日本軍にドイツ軍が降伏する形で、3カ月もしないうちに終結した。
戦死者は、日本、ドイツ各々270、183名、であり、ドイツ国の全面降伏が1918年11月であった事を考えると、大戦初期でもあり、双方何かを死守する程の戦闘ではなかった。日本国に連れて来られたドイツ兵捕虜は約4600人。そのうち約1000人が「板東俘虜収容所」に収容された。
「板東俘虜収容所」の所長は 陸軍歩兵中佐であった松江豊寿(44歳)、戊辰戦争に敗れた会津藩士の子としての経歴を持つ。「武士の情け、これを根幹として俘虜を取り扱いたい」と、捕虜を収容所に迎える前日、松江は部下にそう伝えた。
ドイツ兵捕虜の中には各分野の専門家がいた。日本政府は、これを機にドイツの科学技術を国内に導入しようと、ドイツ兵から指導を受けるよう各収容所に指示していた。経済・政治学から、ウイスキー、ビール醸造、ソーセージやパンの製法、楽器演奏の指導までである。
「板東俘虜収容所」内にも、パン工場が建てられ、共同農場ではトマトや赤ビート、キャベツなど、それまで栽培されていなかった野菜の栽培指導が行われた。牧場では、ドイツ兵の指導により、牛乳の生産量が5倍増しになった。
指導に赴くドイツ兵捕虜には見張りが付いていなかった。捕虜の待遇としては異例のことだが、ここ板東では一定の秩序の下、捕虜には生産労働や文化活動が許可されていた。日本語教室や芸術活動、各種スポーツを楽しむ捕虜の活動は、町の人々の興味・関心を引き、見学者の訪問も絶えなかったそうだ。収容所で結成されたヘルマン・ハイゼン楽団によって、1918年6月1日に、ベートーベンの交響曲第九番が合唱付きで演奏された、という。
この「板東浮虜収容所」は、私達の捕虜収容所の概念とは、およそ懸け離れたものだった、ということらしい。しかし、「奇跡の浮虜収容所」といわれるようなものが、一司令官の採択でできあがるものなのであろうか。
私はここドイツ村を、およそ25年前に一度、それから10年ほどしてから、もう一度訪れている。
「板東浮虜収容所」では、捕虜達自身の自治組織があって、新聞を発行している。所内フットボール大会をどの様に運営していくかの告知がある。新聞の名前は“Die Baracke(兵舎)”である。
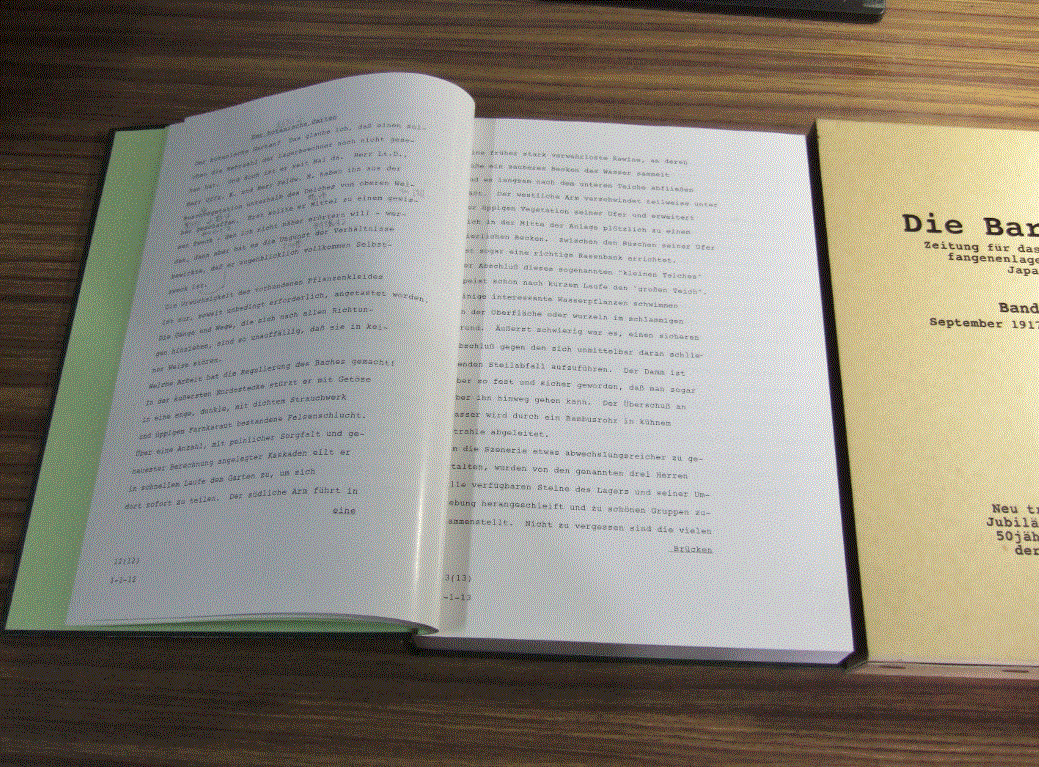 発行当時はガリ版刷りのものであったが、今、資料として出回っているものは、例えば私が買って帰った、新聞約半年間を纏めて活字に摺りおろした製本版である(写真参照)。私は、未だ10数頁しか繰っていないのだが、購入当時は、自分で原書を読み、ドイツ人気質を知りたかったのかも知れない。
発行当時はガリ版刷りのものであったが、今、資料として出回っているものは、例えば私が買って帰った、新聞約半年間を纏めて活字に摺りおろした製本版である(写真参照)。私は、未だ10数頁しか繰っていないのだが、購入当時は、自分で原書を読み、ドイツ人気質を知りたかったのかも知れない。
私が広島にいた30歳の頃、通勤バスの中で、畑口さんという方とよく顔を合わせた。畑口さんは近所にお住まいで、その昔、第2次世界大戦後のシベリァに抑留された経験の持ち主だった。
その畑口さんが仰有るには、日本兵の私達は、空いた時間ができると、自家製の駒で将棋を指し、花札をして群れていた。ところが、ドイツ兵は違った。同じように抑留され、作業をさせられていたのではあるが、休み時間ができると、何時も、仲間内で先生を出し、その人を囲んで、勉強というのか、しきりに議論をやっているのであった。
この違い何なのでしょう。私はこの経験を、ドイツ人気質を、誰かに伝えておきたい気持ちに駆られるのですよ、と畑口さんは通勤バスの中で、しきりに私に話しかけてくれた。
私は40歳の頃、大阪のドイツ文化センターにあったドイツ語学習塾に5年間ほど通ったことがあった。まるで、義務教育のように、教育プログラムはかっちりとできている。
その内容であるが、教科書には始めから、カール・マルクスの仕事に関する哲学、アイシュタインの相対性原理の基本が出てくるのである。多分、ドイツ人は、日本人の学者のようには難しい言葉を使わないで、日常の言葉を使って、難しい経済論や相対性原理を討議し合う習慣があるらしい。しかもそれを話すドイツ語の文章構造である。
英語では、I love you, because you have a car.
ドイツ語 Ich liebe dich, weil du ein Auto hast.
西洋人の文化は、主語の後には必ず動詞が来て、文章全体を支配するだが、ドイツ語の従属文(weil 以下)では、動詞(hast =have)は英語と違って、必ず文の最後に来る。これを「後置」と言うが、何故に、使うと決めた動詞をわざわざ最後に持って来て、文を締め括るのか。それは正に言葉の緊張である。
別の言い方をすれば、ドイツ人は英国人より、話す内容をきっちりと組み上げてから言葉にするのだと思われる。それが、ドイツ人気質の真面目さに通じていると、私は考えている。
さて、収容所内でその当時に発刊されていた“Die Baracke(兵舎)”である。ちらっちらっと目を通すのだが、その内容は、捕虜が収容所内の自治組織として主催するスポーツ大会のサッカーやテニスの運営方針、小さい植物園を造ろうとしていること、日本の諺の紹介など、これらは素直に解るのだが、中に砲術に長けた人がいて、最近の大砲の性能言及に及んでいる。ここは敵国、まるで、何でもありの自由紙ではないか。
一冊子が、私が見ている活字版では、20ペイジにも及んでいる。収容者の数1000部発行されていたかどうかは分からないが、B−5サイズのわら半紙の両面に、ガリ版刷りの20頁である。各週発行である。
私も中学時代は、学級新聞に明け暮れていたが、とにかくこの“Die Baracke”には、5人の編集者がいたとかいうが、真面目一途の、製作のエネルギーが感じられる。
その実直さ故に、多くの板東の人達が、私がバスで出遭った畑口さんのように、ドイツ人に感銘を受けたのではなかったか。
収容所が日独交流会館のような様相を呈していくにつれ、町の人々はドイツ兵捕虜を「ドイツさん」と、親しみを込めて呼ぶようになった。ということである。
だがしかし、「板東俘虜収容所の奇跡」は、収容所の所長松江豊寿の英断に加えたドイツ人気質だけで、その説明ができるのであろうか。
(以下は、2018.6.1 付けの天声人語の要旨である。)
ベートーベンの交響曲第9番が日本で初めて演奏されて100年を迎える記念の日である。この曲が演奏されたのは徳島県鳴門市にある「板東俘虜収容所」で、捕虜のドイツ兵によって行われた。捕虜にこの第九交響曲を演奏させている。
もし、鳴門市「板東俘虜収容所」にあったこの度量を、第二次世界大戦前の日本人が継続して持っていたら、太平洋戦争で日本兵は玉砕に走ることはなく、日本人による敵国捕虜への虐待もなかったのではないか。
この記念の年2018年には、「俘虜収容所の奇跡」はテレビでも取り上げられ、ドイツ軍の捕虜の子孫も式典に訪れて日独親善交流の映像が我々のお茶の間にも届けられた。
2019年3月16日にあったNHK番組「ぶらタモリ・鳴門編」では、この地で亡くなったドイツ人捕虜のお墓を、今に守り継ぐ日本人の姿を撮し、敵国捕虜に親切に接したのは、お遍路の文化が培われた鳴門市民の「おもてなしの心」であったとして、物語を結んでいる。
「板東俘虜収容所の奇跡」に対するこの説明には、「そうだったのか」と私も納得した。
今は、2020年5月である。新型コロナウイールス禍の非常宣言に一応の終結が打たれるかどうかの瀬戸際である。徳島県の街の、こんな様子がテレビでも報道され世間を賑わせている。
{徳島県では、県外ナンバーの車に「暴言やあおり運転、投石、傷つける」といった差別的行為が発生している。その差別行為から自己を防衛するため「徳島県内在住者です」と明記した車用のステッカーも販売されている。
徳島県は感染者が24日現在で計5人と少ない。飯泉知事は21日に「感染リスクの高い地域との往来は危険」と、県外から人の往来を調べるために、県外ナンバー車の数の調査を指示したらしい。24日の会見では、「強いメッセージになり過ぎたかもしれない」と釈明した。}(福井新聞2020年4月25日より抜粋)
このテレビ報道を見て、「板東俘虜収容所の奇跡」を、お遍路の文化で培われた鳴門市民の「おもてなしの心」とする帰結には、些か懐疑的にはなってきた。
いや、「おもてなしの心」にも色々あって、広い慈悲の心ばかりではなく、そこは人のやること、多少の選別があっても、「おもてなし」はやっぱり「おもてなし」と解釈するのが、私達、大人の納得の仕方なのかも知れない。が、然しである、本当のところは、お遍路の文化の「おもてなしの心」は、一つであって欲しいと願うのは、私個人の感傷か。
(2020.05)
|

