|
◇レンタルなんもしない人◇
NHK「ドキュメント72時間」で、「レンタルなんもしない人」というのがあった。
「何もせず、ただそこにいるだけ」にも拘わらず、さまざまな依頼が殺到している。どんなレンタル依頼があるのか、その「なんもしない人」とはどんな人であるのかを、72時間に亘ってその様子を撮影しているのである。
レンタル料は、そこまでの交通費と飲食代等の諸経費のみ、便利屋ではないから何にもせず横に立って、受け答えだけをする。Twitter上でそんな提案を持ち掛けたところ、話題となり、現在、依頼が殺到するまでに。一体どんな依頼があるのか。
離婚届の提出に付き添ってほしい、自分の民事裁判を傍聴してほしい、結婚式を眺めに来てほしい、造った料理を一緒に食べてほしい、などなど。例えば、私個人的に言っても、何十年も住んでいない田舎の実家に帰るとき誰かが一緒に付いて行ってくれればいい、路上ライブをするので見物人の格好で立っていて欲しい、夜道に前を歩いてほしい、などとの希望は有るが、わざわざ待ち合わせをしてまで、それを見知らぬ誰かに頼むのか、というところでは考えるべき問題がある。それを、人は気軽に頼んでいる。正に驚きであるが、Twitterという‘のり’はあるのかも知れない。
いや待て、このレンタルさんが、‘綾瀬はるか’であったなら、一緒にお茶を飲んで欲しいと、私がレンタルするのは頷けるのではある。が、これは本末転倒、ジャニーズに無料で逢えるのならば、要件などは後から付いてくるのである。本質は、レンタルさんが氏素性の判らない怪しげな人物であるにも拘わらず、無料ならば、敢えて頼もうとする位の、要件を抱えている人がいる事の面白さである。
レンタル家業が有名となり、レンタルさんが、‘綾瀬はるか’程に品好く憧れの人物となってしまうと、レンタルさんが始めた冒険の意義も色褪せて行くということか。
このレンタルさん、森本祥司氏35歳、外見は文学青年のひ弱さを持つ。京大農学部卒、一般会社に就職したが馴染めず、「プロ奢(おご)ラレヤー」に触発されて、この路を採ってみたと言う。妻子あり。どちらかといえば、中性的で感情も表さない点が依頼者に好感度が高い要因の一つであろう。
因みに、「プロ奢ラレヤー」やとは、何処でも寝られるぐらいの図太い神経の男性だが、Twitter上に、場所を指定して、「今晩の夕食と寝場所を提供してくれる人は居ますか」と募集して、提供応募者の好意に甘える。提供者は結構現れるらしい。提供者は、彼の貴重な体験談、彼はチェコにも行った経験を持つ、即ち、破天荒な人生哲学、生き方の手本を期待していると思われる。
さて、レンタルさんの収入は何に拠っているのか。レンタルを依頼する人たちやその依頼内容を取材して、レンタルさんは本を出版している。その余波で、ドラマ化の原作者としての収入、また、「レンタルなんもしない人」としてのインタービューを受ける報酬などがあるという。
Twitterという世界に上手く乗って、本来念願だった、文才を生かした人生を切り開いたというところであろうか。よかったねと、今のレンタルさんの開発者としての冒険には素直に拍手を送りたい。
然し、レンタルさんの取材には、お互いの人生には深くは関わらないという暗黙の了承がある。従って、話の面白さの深さには自ずと限界が来るのかも知れない。これをどう乗り切るか。或いは、10年後、レンタルさんにはまた新しい着想があって、今の私には想像も付かないような独自の展開が待っているのかも知れない。
10年後のレンタルさんの往き方を是非注目して措きたいと、思うのである。
◇自動翻訳機◇
私は今80歳である。「働かざる者食うべからず」を信奉している。従って、未だに求職中である。
私は、或る団体下の翻訳グループに所属している。市販される技術書の翻訳を手掛けており、それも生業と言えぬこともないのではあるが、この頃書籍は売れないの煽りを喰らって、実利のある報酬を得るところには行き着かないのである。
そのグループに或る日、もし好かったら、特許を専門とする翻訳会社のトライアルを受けてみませんかとの、お話しが舞い込んだ。今の翻訳グループか、お話しの翻訳会社の何れを本職とするか、アルバイトかの区別はともかく、私はその会社のトライアルを受けてみようと思い立ったのである。
私は、ガラスやセメント関連の技術者であった。もう20年は昔のことだが、定年後に初めて勤めたところが、大手の特許事務所であった。電子関係の特許技術者となり、明細書などを担当したのではあったが、できれば、特許翻訳部門に移りたいと思っていた。簡単に移れなかったのは、英語から日本語訳の方はともかく、日本語を英訳する翻訳力は未だ乏しいと思ったからであった。
その後、特許事務所を離れて長い期間があって、今回再び、特許を専門とする翻訳会社のトライアルを受けてみようとしたのには訳がある。今の技術翻訳書の出版業務に参加している内に、単語をいちいち辞書で引く代わりに、パソコン画面から単語をコピーして、インターネットに無料で提供されているWeblio とか Google 翻訳の画面に貼り付け作業をするだけで、簡単に意味が分かる。最近では、長文をコピーして貼り付けるだけで、1頁の長さのものでも、直ちに翻訳されて出てくる。
さすれば、この機能を使えば、英作文の技術があろうが無かろうが、日本語の特許明細書から一応の英語の明細書は直ちにできあがって来る。後は、その翻訳が適切かどうかの、正にその分野の専門家のチェッカーとしての、私の専門知識だけが重要となるである。個人の頭脳の英単語の蓄積量や、日本語から英文への翻訳技法に長けている、それ自体はそれほど重要ではない時代が来たのである。これなら私も、特許の翻訳家としてやっていけるのではないかと、この歳で改めて思ったのである。
トライアルというのは、時間内に課題を翻訳させて、その翻訳成果物が会社の持つ基準に到達しているかどうかを見るものである。予め決めた時間に、翻訳会社の課題がE−メールで自宅に送られてきた。4時間後に再びE−メールで回答を送り返す。テスト課題は実際に有りうるような特許の明細書である。そこに、どんな翻訳機を使っても良いと指示してある。よほどの翻訳熟練者でも、辞書を片手には、翻訳しきれないような課題の量ではある。従って、始めから翻訳機、私の場合は Google 翻訳の使い方が勝負になる。
このトライアル、ちょっとした翻訳械使用上の不慣れな部分が出た。が、全体としてはまずまずだと思った。然し、結果は、翻訳会社の評価では、即戦力とはならないということで、不採用となった。落とされたということでは多少頭に来るのだが、それは仕方がない。私が思う以上に、合格レベルが高かったのである。然し、トライアルして分かったこともある。
私は働く、働くと言っているが、肉体的には、例えば、工場内で何かを測定するのは危険と思わないでもない。肉体をあまり使わない翻訳業は高齢者向きだと気が付き、トライアルしてみると、自分の採点では、私は日本語から英語への翻訳はできたのである。
が、思い返すと、特許分野は、時間を勝負とするから、高齢者には精神的に悪い、ということを忘れていた。この分野への挑戦は止める。それなら、技術書の翻訳ばかりでなく、広く商業、或いは工業的な翻訳分野に的を広げて、自分の求職活動を行ってみるのはどうか。
だが、それ以上に、このトライアルで判ったことがある。世の中アット言う間に、AI(artificial intelligence人工知能)の進化に伴い、というべきであろうか、多くの翻訳機械が出て来たことである。AIロボットとかの行く末を見ている間に、翻訳をやっている私達が気づかない内にも、翻訳技術の世界が変わったことである。「翻訳機」をキーワードにインターネットで調べてみれば、例えば、【2020年オススメの翻訳サイト・アプリ・ツール20個を徹底比較】のサイトにもあるように、20種類もの機械翻訳システムの性能比較が出ている。私がやっと慣れ始めたGoogle 翻訳 以外にである。
優れた翻訳するためには、語学を大学で履修し、外国に留学して外国文化を知るといった王道は、もはや必要がないのかも知れない。例えば、日本語で書いた手紙をドイツ人の友人に送ろうと思えば、季節の挨拶、拝啓、敬具の位置、必要性など些細な事柄を別にすれば、Google 翻訳に日本文を挿入しさえすれば、無料で、瞬時に、こちらのドイツ語の理解の有無を越えて、相手方には手紙の十分すぎる内容がドイツ語で伝わる。E−メールでのやり取りがいい。相手方が手書きで返信してくると、その手書き文字を活字に起こしてやらねばならない。その手間が省けるからである。翻訳機は手書きの文字は読めないのである。
私はトライアルを受けてみて、初めて翻訳機がこんなに普及していることに驚きもするのだが、英語は実用語学、即ち、聞いて話せる、やれネイティブだとの英語教育を必死に進めている諸先生にはこの現状が理解されているのかなと心配になってきた。
昔、算盤ができなければ、数学ではハンディがあった。今や、100円ショップで売っている電卓が有れば、日常の計算に困ることはない。英語学習でいえば、むしろ昔の英語の教科書に戻り、ごく基礎的な知識を習得して措きさえすれば、あとは自動翻訳機や機械翻訳を、電卓代わりに使えば、日常の英会話などの処理は無論のこと、興味と才能さえあれば、英語を日本語と同じくらいに駆使できて、国際情勢を股に掛けること位、それほど難しくない時代に来たのではあるまいか。
変な時代が、AIに依ってもたらされたものではある。
◇分身ロボットカフェ◇
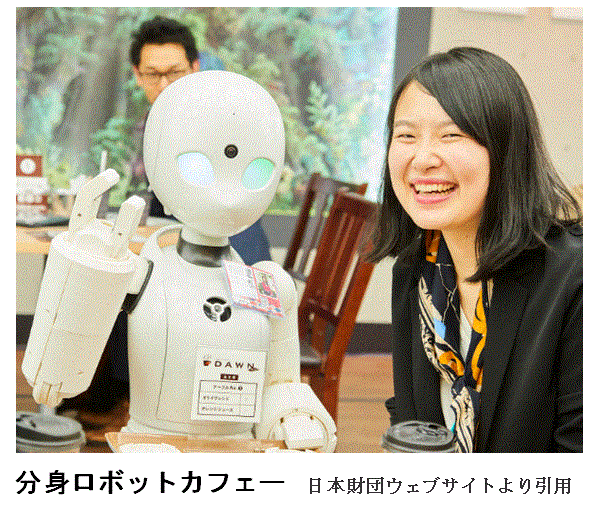 新型コロナ・ウィルスの到来によってリモート・ワークの時代が来たと報じられている。在宅勤務や遠距離会議でテレビを通じた対話や会議は当たり前になった。その大本となる大容量通信の設備、即ち、光回線の付設、高速度通信を可能にする機器が開発され普及していたからこそ、社会はリモート・ワークの時代に即応できたわけである。そういえば、ウィルスの到来の数年前から、5G(第5世代移動通信システム)という言葉は踊っていた。
新型コロナ・ウィルスの到来によってリモート・ワークの時代が来たと報じられている。在宅勤務や遠距離会議でテレビを通じた対話や会議は当たり前になった。その大本となる大容量通信の設備、即ち、光回線の付設、高速度通信を可能にする機器が開発され普及していたからこそ、社会はリモート・ワークの時代に即応できたわけである。そういえば、ウィルスの到来の数年前から、5G(第5世代移動通信システム)という言葉は踊っていた。
この5Gの高速通信網によって、それAI(artificial intelligence人工知能)で顔認証ができるとか、IOT(Internet of Things 家電をインターネット操作)で家電が何処からでも遠隔操作できる、自動車の自動運転可能となるなどと、何か異次元の世界から押し寄せてくる巨大な黒い圧力に曝されているような、我々の日々ではある。そこに、私が偶然に見たテレビの中に、「分身ロボットカフェ」(NHK2020.5/31目撃!にっぽん 再)というのがあった。
ロボットと聞くと、我々の世代は手塚治虫の「鉄腕アトム」である。人間より明晰な頭脳と正義感を持つ、さらに100万馬力の力持ちで空も飛ぶ。それに較べると、顔は宇宙人、手は天使の羽根のような形をして、背丈から推しても幼児のような何処か未完成な姿と動きの「分身ロボット」ではある。そのロボットが、或る東京のカフェーで、お客さんの注文に応じて、実際にコーヒ店のサービス嬢の動きをしているのである。
その店のテーブルに座っている客人は、楽しそうに笑ったり、ロボットに向かって質問したりしている。だが、このお客さん達は、多分、ただ物珍しいロボットの給仕を見に来ている訳ではないのである。そのロボットを、遥か遠くのベッドの上で操縦している重度身体障害者のひたむきさを想い、ここまでに辿り着いた「分身ロボット」発明者の心意気に感動していたのである。
分身ロボットの発明者は吉藤健太朗 (年齢 32歳)、常に、手塚治虫の「ブラック・ジャック」の様なトレンチコート風の黒い衣装を付けている。この衣装、吉藤氏が自ら語るには、「自分には科学者の着る白衣が似合うと思ったのだが、白衣はごく一般的、だが黒は無いからと、自分で縫製した黒衣を造った。手品師のようにスマホの取りだし口もある」らしい。 異様な風体とは別に、語り口、表情は実に優しく誠意がみえる。
小・中学時代は不登校児童、だが、母親が申し込んだロボットコンテストで優勝、その後工業高校に進学、電動車椅子の研究開発に取り組み、科学技術コンテスト文部科学大臣賞。早稲田大学在学中にオリィ研究所を設立、分身ロボットOriHimeを誕生させた。2015年、寝たきり秘書、番田雄太氏を入所させる。
私は2年ぐらい前に、これも偶然だが、吉藤健太朗が語る、番田雄太との邂逅と別れを、どこかのテレビで見ている。
番田雄太氏は4歳の時、交通事故で脊髄損傷し20年間呼吸器を付けての寝たきの生活、学校も行かず友達も居ない。唯一の動く顎を使ってPCを操作し、2013年に吉藤健太朗をネットで見つけて分身ロボットOriHime開発に参加したのである。
番田雄太氏の社会参加については、吉藤健太朗は先ず、健常者の常識との大きな意識格差を埋める研究(自信5段階説)を共同でやりつつ、分身ロボットカフェの開発に着手していたが、2017年春、番田雄太氏は還らぬ人となった。その分身ロボットカフェ実験の開始は、2018年に始まった。
今先端を行く人工頭脳AIは分身ロボットOriHimeには入っていない。その頭脳の役割を、遠隔地のベットの上で、障害者がやっている。ロボットの目から来た客の映像をベッドの脇のモニターで見つつ、「コーヒは如何ですか」声を出す。客の反応を見つつ、コーヒを手渡す動作をPCパネルに顎でタッチして、指令する。多分将来を絶望視していた重度障害者が、こうして勤めて、自ら給料を稼ぎ出しているのである。社会参画ができる喜びで、夢ある将来を自ら企画しょうとする迄になって来たのである。
分身ロボットが動いている東京のコーヒショップは、AIの無い、正にその人間のつながりが醸し出す暖かさで満ち充ちているのである。
私は奈良に住むが、年に一度くらいは東京に所要がある。昔は、「英会話喫茶店」を探して恵比寿周辺を歩いたこともあるが、今度東京に行くときは、「分身ロボットカフェ」の有る場所を予め調べて、絶対に訪ねたいと思っている。
其処でこのシステムの発明者、吉藤健太朗氏の姿を偶然にも見ることができるなどとは思わないが、テレビでみて、そしてまた、氏の資料を読んでみると、多くの若き天才がそうであったように、吉藤健太朗氏の健康は、やっぱり気になるのである。
どうかご自分の健康にも留意され、この幸せのシステムを普及させて戴きたいものである。
(2020.07)
(2020.08/01 分身ロボットカフェ写真挿入)
| 
