|
 実は、このエッセイを書く切っ掛けにもなったのだが、今年はやけにドクダミの花が白く綺麗だなと思ったことがあった。普段はどこか暗くて馴染めない野草である。すると、どうだ。天声人語に、「ドクダミの真っ白い花、それを綺麗だと思ったのは、実は今年が初めてである。」(2020.6/13付け)としたものがあった。こんな目立たないところにも、ちょっとした異変は起こるのだった。
実は、このエッセイを書く切っ掛けにもなったのだが、今年はやけにドクダミの花が白く綺麗だなと思ったことがあった。普段はどこか暗くて馴染めない野草である。すると、どうだ。天声人語に、「ドクダミの真っ白い花、それを綺麗だと思ったのは、実は今年が初めてである。」(2020.6/13付け)としたものがあった。こんな目立たないところにも、ちょっとした異変は起こるのだった。
今年は特に鮮やかに映る。天候のせいかもしれない。雨が多くむしむしする。気分的には、コロナ禍で世間が沈滞しているせいかもしれない。青黒さが増す低い緑の葉を背景に、花の花弁をわざわざ覗い見たくなるほどに、純白の輪郭を浮きだたせて凛と咲いていた。
今を去る8年ほど前に、母親が尼崎にある有料老人ホームに入居した。亡くなるまでの5年間、三日に一度を私の当番日と決めて、その一日を母親の部屋で共に過ごした。母の最後を自宅で共に過ごすという理想の形は取れなかったのだが、老人ホームでの穏やかな一時があったことは、それはそれなりに好かった、との思いはある。
その尼崎駅につながるJR最寄りの河内磐船駅迄は、我が家からは、往きの下り道では一時間、帰りの登り道では1時間半の道程である。片道で数えると、週5回は同じ道を歩いたことになる。登山の遊歩道ともなっているので、植物は嫌でも目に入ってくる。その自然の季節の移ろいを、この「ゴンちゃん倶楽部」の一こまを借りて、定点観測風に世間にお伝えするのはどうかと思ったこともある。無論写真は欠かせない。何時もカメラは持って歩かなくてはならない、などと考えている内に、この道を頻繁に歩く必要もなくなったので、何時しかその企画は放棄されたままとなっていた。
道に沿った全体の風景は季節ごとに変わる。道の片隅にクローバのように現れるのは“猫の目草”である。春、季節がよくなると、何時しかこの草は他の草にその場所を明け渡している。山桜が咲き、“水芭蕉”の純白の仏炎苞(ぶつえんほう)が見られる。“水芭蕉”は近畿地方では珍しいかも知れない。20年前、「くろんど園地」の管理人さんが20本ほどを湿地に植え付けたのではないかと思うが、毎年見ていると、増えて大きくなり、今では200本以上になって、ちょっとした観光スポットともなっている。
その頃は“落羽松”が青く立ち上がり、卯の花が咲き、のり卯木の白い花の房が現れる。途中稲作地帯もあって、秋の初めには、畦道沿いに曼珠沙華の紅い列が見られ、たわわに実った柿の木が山中あちこちに見られる。冬は、紅葉樹木が少ない山であるので、“こ楢(なら)”が葉を落とすと、常緑の木に落ち葉色が混ざった冴えない風景となる。
定常的とも見られる季節の移ろいとは別に、その年にしか起こらないような異変も見られる。「楢枯れ」などはその典型で、“こ楢”の根本に粘土状に黄色い土が溜まってゆく、それはどうやら木の幹にできた孔から吹き出ている樹液と木屑の混合物からできている。この孔はカシナガ虫による穿孔痕で、それが持ち込む菌類で“こ楢”の幹内の導管が詰まり樹木が弱ると、たちまち“かわら茸”が幹表面に取り付く。やがて“こ楢”の樹木からは、アット言う間に緑の葉は落ちてしまって、枯れて朽ちた大木が残る。
“こ楢”や“粗樫”にドングリが殆どできない年もあれば、落ちたドングリで足場の踏み場もないほどできる年もある。青虫、毛虫が多くて、歩いている目の前をするすると糸を垂らして下りてくる。気は付けてはいるのだが、電車に乗ってからも背中の方からその青虫が現れたりする。目纏虫と言って、涙が好きなのか眼に向かって寄ってくる蚊のような虫の大発生があると、山道は、団扇かタオルでパシパシやりながら歩かざるを得ない。不思議なことに、これらは或る年に限って起きるのである。
藤の紫の房が山の森を覆っていることもある。蝮(まむし)と5回位遭遇した年もある。山鳥といって、雉より一回り大きい、なんと桃色の2匹が目の前を通っていったこともある。
 妻がどこかの羊歯(しだ)の会に所属していたので、妻に附いて歩く内に、幾つかの羊歯の名前は覚えるようになった。
妻がどこかの羊歯(しだ)の会に所属していたので、妻に附いて歩く内に、幾つかの羊歯の名前は覚えるようになった。
だから歩いていても、つい、道傍の緑をその眼で探っていく。先ず一番多いのは“紅羊歯”である。何で「紅」が名前にあるのかと思っていたら、朝日を受けた若葉は紅かった。納得である。“湿気羊歯”、湿気の多いところに見られる。“柔ら羊歯”、“針金羊歯”、縁の隈取りがしっかりしているのが、“犬羊歯”。もっと葉がしっかりしている“イタチ羊歯”、茶人が好む侘び寂びの“しのぶ”、“軒しのぶ”。何時も大きく青々しているのは“両面羊歯”、“ふもと羊歯”。蘇鉄の葉に似ているかどうか“ヤブソテツ”、艶のある “鬼ヤブソテツ。”
羊歯というのはどれも同じ、十把一絡げの様にも見える植物だけに、その名前には先人の苦労の跡が見える。手振りでは駄目、さすがに絵に描くしかないのだが、縄文時代から人は脈々と、この羊歯の名前を伝えてきたのである。口で伝えるために具体的で身近なものの名を借りたのである。差別用語など何のその、とにかく違いを見分け、伝え措くために分類したのである。ここに言語のそもそもの意味がある。
裏が白いので“ウラジロ”、雉の尾っぽのように垂れ下がっているから“雉の尾羊歯”、猪の手のように茎に毛が密生する“イノデ”、葉が 垂れ下がる様が獅子の鬣(たてがみ)のようにも見える“獅子頭”、小さいが、細長い葉身を虎の尾に見立てた“虎の尾羊歯”、葉の先端が稲穂のような “穂羊歯”などなど。“虎の尾羊歯”に似ているが、同じ崖に生えているのが“コウザキ羊歯”、津島の神前説がある。もう少し下等と思われる“かた比婆”。
秋の栗、松茸の緩衝材の“コシダ”。“ゼンマイ”、“いわがねゼンマイ”、“ひめワラビ”、“イノモトソウ”。一本葉の“三手ウラボシ”、蔦のように絡まっているのは “豆羊歯”、“蟹羊歯”。いやはや、私の通う道だけでも、羊歯と称するものざっと30種類に近い。
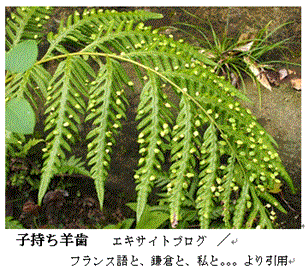 昔、「奈良県の羊歯といっても、何で奥山深く分け入って新種を探さないのか」と、妻にその採集方法を聞いたことがある。「植物の歴史は古い。奥深い山に群生すれば、必ず道端にも現れる。」という妻の言葉には些か感動したのであるが、こうして、門前の小僧のようにして植物を見ていると、或る特定の場所、尾根を隔てたところで見た、例えば、“子持ち羊歯”(葉の表に無性芽と呼ばれる芽をつける)は、それ以外の場所、例えば、この山道沿いでは見たこともない。それを妻に言うと、「95%はそうかも知れないが、中には、滝の飛沫が飛ぶような秘境にしか現れないものもある」らしい。何だ、それなら羊歯に限らず、植生では当たり前のことではないか、感動しただけ損をした。
昔、「奈良県の羊歯といっても、何で奥山深く分け入って新種を探さないのか」と、妻にその採集方法を聞いたことがある。「植物の歴史は古い。奥深い山に群生すれば、必ず道端にも現れる。」という妻の言葉には些か感動したのであるが、こうして、門前の小僧のようにして植物を見ていると、或る特定の場所、尾根を隔てたところで見た、例えば、“子持ち羊歯”(葉の表に無性芽と呼ばれる芽をつける)は、それ以外の場所、例えば、この山道沿いでは見たこともない。それを妻に言うと、「95%はそうかも知れないが、中には、滝の飛沫が飛ぶような秘境にしか現れないものもある」らしい。何だ、それなら羊歯に限らず、植生では当たり前のことではないか、感動しただけ損をした。
今年は春からコロナ禍で、訳の分からない空気に支配され、何となく私の活動も鈍る。妻が、駅の通路で転んで坐骨を痛め、「家で余り動かないと、頭が惚けてきた」と脅かすので、仕方がない、近くの、「“くろんど池”の周りを散歩するか」と、とろとろした歩様で毎日1時間を二人で歩くことに決めた。だが歩いてみると、自分の老体の動きには苛立つのである。腰も痛いし、脚の筋肉も攣りかける。平衡感覚は鈍っているし、まともな歩様ではないのである。
ワンちゃんが生きているときには、月に2度ばかりはこの付近を散策したのだか、最近はめったに足を運ばない様になっていた。このコロナ禍のお陰とも言えようか、毎日のように夫婦で歩いて9ヶ月、この池、散策には実に良い処だと、今更ながらに気付かせて貰った。
旅館もレストランもあり、貸しボートも充実している。明るくって紅葉も映える。お店の人とも、毎日声を交わす。老人の釣り人が朝から竿を垂れ、平日というのに釣り竿を持った若者も多い。余りにものんびりしているので、この活気のなさは停滞する日本の縮図を見ているようで、不気味といえば、不気味である。
妻は、杖をつき、よろける足で双眼鏡を持ち、野鳥観察をしているかと見ると、小さな紅い花を付けた“水引草”や“金水引草”に見入っている。
 道の中央に存在する“大葉子” 、道脇にあって種がくっつく“盗人萩”、“猪の子槌”、この“盗人萩”、種ができる前には、“水引草”と同じように桃色の米粒ぐらいの花が細長い花序に並ぶ、よくよく見ると、独特の茶花の趣が確かにあって、こんな風には“盗人萩”を見たことはないなと、この時期、落ち着いて雑草を見る機会ができたことは、良いのか悪いのか。
道の中央に存在する“大葉子” 、道脇にあって種がくっつく“盗人萩”、“猪の子槌”、この“盗人萩”、種ができる前には、“水引草”と同じように桃色の米粒ぐらいの花が細長い花序に並ぶ、よくよく見ると、独特の茶花の趣が確かにあって、こんな風には“盗人萩”を見たことはないなと、この時期、落ち着いて雑草を見る機会ができたことは、良いのか悪いのか。
花が煙管(きせる)の頭の“雁首草”、“段戸襤褸(ぼろ)菊”、“センダン草”、狐のしっぽのような“えのころぐさ”、小さな紫色の花がやがて立ち上がってキツネの尾房を付ける“狐の孫”、万葉集に聞く“八重むぐら”。
妻と見合いをした後、何ヶ月か経って奈良近くの渓谷を散歩しているとき、木から出た樹液がねばねばするのを触らされて、“餅ツツジ”という名を教えられたのを想い出す。
妻とは見合いで知り合ったといったが、我が人生、まさか伴侶を見合いで見付けるなどとは思わなかった。伯父、叔母の紹介である。彼女は理科の教師であり、私は、否応なく理科コースを採った研究職だったので、伴侶には文化系の人が良いと思っていたし、プリーツスカートと、黒い長い髪という構想も有ったのだが、それからも外れていた。
妻は、どちらかというと、従順ではなかった。昔、自動車を持つことを、私は良しとしなかった。が、妻は新婚当時少し教職から離れた間に、自動車学校に行き、教職に復職すると、中古自動車を買った。
妻は、妻の母と、妹が住む奈良の近くに、今の住居地を見付けてきた。そこに住み始めると、妻の昔からの夢である、ビーグル犬がやってきた。それまで私は犬と接触する機会はなかったのではあるが、このワンちゃん“ゴン”との生活は、私にとっては、何時までも忘れられない人生のひとこまとなってしまった。あれから10年、今でも毎朝、裏山の隅に手を合わせている。
この住宅、雑木林のある辺鄙なところであったので、結局、私も自動車免許を取りに行くことになった。自動車学校に行かずして、免許を取得する方法を提案したのは妻である。お陰様でといおうか、母とワンちゃんを後ろの座席に積んで、共に行けた家族の自動車旅行は、心に残る想い出である。人生の終盤に京都の大学で教鞭を執らせて貰ったときにも、この車が役に立った。今も、遠い南紀白浜の方面で、多少のアルバイトができるのは、私が自動車で走れるからである。
さて植物の観賞のことであるが、私には中学時代の苦い想い出がある。夏休みの宿題に、10か20種の植物を採取、標本提出があった。他の宿題は、夏休みの終了間際に何とかなったが、植物採取をせず、標本を放置しておいたことは取り返しが付かなかった。採っても名前が解らない、調べようもないのが理由であったが、植物の奥深さが解らず、何の興味も持てなかったことが一番の原因である。夏休み空けに学校に向かう。先生に咎められるかも知れない。自分の怠惰に後悔の混ざる苦々しい気持ちを、今も忘れられずにいる。
それなのに、書くエッセイの題材に苦労しているとはいえ、この私が今、身辺の植物のことを書いている。どう見ても、妻の影響である。見合い結婚以来、結婚とはこんなものかと納得したり、ふと、別の形もあったかなと思ったり、それで50年近くをやってきた。思っている内に、そのまま点鬼簿に入る。あれも人生、これも人生、島倉千代子の歌ではないが、人生色々である。
(2020.10)
| 
