|
東日本大震災は、2011年3月11日に起こった。その日、私は午後のひと時をただ何となくテレビの画面を見つめていた。まもなく石原東京都知事が3選に向けての出馬表明があるとのことだった。
地震は14時46分に起こった。白昼だったので、テレビは被害の様子を分かるように伝えていたと思う。街の被害は阪神・淡路大震災に較べると、ビルの倒壊など、さほど大きくはなかったのではないか。突然画面が切り替わった、漁港の水面が写った。津波警報が出たと言うことだった。水面が少しあがったということだったが、やがて画面に信じられないほどの、水の逆流する光景が映し出された。停車していた自動車が浮き上がり、数台が互いに頭を突き合わせそのままの形でどんどん山側に向けて流されていく。
未曾有の大惨事のその2日後ぐらいから、さらに世間を不安に陥れるニュースが流れた。福島にある原発の原子炉で事故があり、核爆発が起こるかも知れないという。チェルノブイリの原発事故と同じで、住民は全員遠くに逃げなければならない。日本の原発は何があっても安全だとの神話が崩壊したのである。
近畿にいてテレビニュースだけに頼っている私たちも不安でいっぱいだった。事故があった東京電力福島第一原子力発電所へは時の総理大臣、菅さんも乗り込んだのだったが、私が日本沈没とまでは考えなかったのは、現場作業員が逃げず、原発の爆発を防ぐために放水を続けていてくれたからである。一般国民にも節電要請があった。原発抜きの日本のエネルギー事情はどの様になるのだろうか。不安は不安を煽った。
ここに震災の年の1年前、2010年の電源構成を表すものがある(表.1)。なんと、必要電力10,000(億kWh)の原発に依存する割合は既に、凡そ30%にもなっていたのである。その時、関西電力では51%にも達していた。街では原発は怖いなどと、こそこそ言っていたのに、原子力発電が水力発電量を凌駕して既に日本の電力の主要な軸に躍り出ていたのであった。
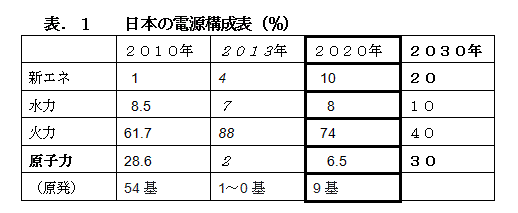
それから凡そ10年後の2020年では、震災を教訓に多くの原発は休止、廃炉に追い込まれた。ほぼ同じ量の必要電力に対して、その割合は6.5%になった。その分を火力と、10年前には姿を現してばかりの再生エネルギー(新エネルギー)が補ったことになる。震災当時、日本にあった、再生エネルギーもしくは新エネ(太陽光、風力、バイオマス)といわれるものは1%であったから、10年間程度でよくも10%にまで伸びたものである。
さて、地球環境温暖化が叫ばれなければ、現在の日本、この電力構成でさしたる問題もないのであるが、今や、地球規模で人類の営みを考え直さねばならない事態に突入し、エネルギー源として最たる電力は、CO2削減に率先して舵を切らねばならないのである。
2030年に向けた温室効果ガスの削減目標について、菅総理大臣は、政府の地球温暖化対策推進本部の会合(今年4月22日)で、2013年度に比べて46%削減することを目指すと表明した。さらに、50%削減の高みに向けて挑戦を続けていくとも強調したのである。(何故基準が2013年度か、何故数字だけで積み上げの削減細目を口にしないのか、読者には、以下の文章を読みながらご推察いただきたい)
それでは、今から10年後、2030年の電源構成はどうあるべきなのか。水力発電は一番確かな再生エネルギーであって、CO2を出さない。しかしながら10%程度に留まっている。画期的なアイデアが出ない限り、この10%が限度なのであろうか。今後CO2の発生を今の1/2に抑えるとすれば、火力発電の75%は40%以下に削減されるべきであろう。果たして、その35%の削減量を新エネで賄えるのか。
10年前、家庭の屋根に付ける太陽電池システムの売電価格は48円/Kwhであった。売電に10年間も使用すれば、導入した太陽電池システム装置代金がチャラになる。取り付けた太陽電池システムがそのまま、あと10年持てば、そこで稼ぐ屋上発電料金(売電価格としては24円/Kwhw)が、持ち主に利益還元されるとのことであって、その還元額は大略100万円かそこらか。
あれから10年、家庭の屋根に付ける太陽電池システムの売電価格はなんと1/4の12円/Kwhであるという。この売電価格、私たちが普段買っている電力使用料金25円/Kwhより低い。ということは、屋根の上の太陽電池は、売電という小銭稼ぎから離れて、例えば200万円程度のシステムを自ら買って、自分が使う電力は自分で発電させて造るといった、エコに目覚めた篤志家が取り付けるぐらいのことになるので、その結果、家庭の屋根の太陽電池システムが電源構成表に現れるぐらいの桁数を稼ぐのはむつかしくなる。
メガソーラー発電といって、工場跡地、休耕田などを使って、太陽電池パネルを一面に敷き詰めた光景を目にすることがある。これがサッカー場4,5面クラスの広さに森林を切り開き、あるいは、海洋に浮かぶ島一面に展開する。
しかし、これほどの巨大なものを見ると、私は太陽発電そのものに嫌悪感が走るのである。多分それは、いつも近くにある緑の木々から余りにも遠い人工的な工作物の匂いがするからである。サウジアラビアやゴビの砂漠の中に建造されるのならばともかく、日本のメガソーラー発電の場は本来、穀物、緑の木々が生い茂るところに忽然とできるのである。この土地では、当然のことながら、木々や雑草が温暖化ガスの炭酸ガスCO2を吸収し、酸素を吐き出すと同時に、昆虫、小動物の住みか、大木となる過程でどんどん炭素Cを木材として数100年に亘り固定していってくれている場所なのである。
この日本人の、生物的に肌に合わないことが原因かどうか、発電総量でいうと、その割合は家庭用太陽光発電総量の4〜5倍程度であるが、これも一定程度の増加に留まっているという。すると、再生エネルギーとしては2010年からの10年間で10%に到達したときと同じ伸びであり、今後10年で10%伸びるとしても、精々、20%程度にしか到達できないのではないか。
再生エネルギーとしての積み増しは、火山大国の特性を利用した、地熱発電が頭角を現せば一番良いのだが、この10年間、革新的な技術が生まれなかつたところを見ると、今のところ、地熱発電には将来的にも多くは望めない。
従って、火力の代替分の残る25%の枠は、結局のところ、CO2の輩出のない原子力発電に頼るしか方法がないのではないか。ということは、原子力発電が大震災前の30%枠に戻るということになる。
原理は原子爆弾と同じだが、核反応を制御すれば有効なエネルギーが得られる。日本には多くの石炭はなく、石油に至ってはその埋蔵量は殆ど無い。資源のない日本でも利用できる格好のエネルギー資源が原子力発電であるとして、最初の発電は東海村に建設された動力試験炉で行われた。1963年(昭和38年)のことである。
ただ、日本には最初の核被爆国として、核反応に依存する原子力発電に反対する空気も強く、その声を怖れて、政府も業界も原発には万に一つの危険性もないと謳ってきたのである。が、その副産物の例が、関電の原子炉がある福井県高浜町で起こったことは耳新しい。「関電の幹部20人が原発立地町の元助役から計3億2000万円分の金品をもらっていた」というのであるが、関電会長ほどの人物でも、受領を拒否できないほどに、「穏便、穏便に」と、その地元の権力者に気を遣わないといけなかったのである。
だが、安全神話は吹っ飛んだ。原発にも、「予想もされない事故は起こり得る」という観点で向き合わねばならないのである。事故が起こった場合には、その地域住民全員を収容できる、住民が安心し定住したいと思える代替地を予め用意しておく。平時の場合は、貸別荘のような感じで地域全体は観光地として利用されていても良い。市民生活が営まれているのもよい。ことあれば避難代替地として使う。福島の浪江、双葉町などで起こったような、原発プラント近隣住民の悲劇を最小限にとどめる、そのための約束、場所空間の準備は絶対にしておかなければならない。
東日本大震災以来、その安全性を問われて、現在、多くの原発が停止している。ところで、原発の安全神話を崩した、そもそもの原因は何だったのか。
「地震から約1時間後に遡上高14 - 15mの津波に襲われた東京電力福島第一原子力発電所は、1 - 5号機で全交流電源を喪失した」。ために、原子炉の制御、炉心の冷却機能が働かなくなり、炉心溶融が起こった。水素が原子炉格納容器内に溜まり、容器内の圧力を下げるためのベント(原子炉圧力容器内の圧力が急上昇した際に、内部蒸気を放出することで、圧力を降下させる安全装置)の不慣れな操作のうちに、(設計ミスがあって、最初からベントへ繋がる配管がなかったという記事もある)溜まった水素が爆発し、建屋から放射能物質が飛散した。と、大まかにはこういう説明がされている。
とすれば、電源さえ確保できていれば、損傷から廃炉になることはあっても、原発事故という大問題には到らなかったわけであり、原発の基本技術そのものは既に半世紀以上の操業を経て確立していると捉えて良かろうと、私は思うのである。
原発の一番の問題は、核廃棄物の廃棄場所が見付からないことである。世界で唯一決まった核廃棄場はフィンランドにある。バルト海に浮かぶオルキルオト島にできた核のごみ捨て場は、地下400メートルに廃棄物を埋設し、10万年にわたって保管する試みだ。
火山と地震大国の自国では無理とあらば、ブラックホールに廃棄するというような夢話ではなく、開発費を掛けると同時に多額の埋め立て場所代を払って、海外に埋設地を求めるのはどうか。これはダラダラと引き伸ばすのではなく、2030年に向けた目標の一丁目1番地で取り組んでいただきたい。
世界の覇権は核兵器が担っている。東芝社は世界最大の原子力発電機器メーカーを夢見て、米国ウェスチングハウス(WEC)を買収したが、原発事業に世界的な逆風があって、その投資に失敗、会社としての存続が危惧されるほどの大打撃を被った。
核兵器に近い技術は何か。原子炉である。私は、東芝社は、日本の安全保障を念頭に賭に出たと思う。同じ理由で、日本が列強に埋没しないためには、日本が原子炉を巧く操る技術を世界に誇示しておくことである。自国の安全保障に繋がる。そのためにも原発は日本には必要と私は信じるのだが、諸兄姉はどの様に考えられるのであろうか。
(2021.05)
あとがき
本稿は、日本技術士会近畿本部の機関誌‘きんき’ 180号別冊(2021.7月1日発行) 特集「日本のエネルギー問題を考える」に寄稿したものである。同特集の発刊を確認した上で、本稿を、この「ゴンちゃん倶楽部」に転載した形を取っている。
しかし、‘きんき’掲載のものは、機関誌編集室との話し合いの中で若干表現に手を加えた部分もあるので、ほぼ同じものであるが、実は、「ゴンちゃん倶楽部」に出したこの稿が、オリジナルと言えばオリジナルなのである。
寄稿文は5月13日に届けたが、偶然と言おうか、翌、5月14日付けの朝日朝刊紙に経済産業省の2030年度の電源構成計画が出た。再生エネルギー比率を倍増、原発を20%強に維持したい考えを打ち出したものである。
私のような全くの素人の推論も、経済産業省の役所の細かい積み上げも、行き着くところは同じかと、ちょっと不思議な気がしたが、‘きんき’機関誌編集室でも、私のオリジナリティーを強調するために、この一日の差を、次のような表示にして、経産省の値を赤字で併記してくれている。

私は、「ゴンちゃん倶楽部」に臆面もなく専門外の事柄を、エッセイネタとして掲げている。株券一つ買ったことのない経済音痴が、只ただ義憤に駆られて、「私の経済論」(エッセイ181、エッセイ138)と称して上げてみれば、その分野のエッセイ検索では、上位をキープしている。多分、その筋の方々の明察なる理論よりも、ただ読みやすいせいではないかと思っている。日頃、エッセイにならぬエッセイでも、書き続けておれば、時々変な御利益は出てくるものではあるらしい。
今回の‘きんき’「日本のエネルギー問題を考える」の課題の下でも、本稿は、内容はともかく、専門家の誰よりも読みやすいものとなっているだろうことには、私に、変な自信がある。
|

