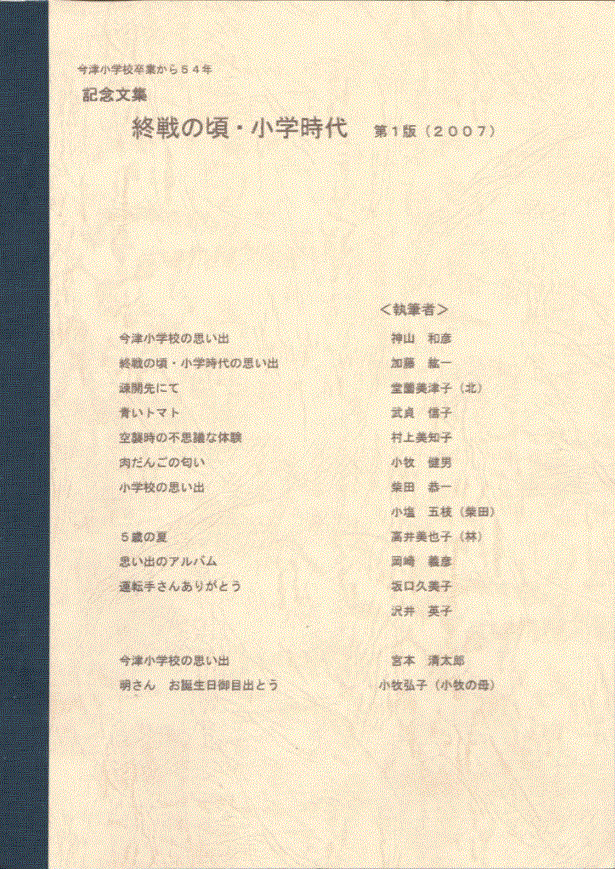|
私は、終戦から数年も経たない頃の情景が記録された、この記念文集を、なんらかの形で世に残せないかと考えていた。西宮の図書館はどうかと尋ねたこともあるし、朝日新聞にも送ったことがあるが、まだ目的は果たせていない。
今般、ひょんなことから、ホームペイジに掲載することで、その目的に近い形で、世に公開することになったが、ホームペイジ掲載については、この記念文集の執筆者全員の同意を得ているわけではない。
従って、同意手続きを取るまで、私と、私の母以外の執筆者の名前は、暫くは念のため、黒塗りとすることで、ご容赦願いたいと思っている。
<< と、同時に、同じ時代を過ごした、私の同期生に呼び掛けたい。諸兄姉の記憶にある終戦の頃の姿を、なんらかの形で後世に残すべきだとお考えであれば、このホームペイジの枠を使って、一緒に記録させていただけないだろうか。賛同いただける方は、是非、私、小牧健男まで、直接ご連絡をお願いします。>>
(2014(平成26年).7月 記)
記念文集(西宮市立 今津小学校 昭和22年入学)より抜粋
◇小牧 健男 宮崎学級
肉だんごの匂い
夜になると決まって、敵機襲来を告げるサイレンが近所に鳴り響き、私は母に眠い体を揺り動かされ、頭巾を頭に着けさされる。そして、私達の家族は防空壕の中に入る。防空壕は、家の側を通る道路の脇に父が掘ったもので、地面の上に大人一人分程の土が盛り上がっていた。父母、祖母と私と弟の家族が身をくっつけてやっと入れる程の大きさの穴があって、その穴の土の崩れを防ぐために内部に板を張っただけのものであった。
その穴の中で潜んでいると、やがて空襲警報が解除されたとの合図がある。家族と共に防空壕の外に出て、夜空を見上げていると、サーチライトの中を敵機が悠然と北へ飛んで行くのが見える。サーチライトの幾条かの光がその機影を捕えて離さないのだが、それを迎撃するはずの友軍機はいっこうに現れないのだ。あの敵機はBー29だと教えられたが、爆撃機は成層圏を飛んでおり、日本機にはその高度を飛ぶ能力はなかった、と後日知った。
西宮大空襲の夜の事は覚えている。私の家の前には阪神電車が走っていて、近くには今津駅と鉄道の枕木の置場があった。その枕木の山が焼夷弾で焼かれて煤を出しながら夜の闇に赤々と燃えた。つい50メートル先の戦火を私は防空壕からじっと見ていた。投下された焼夷弾の数は大量だったが、その落ちる音は雨の降る音に似ていた。そして、其のあとには何時も黒い雨が降った。この時も何時もと同じで、強く雨が降った。
終戦後も焼夷弾の殻は其の辺りの道端に転がっていた。近所に住む青年団の茂さん達は、不発だった焼夷弾から褐色の液体燃料を取り出して、それを炊事の燃料に使っていた。茂さん達は外の筒を叩いて二重構造になった中筒を取り出す。其の中に褐色のねばねばした油脂と揮発性の液体がある。
当時6才だった私は、自分も燃料を取ってやろうと考えた。私は弟達が見守る中、金槌で焼夷弾の筒を叩き始めた。筒の底部にあった小さな突起が出た部分で、多分信管に相当する箇所でなかったかと思う。私の家の庭に、血相を変えた茂さんが飛び込んできた。「何するんや、爆発して死んでしまうで。」
当時、私の家族は七輪の様なものに木ぎれを入れて炊事をしていた。燃料は貴重だった。私は、家の助けになればと思ったのだが、もし、焼夷弾がはじけ、燃えた燃料が飛んでいたら、すんでのところで、自分や弟達に火傷を負わせるところだった。
小学校一年生の担任の松田先生は、何時も軍服を着ていた。多分それ以外には着る物がなかったのである。その先生が、箸で丸い褐色の『肉だんご』を摘んで、先ず一つずつ、私達の銘々の食器に丁寧に入れていった。それから、バケツに入った『菜っ葉汁』を柄杓ですくって肉だんごの上から掛けていった。給食の肉だんごの匂いが快く鼻をくすぐった。口に入れた私は、世の中にこんな美味しいものがあったのかと思った。実際、私はその『肉だんご』の味を、匂いを、未だに覚えているのである。今の時代になっても、スーパーで肉だんごの試食をやっていると、私は摘んで、あのときの味と匂いを確かめるのである。
肉だんごはアメリカからの援助物資だ、ということだった。その後、口にした脱脂粉乳、これはそれ程感激する味ではなかったけれど、それから、卵黄を乾燥させた粉、小麦粉など、アメリカの余剰農産物が日本に届いていた。たとえ、本国では焼き捨てる穀物とはいえ、敵国に援助する豊かな国の寛大さは、子供心にも感謝の念を持たせた。
それから二十年位経って、日本の経済成長がめざましくなり始めた頃、アメリカから、「あれは無償援助ではなく、その代金を請求したい」、という話があって、日本中で物議を醸し出したことがあったが、「あの食料によって私達の窮状が救われたのだ」と言う、アメリカの善意に感謝する私の気持ちには、その後も、些かの揺らぎもない。
<<以下 (エッセイ 46〜47)に続く>>
|