|
5月20日(2014)の朝日新聞に驚いた。福島原子力第一発電所の故吉田所長が述べたとされているのだが、津波で原発が停止し、水素爆発があった日、大多数の発電所従業員が彼の命令を聞かず、遠くへ避難したという。
これはどうしたことか、確か、大変な混乱にあったとしても、従業員は吉田所長の号令の下、それぞれの任務を果たしていたのではなかったのか。
そこに官邸サイドから「撤退はならん」と菅首相が東京電力の本社に乗り込み、また、原子力安全委員会委員長 班目(まだらめ)春樹と共に福島原子力発電所にまで飛んで来た、しかしその行為は、現場を混乱させただけの愚行だったというのが、大方の見解だったのではなかったのか。
ところが、この朝日新聞の報道が正しいとすれば、真相は、菅首相が逃げる東電を身を挺して阻止したことになる。
それから3ヶ月後の今になって、当時の野党であつた現自民党政権が、朝日新聞の誤報を立証するために、吉田所長からの聞き取りの内容を公表するという。
発電所従業員の逃避はなかったというのである。
「発電所従業員の逃避があった」とすることは大変なことなのである。津波が襲った時、私達は、福島原子力発電所は完全に停止し、再び臨界爆発に達することはないと、当初は理解していた。
そこに、米国本国から在留米人に対する80Km以遠への退避勧告である。管理する日本人が必死に沈静化に努めているのに、アメリカと雖も、ことさら事故災害を誇張する態度は許せないではないか。
しかし、原子炉はいったん停止したとしても、核燃料棒を浸漬させた圧力容器の水が涸れると、核燃料棒の反応熱で原子炉圧力容器を融かし、水素爆発を起こすというのである。そして現に水素爆発を起こし、炉格納容器からもれ出た核物質が飛散したというのである。
以降、吉田所長の要請で、ヘリコプターから、また、高圧ポンプのある消防自動車から、原子炉容器に水を溜めようとして、上から水を散水し続ける懸命な作業が、仮設ポンプ装置が働くまで続いたことは、未だ記憶に新しいところである。
その間、東京ほどには福島に近くない大阪に住んでいても、原子炉が暴走して、日本国がチェルノブイリやスリーマイルになるかもしれないという不安は常にあり、私の気分は、実に落ち着かなかった。
それでも私達が安閑としておれたのは、少なくとも現場は組織だって動いており、沈静化に向けて懸命に努力を続けている、たとえ事態は大変な状況にあるとしても、原子炉は暴走のない管理下にある、と信じようとしていたからである。
現場の作業従事者に死傷者がなかった。所長や従業員が、近隣住民が、先を争って逃げなかったことが、日本国内に住む我々の動揺を鎮め、ひょっとして公海に汚染水が漏洩し続けているとしても、安倍首相がオリンピック誘致の席上で、「事故の起きた原子力発電所は沈静化に向けた処置ができています(under control)、安心してください。」と公言できた由縁である。住民の避難はあっても、ことが混乱なく処理し続けられているということは大切なことで、日本の精神、技術力に関わる。と、私は思っていた。
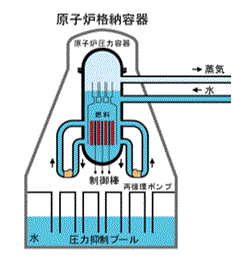 図.電事連 沸騰水型炉のしくみ より 図.電事連 沸騰水型炉のしくみ より
朝日新聞が、事故初期には、東京電力の本店で作業者の撤退が検討され、現場の従業員が所長命令を無視した逃避行動をしたというなら、もしそれが他の新聞社が言うような捏造記事なら、その記事内容の軽薄さは責められて余りあると考える。しかし、事の真相は、朝日新聞が書いたような混乱の一面もあったのではないか、と考えるのが大人の常識というものであろう。
ただ、朝日新聞に、咎められるべき見識の欠如が有るとすれば、福島第一原発の命令系統が混乱の最中にあったとしても、少なくとも、パニック行動に繋がる記事構成にしない配慮が必要だったのではないか。
過去の原子力発電所事故については、インターネットで調べてみた。旧ソビエット連邦のチェルノブイリ原子炉はウクライナにあり1986年、爆発事故により30km半径の周辺は無人地帯となり、現在でも、原発プラントはコンクリートで覆われた石棺になっている。
河の中州にあるスリーマイル島の原子力発電所は、ニューヨークからは300Km離れたところにある。1979年、福島原発と同じ炉心溶融事故。核爆発はなかった。10Km圏内の住民の避難はあったが、事故のレベルは福島より低いとされている。同地の他の原発は今も稼働している。
私はこれまで、映画やテレビの画面で、両原子力発電所共、パニック状態に陥った原発作業者や周辺住民が、先を争って逃避したものと思っていた。だが、スリーマイル島の原子力発電所では職員は逃げては居ない。それどころか、国民が不安に陥らないように、事故の原子力発電所の近くで、爆発事故にはならないことの説明に努めている。
チェルノブイリでも作業員などは最後まで、原子炉が暴走するのを食い止めようと努力し、その結果、1万人以上の犠牲者を生んだともいわれている。住民、約16万人が移住を余儀なくされたとある。
この原子力発電所事故は、いずれも、平常運転中に起こっている。運転者の誤操作から起こったものであり、地震、津波が押し寄せ、その影響で電源喪失といった想像を絶する混乱状況にあった福島原発とは、初期状態の過酷さがまったく異なっている。にもかかわらず、福島原発では、ことが混乱なく処理し続けられていたのである。
テーマは吉田所長の調書から離れて、「我が国が原子力発電所を保有すべきかどうか」に関する議論に移る。
大体、日本の原子力発電所にあっては、事故が起こるはずがないように管理されており、よし事故が起こったとしても、格納容器は絶対に核物質を外に拡散させない二重三重の対策がなされているのではなかったか。今回の事故では核爆発までにはいたらなかったが、まず、その安全神話が崩壊した。
また、使用済みの核燃料棒が、福島原子力第一発電所には多数貯蔵されており、これらの保管を誤やまると、被爆に繋がるという問題が出てきて、使用済み核燃料の最終処分法が、実は世界的にも未だ解決されていないのだという基本問題までが浮き彫りになってきた。
青森県にある六ヶ所村で処理することで、この件は既に解決済みではなかったのか。いや、あれは一時貯蔵庫に過ぎなく、本物の処理技術が確立するまでの時間稼ぎであったのだ。その間にも、核燃料サイクルの根幹が未解決のまま、関西では40%の電力が既に原子力で賄われていたのである。因みに水力発電は10%である。
今、上記二つの理由で原子力発電を全部止めようという動きがある。神話は崩れ、少量とはいえ被爆はありうるとすると、子供の将来のDNAに不安を残す。だから、原子力発電に立脚する国造りには絶対反対だとする一派がある。それで経済が破綻するとあれば、昭和初期の生活に逆戻りをも肯定する一派である。これはこれで絶対に正しい。
が、昭和初期の生活とは、具体的には、便所は水洗でなくてもよい。野菜や魚の購入では、ポリ袋に入れるのではなく、古新聞の包装となる。華やかなショッピングエリァも大型スーパーもない。もちろんマイカーなど一台もない。スマホも携帯もない。が、田んぼには蛍が飛び、めだかが小さな水溜りにも泳いでいる。クーラーはなく、蚊帳をつっての生活となる。
問題は食事であろう。今の一日の普通の食事の量と内容は、昔の盆と正月の贅沢である。貿易収支の赤字からみて、海外からの輸入に頼るわけには行かない。一週間分に引き伸ばして食べて十分と考えられる。これで、糖尿病の心配などしなくていいのであるが、果たしてこれで不満が蓄積しないか。大丈夫か。
現在の日本の生活水準を、日常生活の必須の要件とすれば、原燃料の購入で貿易収支が赤字化した国家経済は債務超過の国へと転落していくことになるだろう。また、地球温暖化、異常気象防止の切り札は原子力発電であったが、石炭、石油に頼る限り、地球環境悪化の歯止めはなくなる。
そのための、再生化エネルギー計画(太陽発電、風力発電)であるが、日本では全電力量のやっと2%達成で、10%の達成は難しいと見られている。従って、世界に伍した生産活動をするためには原子力発電が必要だとの、現状の生活水準を肯定する派がある。
原子炉の安全面は更には発展させていけるとして、核廃棄物が物理的或いは化学的に処理するのが困難で、地下の底深く埋設しておくしか方策がないとすれば、地球上の1/10の地震が起きている日本国土にではなく、地殻変動がない僻地にその場所を求め、世界的規模でその地域の開発が必要となる。その地の危険の代償に、技術、資金の面で日本は開発のイニシャチブを執らないといけない。
さて、起きてしまった福島原子力発電所の事故であるが、発電所(国)側と、地元住民側との対話という点では改善が見られると思う。とにかく、原発安全に関する知識が解説されて、義務教育のレベルは上がってきた。核燃料から生成した放射元素のうち、なぜ、セシュウム137とヨウ素131が放射線汚染物質として問題になるかを、半減期という観点から理解する程度の知識は常識である。
これまで発電所側は、安全神話を纏い、反対側の懸念を一蹴してきた。もし改善の検討を見せれば、絶対安全ではなかったのかと、反対側に付け込む隙を与える懸念が有ったからである。だがその安全神話が崩れたのである。
絶対反対側もある程度の専門的知識で議論することが要求されることになった。有る程度のレベルの原子力知識が常識になってきたからである。
不幸にして、対話の土俵への素地はできたのであるが、両派の話し合いの結果、ゼロ原発を謳う一派は、例えば、子孫のために原発なしと規定した、北海道、或いは九州で昭和初期に戻った生活を始めるかもしれない。現状の生活水準肯定派は、東京ドームが側である暮らしのように、原発プラントの横に住居を置き、安価な電力を得ることを至上とするかもしれない。事例を極端なものにしたが、それぞれがそれぞれの選択をすることで、それはそれで良いのではないか。
私は、日本が、核廃棄物処理を含めた原子力発電の維持管理技術を保有することが、世界の先進国として残る必須の用件ではないかと思う。国の憲法で戦車を持たないことを規定するなら、平和と見える原子力発電の技術で世界をリードし続け、その能力を盾としなければ、慎ましく、のどかに生きることを決めた、北海道が、九州が、アフガニスタンやイスラエルのガザ地区の様に、戦火にまみれ、流浪の民を輩出し続ける場になる、今の世界の情勢には、そんな危険性があると見るからである。
(2014.09)
| 
