|
人生には過去の何が生きるか分からない。私の場合は、大学で講義してみないかと言われたことは青天の霹靂であったが、その授業の課程で、キャッピングという技術が、実に心強い支えになってくれたことが、これまた、驚きであった。
キャップは帽子のことだから、キャッピングというのは帽子を被せるという意味であるが、何に被せるかというと、コンクリートの試験体の頂部にセメントペーストを塗って、その頂部を真っ直ぐ滑らかに仕上げることをいう。
練り上げたコンクリートの強さを見るためには、その同じコンクリートで10cm径の円筒試験体を造って置き、その試験体に破壊するまでの圧縮力をかけて、練り上げたコンクリートの強さを推定するのであるが、その時、試験体の頂部を、試験機の圧縮面に滑らかに接触させる為に、キャッピングを必要とするのである。
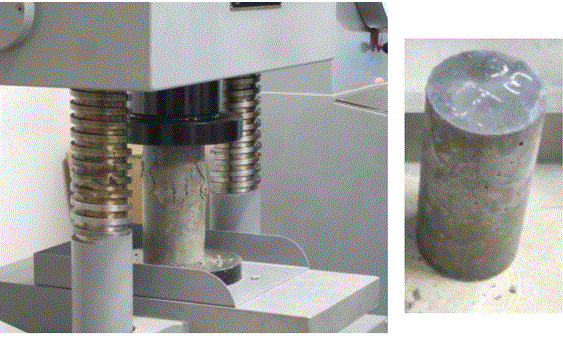
<図1. 圧縮試験とコンクリート・試験体>
さて、この試験体の造り方であるが、円筒形の金型に、練り上げて造ったコンクリートを入れるまではよしとして、さて問題は、できたコンクリート試験体の頂部を、セメントだけのペーストでキャッピングし、その頂部の平滑さを、ガラス板を置いて確実にするという過程がある。何時に、セメントペーストを塗るか?というキャッピング工程の微妙なタイミングは、多分、文章で読んだだけだと自信をもつて実施に移すことができない。本来は、現場コンクリートを扱う専門職の技なのである。
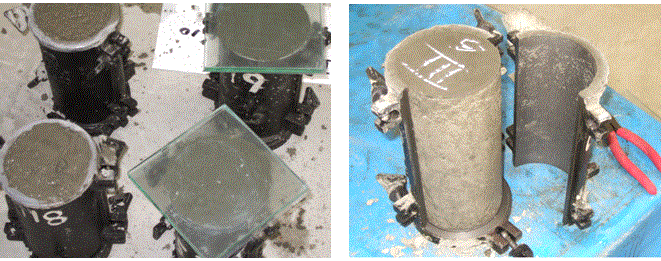
<図2.キャッピングと金型からの試験体の取り出し>
しかし、私はこのキャッピングを、自信を持って行うことができるのである。ひょっとして、この技術を習得しているために、私は、特にコンクリートの課程全般を、自信を持って教えることができるのではないかと思う程である。
今、私は建築材料を、色々な実験を通して教えている。材料は鋼材、板ガラス、タイル、石材、木材などに亘るが、時間を多く割いているのは、建築に使う材料の量から言っても、使用箇所から言いっても、もちろんコンクリートである。したがって、セメントの粉、砂、砂利を使って、学生たちはコンクリートを練り上げ、それを木製の型枠に流し込み、木製型枠の中に入れておいた鉄筋と一体とした鉄筋コンクリートを、実際に造ることになる。その時、同時に、上述の、コンクリート・試験体を採取し、私がキャッピングを受け持つことになるのである。
教官として、何故、私がキャッピングを得意としているのか。
私は55歳のとき、建材の開発職から、コンクリートのコンサルティング会社に転籍した。コンクリート管理の技術責任者ということにはなったが、実際の作業内容はよく分からなかったので、Mさんが、関係する会社に私の紹介を兼ねて、その作業内容を指導してくれることになった。
最初の見習い研修は、このキャッピングを施したコンクリート・試験体を金型からの取り出すことであった。業務見習いではこんなことまでやらされるのかと、不満顔で形ばかりの作業をこなしている私に、Mさんは、協力してくれた会社の足手纏いにならんようにと、たとえ見習いでも、やることは手早くやらんといけないでしょうと、手厳しい。
Mさんは、定年後、現場コンクリートでたたき上げた技術の指導員の資格でこの会社に残っているのである。それだけに、指導性は無論のこと、指導者としての人間性も評価された人物なのである。仕事にはうるさいが、穏やかな性格である。中村美津子ファンで新歌舞伎座には必ず見に行くという。日曜日には、2、30キロ離れた郊外から自転車で大阪の中心地にやってくるという。
こんなMさんに指導を受けて、私自身はあまり身の入らない、いわゆるコンクリート専門職が行う一通りの作業手順を習得するところとなったが、そして当たり前のことだが、特にこの技術が、その後の私の業務に役立つこともなかった。そして、私は定年で退職して、こんなコンクリート管理業務とは完全に手が切れたわけであったのだが・・・・・。
突然、芸術系の大学で、「建築材料」を教えないかと言う話が舞い込んだ。過去、私は、新しいガラス建材やタイル建材の開発にリーダーとして取り組んだが、その製品を市場に出すことはできなかった。現場コンクリートの管理と産業廃棄物の分析などに専門性を持つ程度の技術者として、なんとか息を継いでいたが、「建材を実際に取り扱った、その経験を生かし、解りやすい講義をして欲しい」と言うことであった。会社の経営にも、社会的にも貢献できなかった私の技術が、教育という別の形で生きるとは、なんとも有り難いことではないか。
ほとんど手探りの授業構成と成ったが、どうも私の手持ちの技術で、一番に役立ったのが、なんと、このキャッピングのノウハウだという訳だった。私は、キャッピングをしながら、何時も、「もっとしゃきしゃきしてせんと、いかんですよ」と注意してくれた、親切だったMさんのことを思い出すのだ。
人生、本当に、何が役に立つか分からないものである。
(2015.09)
| 
