|
◇石油資源(壮大な嘘)◇
凡そ50年前から石油の埋蔵量は30年間しか持たないと聞いていた。しかし今、50年経った今、原油の価格は5年前の価格の三分の一に下落している。高止まりしてきた原油の突然の下落には、確かにそれなりの理由はある。シェールオイルという石油が、石油の貯蔵層とは別の、正に岩石の頁岩から取られるようになり、今まで最大の石油輸入国のアメリカが、石油輸出国に転じたことが大きい。
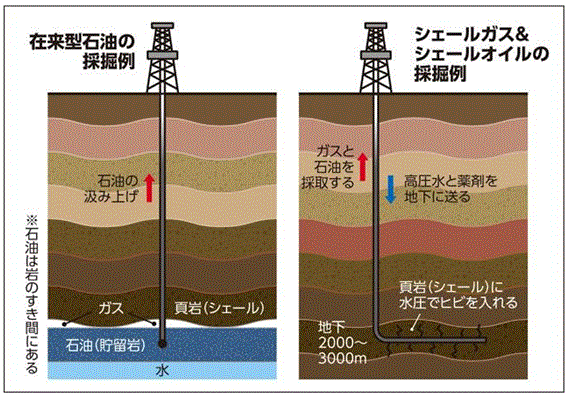
<図 2012/11/14 08:00 by Avanti Yasunori clicccar.comホ−ムページより引用>
あまり次々と埋蔵量が変わってくるので、石油は単なる、生物の死骸の変質といった化石燃料ではなく、そもそも地球ができてきた過程で、作り上げられた無機質とする説があるほどである。
50年前の、当時の石油の探索技術からすれば、海底深くある北海油田や、シェールオイルからの油は予想不可能としても、なくなる筈の化石燃料が過剰にあり続けるというのは、その時の埋蔵量の科学的評価が、そもそもおかしかったとの結論と成るが、科学か、権威とされてきた科学者が、壮大な嘘をついていた事になる。しかも、この嘘が世界の政情を不安定にして、紛争の種をまき散らかせていたということになる。
科学者の側から言わせれば、ものの推定には必ず付帯条件というものがあって、その時代の探査技術、経済情勢、関連化学技術が関係する、などとの弁解はあるかも知れないが、それを言えば切りがない。
人は何かというと、科学的根拠、客観的根拠などと言うが、そもそも、科学的、客観的と言っても、根拠の程度はこの壮大な石油の嘘が示すところである。
私達が心得るのは、地球規模の見通しには、地球温暖化現象にしても、世界経済の見通しにしても、人類の未来に関する見通しも、実は、確定的なことは何一つ無いということであろう。
(2016.02)
◇燃料電池◇
凡そ半世紀も昔のことだが、新設の岡山大学工学部の教室にはクーラーはなかった。夏の、京大の吉沢教授による「電気化学」の集中講義である。「燃料電池」の権威ということで、その話もあったが、肝心なところがよく分からなかった。
水に電気エネルギーを入れれば、即ち、電気分解をすれば、水素ガスと酸素ガスができる。分解してできた水素ガスと酸素ガスを混合して、点火してやれば、爆発的に燃焼して再び水に戻る。そこまではよく解るのである。しかし、できた水素ガスと酸素ガスから、今度は電気が取れる「燃料電池」とは、電気分解の逆反応であるといわれても、よく解からなかった。
逆反応と言うのなら、電気分解を終えた電線の電源端子に豆球をつけてやれば、できたての水素ガスが、ガスが滞留するマイナス電極だった電極に電子を与え、再び水に溶解してゆくというのなら解かるのだが、通常、そんな反応は起らない。
それから50年経った今、水素社会なる言葉ができた。水素を燃料として空気中の酸素と反応させ電気をつくる。電気を取った後、反応した水素と酸素は水に還る。燃焼に炭酸ガスを出さないから、地球温暖化に資する、などといっている。
ここに来て私にもやっと、燃料ガスから電気が取れる仕組みが解かってきた。実は、電解質膜というものの存在があったのだった。
水素ガスが接触する電解質膜には、フッ素系の高分子素材が使われ、水を含ませて使用されるが、水素ガスはプラスイオンとなり電子を放出してこの電解質膜を通過し、出たところで、マイナスイオンを帯電した空気中の酸素と結合して水となる。いわゆる燃焼ではないが、この循環過程で電気が作られるのだ。即ち、電解質膜に良質の材料ができてきたので、効率よく電気が作られるようになって、今、燃料電池が使える世の中になったのだった。(図の 燃料電池の仕組み参照 )
といっても、電解質膜を通過する水素ガスがイオンとなるメカニズムはやっぱり分からないままなのではあるが。
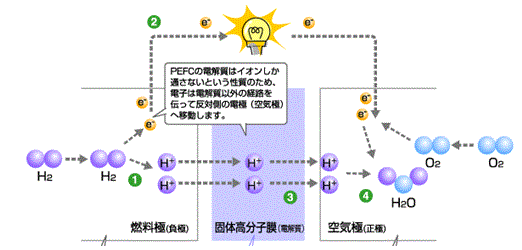
<図−燃料電池の電解質膜 大阪ガスのホームページより引用>
思いだすのは、同じ半世紀前の教科書だが、私達の研究部長が読書会と称して、我々に読ませていた本がある。吉田重知著「固体物性論概説」という本であつた。
半導体では、電子がエネルギー的に存在しない「禁制帯」があるとか。何のことだかさっぱり解らず、この分野には興味が湧かなかったが、思い返してみると、集積回路のマイコンなどという言葉も出始め、今で言う、コンピュータ記憶素子、太陽電池、LED照明のまさに揺籃期であった。
こんな理論を基にして、現在は、コンピュータが当たり前のように動き、照明も、フイラメントの白熱球(いわゆる電灯)は、LED(発光ダイオード)照明に取って代わられているのだが、研究部長は、50年先を見通して、私達に開発の切っ掛けを与えようとしていたのだった。とにかく、現代の華は、50年前にあったのだが、私は全く先が読めていなかっと、今、つくづくと感じるのである。
(2016.02)
◇昭和レトロ◇
今を去ること20年程昔のことになるか、ならないか。福井市にある博物館に行った。恐竜の展示で有名と聞いていたが、実は、恐竜の展示は、勝山市にある恐竜博物館の方に移ったばかりということであった。仕方がないので、ともかく、その抜け殻のような博物館を見学することにした。
展示場は、学校の教室を並べたような感じの処にあった。昭和の日常品の展示だという。昭和のものだから、正に自分が生きていた時代だから、奈良時代、江戸時代の生活資材とはおよそ違う、「何が面白いのかなぁ」と思ったのだが、何とも言えない、奇妙な気持ちを抱えて、展示場を出ることになった。
「ジョン」との名札が就いた木造の犬小屋がある。そういえば、犬は屋外で生きる生き物で、名前はジョンかエスであった。玄関前のその横には三輪乗用車、大村昆の広告で有名だった「ミゼット」が置いてある。森下仁丹の琺瑯製の看板である。昭和の家の中にあるのは、当時の雑誌、広告の類、ブリキのおもちゃである。
昭和30年代に、住宅公団で採用されたダイニングキッチンの一間がある。4人が座れる、今は小さい机と椅子である。電気冷蔵庫は未だ一般的ではなく、製氷を入れる木造りの冷蔵庫かも知れない。前には、ステンレスの流しがあって、煮炊きのガスレンジがある。当時憧れの、4畳半に込められた文化生活の粋である。壁は、木材のプリント合板で、部屋の仕切りは、不思議に珠簾が掛かっていた。
確かに、そんな光景はつい昨日まで身近にあったのである。だが敢えて見せられると、縄文式土器の展示ではないが、あまりに過去のものになってしまったことに驚いたのである。
やがて、洗濯機から始まる、電化製品が次から次に入ってくるのである。蛍光燈も過去のものとなり、今や照明はLEDである。パーソナルコンピュータの歴代の討ち死に姿は未だ各家庭の押入れに、累々と転がっているかもしれない。カラーテレビになったと思っていたら、箱型のテレビは何時か無くなり、薄型液晶の大型テレビである。
ブリキのおもちゃは、組み立てなおしては元に戻らず壊れていく。その虚しさは、バーチャルゲームのせかせかした画面で遊ぶ今の子供にはわかるまい。
時の移ろいの早さである。今や70歳代、80歳代の戦後を知る人には昭和レトロの中に、当時、アメリカ映画に見た文化製品に囲まれた憧れの生活への推移が、走馬灯のように見えるのであるが、それは、面白いとも、悲しいともいえるのだが、ものの溢れた現代生活を基盤に育った若者は、やがては私達のように、時代の哀れに佇むときが来るのであろうか。
(2016.02)
| 
