|
ISOというお札(ふだ)がある。水戸黄門が、「このご紋が見えないか」と、武士や民を前にして大見得を切るときに見せると、皆が頭を垂れる、あの万能手形である。だが、このお札の効用はあるかもしれないが、もらうと、所有税がかかり、錆びないようにと、人手を掛けて磨いておかなくてはならない。その維持管理にお金と人手がかかりすぎると、インターネットには、不満が渦を巻いている。
しかし、ISO9001、ISO14001、という規格を獲得したとの大々的な宣伝文句は、大きな工場の外壁にでも見るし、引越しのトラックの横腹にもついている。ISOとは、国際標準化機構( International Organization for Standardization)の略称であるが、それでは、何故にこれらの企業では、競ってこの資格取得を誇示しまくっているのであろうか。
世界に羽ばたく大企業は無論のこと、関連企業が先を競って、お札の効用に縋るブームが来ていると思っていたのだが、実は、あの世界のトヨタ自動車が、ISOを取得してないというのである。いや、このお札の取得は益なしとしているのである。親方が必要としないのであるから、親方日の丸とする子分も、その通行手形たる、お札は必要がないのである。何故か。
ここにISO9001を取得している10人程度の「ガラス加工工場(製作所)」がある。石英ガラスの塊を購入し、切削して部材をつくり、研磨して製品にしている。この製品は大手の光学機メーカーに納入され、光学器材に部品として組み込まれる。
製造現場で働くのは、4名。古手の職工長指導の許、3人の若手が作業に当たっている。売上高は凡そ1億円、建屋、機械などの固定費、石英ガラス・ブロック、研磨剤などの消耗費、変動費などを引き去ると、人件費他で残るのは5000万円余となり、10人の従業員の平均年収400万円である。
この会社がISO9001の認証を取ろうとすると、運用規定書を作り、ISO認定機関の審査を受けるわけである。100ページに亘る規定書(マニュアル)造りは従業員の手になるものではなく、この種のコンサルタントを専門とする会社に依頼される。作成費200万円である。ISO認定機関による認証審査費60万円、2年に一度更新審査に30万円、その間、規定書の書き換えなどの維持管理にコンサルタント社への支払い、毎年100万円が必要となる。概していえば、この会社は、ISO認証の看板を揚げるために毎年150万円の新たな出費を覚悟しなければならない。はたしてISOに、この程度の会社で、従業員一人分とまでは言わないが、それほどのお金をかける価値があるのか。
さて、その効用である。ISO9001の認定工場となったので、これで納入先の要請には応えることができた。あとは、国際的に見て、製品の品質管理、特にそのマネージメントに優れていることとなれば、毎年150万円の出費の価値はあったと、万歳、万歳である。ところが、現実は何も変わらない、元々からの品質管理体制の踏襲となるわけで、これまで職工長の経験に頼るわけである。新たに作られた自社のISO運用規定書をみることは無い。ISOの規定は、ガラスの研磨・研削作業には精通しないコンサルタントの机上の作だからである。加えて、日常、ISO運用規定書通りの、サービス的な作業、記録とその整合性を確かめる作業が発生するわけで、日常業務が煩雑になったことだけは確かである。
ここの会社の製品がJISの対象製品だったら、いや、そうでなかっても、すべての精力を傾注して、切削加工機でガラスを無駄なく切断すること、研磨機で研磨剤を使って研磨する、その研磨剤の種類と使用時間の関係性を求めるなど、一番肝心な、この製造工程をまずは安定させること。次いで、歩留まり向上である。しかし、ISO9001の規定書では、品質管理の一丁目一番地の、製造工程の品質管理は、全10章の内の1章、いや、その半分に過ぎない。品質管理の徹底した意識付けが必要だと言って他の章の儀式が多すぎるのである。
例えば、社長が社の方針を出し、その方針を品質管理の目標に落とし込んで行く。全社会議を開いて、紙に残すのである。そして社長方針、品質管理目標を冊子にして、従業員が胸ポケットに入れて持つのである。まるで、幼稚園生の胸のワッペンであるが、審査では、その形が評価されるからである。
P(計画)→D(実施)→C(評価)→A(改善)のサイクルを意識付けて、展開せよと、尤もらしく言う。こんなことは無意識にやっていることなのに、問題の処理に、このサイクルを回した証明をいちいち紙に書いて残すのである。いちいちの課程を紙に書いて残すので、記録のための形式と、紙がどんどんたまるのである。
審査当日は無論のこと、上から下まで揃っての会議の儀式が多すぎる。内部監査と称して、わざわざ模擬監査での役割を創り、芝居のような手順で、工場における製品の管理状態ではなく、会社として取り決めた項目の進行のチェックがある。その課程を全てPDCAのサイクルで考えるから、現状がどうあろうとも、少し高みに上がれば好いとの言い訳があるのであるが、この作業をレビューと称して大切にしすぎるのでとにかく無駄な会議が多くなる。この会社の程度であれば、3人の作業員が、適時話し合えばいいことなのである。
ISOの儀式の中に、顧客満足度の調査がある。顧客が満足していなければ商品は売れないので、顧客が満足する品質のものを編み出していくのがそもそもメーカーの企画であり、品質管理である。その調査と言って、顧客を煩わして記録を重ねる要求がこの運用規定にはあるが、こんな茶番をお偉い納入先に対して、現実にできるのか、自動車会社でもない、この程度のガラス部品納入の会社の分際で。
社内の資源管理ということで、生産機械の台帳作成、管理は無論のこと、人材教育の規定、スケジュールを綿密に記録せねばならないのである。生産機械の台帳などは、経理資料を引用すればいいのだが、技術にあっては社内昇段試験を設けて措かなくてはならない。機会を見て、研磨技術の講習会に参加させるということでは、いけないのである。
クレームの処理の規定は唯一、建設的なものである。クレーム物件が出たとき、逆を辿っていけば、直ちにその成因の製造条件に還るというものであるが、巨大な自動車工業ならばともかく、限定された10種類ほどの製品を作っている工場規模では、そのクレームの成因は直ちに判るので、そのために図面の管理、整理など、保管書類の発生こそが、作業を煩雑にする要因と成ってしまうのである。
かくして、実際の営業と工場作業従事者を合わせても4,5人であり、この人間が、ISO9001マネージメントシステムに書かれた、上記の作業工程をこなしながら、切削工程と研磨工程に重点を置いた品質管理に励むのだが、本来業務以外の作業が多すぎないか。
大手機械や家電メーカーは、輸出入で国際取引がある。海外の取引相手先がISO9001の品質管理規格を取得していると、まず製品の品質管理ができていると確認できて安心である。従って当然、ISO9001の品質管理規格認定会社としての認証、資格を自社も取って措こうとする。と、その方針に従い、日本の家電メーカーは自社だけでなく、協力会社である国内の、小さい部品メーカーに、ISO14000の品質管理規格を取得していることを要請する。何故か。
大手家電会社が、ISOの方針どおり、品質管理の全社的マネージメントを円滑にしょうとすると、自社の購買規定に、ISO90001を取得している関係会社を取引先に指定しておけば、なんとなく、間違いがない。いや、取引先をISO90001を取得していない部品メーカーにしていると、購買担当者は、取引先の小さい部品メーカーが、受け入れ試験で購入できる品質にあることを調査し確認して、その根拠を文書で残しておかなくてはならないのである。だから、一手間も二手間もかかる。そのために、小規模の協力会社までが、ISO9001の品質管理規格認定会社としての認証を取得して措く必要がでてきたのである。単に取引条件のインターフェースとしての必要性である。
傍目には、このガラス加工会社に本当に必要なものは、職工長の暗黙知の記録を整理し、体系づけておくことである。品質管理に係わる作業標準化など、まだ、遥か先のことである。
半世紀は遡ることになるが、日本を工業立国として確固たる地位に押し上げたものにデミング賞があった。製品の品質を保証するためにQC(Quality Control:品質管理)手法を駆使する。その製品の品質管理に優れた会社、工場にデミング賞が送られた。この賞の獲得と会社の業績向上は相関関係にあったらしい。デミング賞として授与されるデミング博士の横顔のあるメダルの銀色の輝きは、技術者には尊く、眩しいものに見えるだけの本物の値打ちがあった。
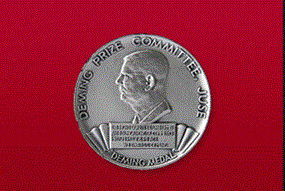 < 写真 デミング賞のメダル>
< 写真 デミング賞のメダル>
QC手法はよくできた工場の管理手段であった。例えば、私の勤めていたびんガラス会社であるが、製造中のガラスびんの内容量を水で測って、工程でへたり(軟化)が出ていないかどうかを調べるのだが、定期的にサンプルびんを5本取りその容量を水で測って、単なる5本の集計から、その数値のばらつきσ(シグマ;標準偏差)を計算すれば、びんのでき方が正常な製造状態ならば、その殆どは2σ内に含まれる、といった管理範囲があって、数値を管理することで製造工程の正常性を把握できた。
日本の工場にあって、実際に品質管理を行う取り組みとして有効とされるものに、品質管理のための小集団活動がある。製造現場で、職場、職種でグループ分けされ生産性を向上させるために討議しあって、職場ごとにグループを組み、日常活動の中から、品質管理、職場環境、特に安全管理などを謳うけれども、実際は生産歩留まり向上に就いて意見を出し合う。そこで用いられる手法が、「品質管理7つ道具」である。例えば、欠点別に統計したパレード曲線と呼ばれるようなものであるが、品質管理を行う上での共通語として、現場にはしっかりと浸透している。
この小集団活動を、上手く運営できているか否かは、JISではあまり重視されないが、QC全社取り組みの一環として最も稔りの多い活動であることは広く認知されている。とにかく品質管理を徹底しょうとすれば、この使用集団活動、本来の統計的手法を徹底すればいいのであるが、ISO90001のマネージメントシステムがこれを推奨しているわけではない。
QC(Quality Control)方法を駆使して、通産省の決めた品質基準をクリヤーして製品にJIS(Japanese Industrial Standards)マークを打てば、使用者が安心できる一定の品質を保証できていたのである。例えば、ネジである。ねじの寸法、山のピッチ、使った鋼材の強度も規格どおりのものが得られる。これで、国内では互換性、品質に何の心配もなく使用できるのである。それでよかったのではある。ある意味では、JIS規定の運用は、ISOよりずっと単純、明快である。
ところで規格の国際化である。ネジ、ボルト、ナットはJIS規格のものが国際規格と同じであるから、特段、国際規格は必要ないのであるが、大手メーカーは国際品質規格ISO9001を取得するから、事情がやや複雑にはなってきた。
JISの品質が維持されているかどうか知るために、立ち入り検査が、昔は通産省、今の経済産業省の役人の手で行われる。その代替を委託された公示検査員として、私はガラス関係の工場の検査に入ったことがある。
工場のJIS製品の管理が、提出書面どおりに実施されているかどうかの検証である。サンプルが抜き取り数どおりに抜き取られているのか、検査器を使っているなら、その校正は?どんな基準器で、その校正の頻度は?その基準器の管理は?外部委託しているのなら、その検査結果のファイルは?となる訳である。
その結果が、記録として書面にきっちりと、残っているかであって、書面には記録されてはいるが、果たして、現在の製品品質そのものが、実際JISに謳われている品質であるのかどうかは、検討しないのである。しかも、不適切箇所が発見されると、その是正項目に就いては、「こうすべきです」というようなことは一切言わないで、是正すべき内容に就いて、「その是正処置方法を書面で何時々々までに役所に提出願いたい」となる訳で、無論、JISマークの返上を恐れる企業からの反論の余地などあるはずがない。お役所仕事にはお役所仕事の欠陥もあったのだが。
ISOの審査は民間の機関である。もし、認証を取り消すとなると、その会社からは審査機関にお金が入らない、という制度の矛盾も抱えており、実は、お役所仕事のようには冷静、厳正沈着には認証定取り消しなどを執行できない。企業もそこは心得ているのである。改善のスパイラルをつなげてゆけばいいとは文言は綺麗が、実質的な品質改善は何も起らないのが現実という、新たな問題も生じる訳なのだが、問題は、ISOの審査官が、運用規定での是正箇所を指摘しながら、品質管理上の的確な技術的アドバイスを、「することは禁じられている」と、しないことである。技術がないのか、結局は、お役所仕事と同じことをやってしまっているのである。
大抵の人達が挙って、ISO90001は特に中小企業には百害あって一利無しという。裸の王様の話があったが、皆分かっても誰も積極的には言い出せないのである。私は、ISO90001の審査官ではないが、審査では、審査官の横にガラスの専門家として立ち会ったので、本稿は、その私的感想である。
さて、海外取引のある大企業の、購買の安全インターフェースのためのISOは、中小企業には、効率面、コスト面に措いて無駄が多すぎるから、もうしばらく放っておけば、自然淘汰が起り、ISOの取得活動の騒ぎは収束するには違いないが、その間、中小企業が無駄な努力にあえいでいるのを、何とか止めることができないのであろうか。そこで、私なりの纏めである。
①.品質管理はこじんまりと、基本に立ち返ってやったほうがいい。その会社の規模と技術にあった助言こそが求められている、といった実態がある。
②.大企業は受け入れ検査のラベル代わりにISOを使うのではなく、大企業が物品の購入を独自の受け入れ検査方式でやれば、小規模な企業がISOの認証など取る必要はないのである。
③.ISOの審査機関は、品質の向上につながらない審査の実態で、社会に非効率なサービスを振りまかない方がいい。例えば、定期検査で不適合な箇所を指摘した場合は、責任を持って、品質向上につながる具体策を必ず明示し、改善を指導すること。
ISOの認証取得という名の下に、どれほど益のない努力とお金が捨て続けられているか。ISOのマネージメントシステムが全産業に広がれば、地球規模での品質管理や環境管理が上手くいくというような概念は、全体としては、巨大な虚構であることを、少なくとも日本の企業から発信することはできないのだろうか。
(2016.07)
|

