|
不動産屋から電話があったと、妻が言う。「マンションのお宅の空家、もうあと7年で築47年となり、不動産価値がゼロになるのはご存知でしょう。もう、購入時の半額になっていますが、今なら、まだ価値があって買い手があります。お売りになるなら今のうちです。」私が不在だったので、「また後ほど・・・」と、不動産屋は、主人の私に電話する積りらしい。
 不動産屋は、それなりに正しい見解を述べているのかもしれないが、私はコンクリートの専門化である。「築47年となり、不動産価値がゼロになる」とは、税制上の単なる決め事で、価値と直結する建物の劣化の本質とはまったく関係が無い。果たしてこれを不動産氏はご存知か。いや、税制上の制度に在る、もっともらしい口実を利用して、慌てた我々に付込もうとしているだけとすれば、「おれおれ詐欺」の手下のような口調は性質(たち)が悪い。
不動産屋は、それなりに正しい見解を述べているのかもしれないが、私はコンクリートの専門化である。「築47年となり、不動産価値がゼロになる」とは、税制上の単なる決め事で、価値と直結する建物の劣化の本質とはまったく関係が無い。果たしてこれを不動産氏はご存知か。いや、税制上の制度に在る、もっともらしい口実を利用して、慌てた我々に付込もうとしているだけとすれば、「おれおれ詐欺」の手下のような口調は性質(たち)が悪い。
コンクリートが劣化して、その不動産価値がゼロになるとはどういうことか。コンクリートの中には鉄筋が入っている。この鉄筋が錆びて、そのさびが膨れて、周囲のコンクリートを割る。鉄筋が錆びやすくなるのは鉄筋を包むコンクリートが中性化したためである。コンクリートが本来持つアルカリ性によって、中に入った鉄筋が錆びないでいたのだが、コンクリート自身が、空気中の炭酸ガスに侵されて、そのアルカリ性を失い、鉄筋を錆び易くさせることがコンクリートの中性化劣化の意味である。
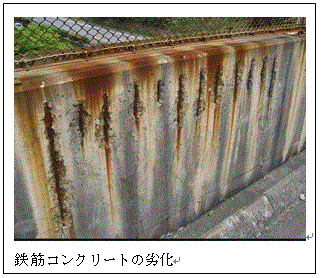 詳しく言えば、コンクリートの中には水酸化カルシゥムがあって、それがコンクリートをアルカリ性にしているのだが、空気中の炭酸ガスの浸透によって炭酸カルシウム(これが中性)ができる。しかし、この炭酸カルシウムはコンクリート自身を脆弱化させるものではないとされている。
詳しく言えば、コンクリートの中には水酸化カルシゥムがあって、それがコンクリートをアルカリ性にしているのだが、空気中の炭酸ガスの浸透によって炭酸カルシウム(これが中性)ができる。しかし、この炭酸カルシウムはコンクリート自身を脆弱化させるものではないとされている。
コンクリートの耐久性とは、建物を建てた時の打設ンクリートの配合と、建物の保護の状況でコンクリートの耐久性が維持できる期間が決まる。充実なコンクリートだと炭酸ガスの浸透は少なくなる。マンションの壁にタイルが貼ってあるのが好いのは、コンクリート表面が剥き出しである「打ちっぱなしコンクリート」と較べると、中性化の進行を数倍は引き止めているからである。空気中の炭酸ガスの浸透というからには、設計時の、鉄筋を覆うコンクリート厚さももちろん関係するのだが、ここではあまり言及しない。
凡そ40年前に購入したマンション(condominium)は阪急不動産、竹中工務店の物件だった。入居して2年目に、屋上に設置された浄水槽へ送るポンプの音か水音かが騒音となり管が通る箇所の住民に安息感がないということで、善処を申し入れた。交渉などは合ったが、結果、ポンプ位置を変えることで改善がなされた。さすが、大手の会社は名を大切にするのだという印象を持った。
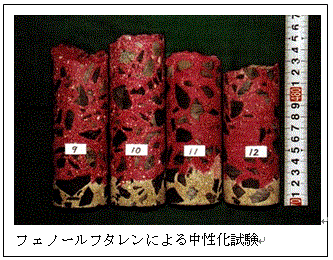 このマンションにはまた、うるさ型の一級建築士がいて、外壁塗装はアクリル系塗料なら10年間隔で補修が必要、バルコニーに少しでもひびがあるようなら直ぐ補修と、我々の修繕積み立て金から出すことでどんどん進めようとする。買ったとたんに補修計画とは、当時私もコンクリートにはまったくの素人だったので、本当に口うるさい頑固な人だと思っていた。
このマンションにはまた、うるさ型の一級建築士がいて、外壁塗装はアクリル系塗料なら10年間隔で補修が必要、バルコニーに少しでもひびがあるようなら直ぐ補修と、我々の修繕積み立て金から出すことでどんどん進めようとする。買ったとたんに補修計画とは、当時私もコンクリートにはまったくの素人だったので、本当に口うるさい頑固な人だと思っていた。
ところで、このマンション40年経っても綺麗で、価値は比較的高値で維持されている様子である。今は、私も少しはコンクリートの専門化である。あのうるさ型の一級建築士のアドヴァイスの価値が分かるようになってきた。
それでは、マンションのコンクリートか健全であるかどうかはどうして調べればいいのか。コンクリート壁から試料片(コアー)を抜き取ってそのアルカリ性をフェノールフタレン液をかけて赤くなるかどうかを調べれば好いだけである。鉄筋のある場所が、赤く発色した部分内に在れば、未だ、鉄筋が腐食する心配はない。コンクリートコアーを、マンションの壁から抜くのは専門会社の手が必要となる。
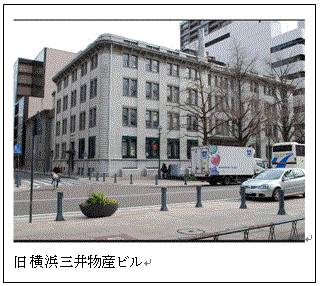 日本で一番古いコンクリートの建物は、「旧横浜三井物産ビル」で凡そ100年前の造りである。あのエンパイヤ・ステートビルディングは90年近く維持されていることになる。「築47年」の縛りではないが、マンションも天井から水が漏れたりしない限り、100年程度はもつと考えたほうがいい。住むには支障がないのである。従って、芦屋や、田園調布にある限り、このコンクリートの建物の取引価格は落ちないのである。
日本で一番古いコンクリートの建物は、「旧横浜三井物産ビル」で凡そ100年前の造りである。あのエンパイヤ・ステートビルディングは90年近く維持されていることになる。「築47年」の縛りではないが、マンションも天井から水が漏れたりしない限り、100年程度はもつと考えたほうがいい。住むには支障がないのである。従って、芦屋や、田園調布にある限り、このコンクリートの建物の取引価格は落ちないのである。
未だ50年も経過していない多摩ニュータウンや千里ニュータウンの取り壊しと建替え例は、旧式となった部屋の大きさ、キッチンや風呂の狭さと設備の古さにその原因があり、加えて耐震基準の見直しがあったことによるのである。
それでは、冒頭の「築47年」の縛りとは、何だったのか。会社が新築のビルを購入しょうとして、1億円のビル1億円を支払ってしまうと、会社の今年度の利益は無くなり、税を支払わなくてもよい。国税局はそれでは困るので、1億円のビルは47年間で分割支払うこととし、今年は1/47だけ支払って、残りの利益には課税できるように仕組んだのである。すなわち、単なる税制上の取り決め事項なのであり、「場所がいいから住みたい。」という、ビルの不動産価値とはまったく関係の無い数値だとも言える。あの冒頭の不動屋さんは、この知識があって、敢えて、「不動産価値がゼロになるのはご存知でしょか。」と電話してきたのか。
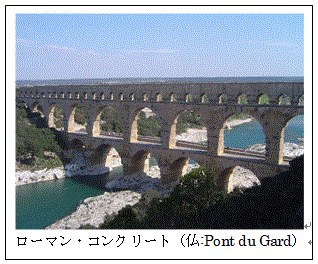 奈良の法隆寺五重塔は1400年前の建物である。木造はこの期間の耐久性があるのである。この木材に対して鉄筋コンクリートの100年程度の耐久実績は、あまりにも儚いものではないか。しかし、現在のポルトラルセメントではないが、同じような成分の火山灰からできたコンクリートはローマン・コンクリートと呼ばれ、ローマ時代に造られた集会所のドームや水道橋は2000年以上経った今でも使われている。
鉄は武器としては有ったが、鉄の棒を入れることでコンクリートの強度が増すとは知らなかったのではある。お陰で、2000年以上経ったローマン・コンクリートが今もひび割れ劣化することなく使われていのは、皮肉なことではないか。
奈良の法隆寺五重塔は1400年前の建物である。木造はこの期間の耐久性があるのである。この木材に対して鉄筋コンクリートの100年程度の耐久実績は、あまりにも儚いものではないか。しかし、現在のポルトラルセメントではないが、同じような成分の火山灰からできたコンクリートはローマン・コンクリートと呼ばれ、ローマ時代に造られた集会所のドームや水道橋は2000年以上経った今でも使われている。
鉄は武器としては有ったが、鉄の棒を入れることでコンクリートの強度が増すとは知らなかったのではある。お陰で、2000年以上経ったローマン・コンクリートが今もひび割れ劣化することなく使われていのは、皮肉なことではないか。
 しかし、複合材料としての鉄筋コンクリートは素晴らしい発見である。不均質なコンクリートと付着して、剛性のある鉄筋が大部分の応力を引き受ける。均質な鉄筋が力を均等に分配するから、コンクリートの最も脆弱な部分に応力が集中することは無く、破壊につながることが避けられる。こんな面白い材料の組み合わせを誰が考案したのか。
しかし、複合材料としての鉄筋コンクリートは素晴らしい発見である。不均質なコンクリートと付着して、剛性のある鉄筋が大部分の応力を引き受ける。均質な鉄筋が力を均等に分配するから、コンクリートの最も脆弱な部分に応力が集中することは無く、破壊につながることが避けられる。こんな面白い材料の組み合わせを誰が考案したのか。
約150年前の1867年に、フランスの植木鉢をつくる職人が、モルタルの中にたまたま針金を網状にいれたところ、ひび割れの少ない薄い丈夫な鉢ができたことから、鉄筋コンクリートが生まれた。ということらしい。1875年には、そのモニエの設計によって、Chazelet城に世界初の鉄筋コンクリート製の橋が架けられた、とある。
ポルトランドセメントが1800年代の前半に登場した歴史を考えても、現代インフラを形成するコンクリートの基盤技術が、如何に歴史的に浅いものかを知ることとは興味深い。しかしその中で、エンパイヤ・ステートビルディング(102階)高さ381mが鉄骨鉄筋造りで1931年に建てられている。凡そ90年前、タワー・クレーンも無い中、現在に匹敵する鉄筋コンクリート技術が完成していて、高速のエレベーターが走っていたのである。因みに、日本一のあべのハルカスは(60階)高さ300mである。
話は鉄筋コンクリートから少し飛ぶが、土木建築では、砂利のことを骨材という。最初この言葉に触れたとき、私は、てっきり鉄骨のことだと考えて話を聞いていた。確か、曾野綾子さんも、「湖水誕生」という本を書かれたとき、「現場で話を聞きながら、骨材と聞いて鉄骨のことを考えていた」というような話を、講演の席でされていた。
この業界では、PC、PCa、NATM、AE剤とか、やけにあちらの文字での短縮用語があり、スランプ、ワーカビリティー、コンシスタンシィー、ラーメン、フーチングなど、日本語に咀嚼しないままでの横文字が氾濫している。多分、コンクリート技術には日本は後進国で、技術導入を焦ったためかもしれない。
セメントの粉と砂と砂利を混ぜ、適当量の水を入れて、更に混ぜればコンクリートの出来上がりである。素人がホームセンターなどの情報を基にしてコンクリートを造るとなると、バケツいっぱいのセメント1に対して、バケツ砂2、砂利(小石)3、或いは砂3、砂利6でよいとされているから、配合割合とは非常に幅があり、どう配合しても、セメントさえ入れておけばコンクリートなるものは硬くなってでき上がるのである。
都市でも町でも、駅や橋、護岸や下水道はコンクリートでできている。我々の社会インフラ(基盤)にこのセメントたるもの欠かせないものであるのだが、それはまた、この材料が大量生産され、通常はセメント一袋(25Kg)500円程度で売られているが、量販店では300円程度の場合もあり、多分工場卸は1Kg当り10円程度ではないかと思われる安さに助けられたものである。今時、水でも安くて1Kg当り50円はする。1Kg当り10円というのは、土の砂、切り屑ぐらいで、他には無いのではないか。
このセメントの主原料は石灰石であり、近畿地方では伊吹山であり、日本の至るところにあって、日本が資源に恵まれた唯一の産業と言ってもよい。その工場は既に巨大な装置産業となっていて、人件費をかけない構造となっているから、製品安価につながっている。1990年ごろが生産のピークであって、凡そ1億トン製造されていたが、箱ものの基盤造りを良しとしない国政への転換が行われていった今、生産量はその半分である。パン屋が半分しか売れないと、値上げの他はないが、セメントは値が上がっていないのである。何故か。
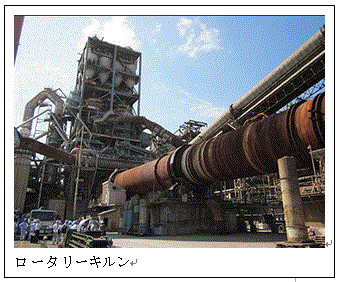 セメント工場の中心設備は、巨大な回転窯(ロータリーキルン)であって、そこで原料の石灰石などを溶かしてセメントに変えている。燃料は石炭であるが、廃タイヤを燃やし、産廃の油を燃やし、汚泥、焼却灰をセメント原料に変えて利用している。セメント産業は産廃の処分場を兼ねており、有償でそれらを引き取っているから、安価なセメント供給につながっている。セメント原材料の半分は持ち込まれた産業廃棄物が利用されており、今や、循環型社会構造を担う優良産業なのである。
セメント工場の中心設備は、巨大な回転窯(ロータリーキルン)であって、そこで原料の石灰石などを溶かしてセメントに変えている。燃料は石炭であるが、廃タイヤを燃やし、産廃の油を燃やし、汚泥、焼却灰をセメント原料に変えて利用している。セメント産業は産廃の処分場を兼ねており、有償でそれらを引き取っているから、安価なセメント供給につながっている。セメント原材料の半分は持ち込まれた産業廃棄物が利用されており、今や、循環型社会構造を担う優良産業なのである。
三文文士の下手な物語を綴ってきたが、私がセメント・コンクリート分野の技術士であることを明らかにして、この内容があながち、でっち上げ、思い付きでないことだけは明確にして措きたい。
(2016.12)
| 
