|
小学生3,4年の頃であった。玄関先に小さな池を造り、その池で、近所の家のように、金魚を泳がせたいと思った。友達の一人の家にセメント袋があった。砂は家の庭を掘れば出てきた。セメントを少しもらって、砂と水に混ぜ、掘った穴にその泥団子を貼りつけた。小さな池らしきものはできたが、そこには水が溜まらなかった。この池造りは失敗したと思った。二度三度と試みたが結果は一緒だった。
私はコンクリートが水を簡単に透すことを知らなかったのだ。そういえば、現在では、マンションのコンクリートの床にこぼした水が、あっという間に階下の天井から落ちてくることは経験されているところである。水を溜める池にするためには、練ったコンクリートに防水剤を入れる、コンクリート表面に防水剤を塗るなどの処理が必要だったのである。
セメント粉と砂を水で練っているとき、コンクリートは乾いて固まるから、水は粘性をつけるために入れている、と思っていた。しかし、セメント粉、すなわち、石灰石と粘土との高温の焼き物であるアリットという成分は、セメント製造の焼成窯(キルン)から出てきたときは、茶碗の陶器みたいなものである。クリンカーというが、これを粉砕したものがセメント粉なのである。セメントは水と結合して(水を取り込んで)初めて硬くなる。これが、砂や砂利を糊のように接合して硬いコンクリートにするのである。だから硬くなるためには水が必須な成分なのである。これを水和という。
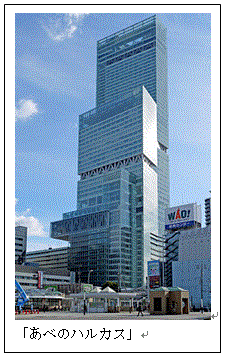 コンクリートの配合は、セメントと砂、砂利、あとは水だけである。しかし、地上60階建の「あべのハルカス」(地上60階、地下5階、塔屋1階 鉄骨・鉄筋コンクリート造)では、それらをどのような配合割合にすれば、1階を支えるコンクリート柱と、60階上にあって、その1階だけを支える柱の強さのスミ別けができるのか。すなわち、ハルカス1階を支えるコンクリート柱は60階全部の重量を支える強さのコンクリートが使われているわけである。
コンクリートの配合は、セメントと砂、砂利、あとは水だけである。しかし、地上60階建の「あべのハルカス」(地上60階、地下5階、塔屋1階 鉄骨・鉄筋コンクリート造)では、それらをどのような配合割合にすれば、1階を支えるコンクリート柱と、60階上にあって、その1階だけを支える柱の強さのスミ別けができるのか。すなわち、ハルカス1階を支えるコンクリート柱は60階全部の重量を支える強さのコンクリートが使われているわけである。
この、コンクリートの強さに関係する問題の提起に、超高層ビルの「あべのハルカス」を持ち出すやり方は面白いが、実際は、この建物の鉄骨・鉄筋コンクリート造とは、H鋼と称する太い鉄筋の柱が60階の階層からなる骨格を先ず形成して、その鉄骨が、加わる全荷重を支えているわけであり、その補助としてのコンクリートの強度では、極端なことを言えば、1階を支えるコンクリート柱でも60階の柱でも、それほど大きな強度の相違はないのであるから、このビルで、この問題を提起することが間違っている。
それでは、鉄骨のない鉄筋コンクリート造なら、1階を支えるコンクリート柱は上部の全加重を支えるという設定が成り立つ。この問題を20階建ての一般ビルの柱で問いかけると、このビルの全上層階を支える1階の柱のコンクリートと20階だけを支えているそれを考えてみる。では、どうすれば強度の違いのあるコンクリートを造ることができるのか。
コンクリートの強さは水とセメントの重量割合によって決まるとしたのは、凡そ100年前、大学の助手だったエイブラムスの発見である。なんと、この法則が今もなお生きているのである。使うセメント量に対してできるだけ水を少なく入れて練るのである。無論大量のセメントに対して水の一滴とはいかない。使える、すなわち練って型に押し込める位の実用性のある粘性状態のものでの比較である。水が少なくても練りやすくできるというので、高性能AE減水剤という薬品が使用される。
したがって、通常は使われないほどの高強度のコンクリートを使う建設現場では、このセメント量と水量で確かにこの強さのコンクリートができることをあらかじめ証明しておかなくてはならないのである。必ず試験煉りと称する実証実験が行われる。傍目には、セメントと、数種の砂と砂利の組み合わせだから、コンヒュータに公知のデータを入れておけば、訳もなく計算できるのにと思うが、強度には生コン会社のミキサーの練り方が関係するのか、とにかく試験煉をやるのである。配合のセメント量と水量の割合が問題だとは言うが、割合はともかく、高強度コンクリートほどセメント粉が多量になる。
セメント粉が多量になると、実は別の問題が発生する。セメントが水を取り込んで硬くなるとき、結合の反応熱が出る(水和熱)。筆者は過去に、このコンクリートの温度を測定したことがある。コンクリートを練って、1立方メートルのパネルの中に入れ、1日だったか、1日半だったか、その辺りの時間に、内部温度は100℃以上になった。ということは、水はセメントの化合物アリットと水和するが、余剰の水は内部で沸騰していたに相違ない。内部に巣ができるかどうかはともかく、橋脚などコンクリートブロックの内部と表面に温度差ができると、丁度、熱い湯を入れたガラスコップが冷たい机に置かれると割れると同じで、コンクリートブロックの表面にひび割れができやすくなるのである。
内部を高温にしないようにするために、コンクリートブロック内部にパイプを入れて水冷をしたり、ポルトランドセメントの半量を、強度の発現は少し遅いが、反応熱の少ない高炉セメント(高炉スラグ)で置き換える方法がある。
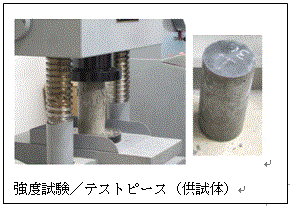 建設現場へのコンクリート供給は生コン会社が請け負っている。現場は発注したコンクリートの流動性や強度については、受け入れ検査の義務がある。流動性に着いては、決められた簡単な検査方法(スランプ試験)がある。しかし、現場に打設したコンクリートが発注したコンクリート強度を本当に持っているかどうかは、その場では分かりようがないのである。コンクリート強度というものは打設したときに採っておいたテストピース(供試体)を一ヶ月後に試験して初めて分かるのである。すなわち、コンクリートの性質として、最終強度となるまでには、一ヶ月の熟成期間が必要なのである。関連したテストピースの情報が(エッセイ 73)キャッピング にあるので、ご参照願いたい。
建設現場へのコンクリート供給は生コン会社が請け負っている。現場は発注したコンクリートの流動性や強度については、受け入れ検査の義務がある。流動性に着いては、決められた簡単な検査方法(スランプ試験)がある。しかし、現場に打設したコンクリートが発注したコンクリート強度を本当に持っているかどうかは、その場では分かりようがないのである。コンクリート強度というものは打設したときに採っておいたテストピース(供試体)を一ヶ月後に試験して初めて分かるのである。すなわち、コンクリートの性質として、最終強度となるまでには、一ヶ月の熟成期間が必要なのである。関連したテストピースの情報が(エッセイ 73)キャッピング にあるので、ご参照願いたい。
一ヵ月後に試験できたテストピースの強度が、一ヵ月前に、打設コンクリートに設定されていた値を下回った場合はどうなるか。既に硬化している、一階層を占める鉄筋コンクリートをすべて撤去しなければならないのである。一大工事になるのである。
過去、実際に不良コンクリートを撤去した例があるかどうかは知らないが、あったとすれば、この大工事の費用の負担は不良コンクリートを納入した生コン会社が負担しなければならない。この危険性を意識して、生コンクリート会社は、間違っても強度が下回ることのない、必要以上に強度のある生コンクリートを供給しているに違いないのである。
この時代、一ヶ月も経たないと判らないような判定検査が本当に有効なのか。各社はコンクリートについて一ヵ月目の強度と3日目の強度との相関図を持っていて、多分3日目の強度で、最終強度を判定しているものと思われるが、それにしても、コンクリートの受け入れ検査時に、即刻、何とか強度判定ができないものだろうか。
コンクリートの強度は、エイブラムスの法則により、コンクリート中の水とセメント量の比で表されることは、上述の通りである。それでは、5ミリ目のふるいを持ってきて、現場に到着したばかりの生コンクリートを篩い、一定量のモルタル量を採り、電子レンジで水和を始めたばかりのセメントからすべての水を蒸発させて、その消失重量から水量を求め、一定量のモルタル量に含まれるはずのセメント量から、水とセメント量の比を求め、この値で、受け入れたコンクリートの強度を推定しょうとする試みがあった。その実用化に向けた実証実験には、私も参加していたが、条件付きの測定値や引用データから求める水セメント比では、結局は、相関関係からなる推定値に終わる感が強い。これは試料を一定量だけ採り、そこにある水量を電気的に検出しても、その水量は相関関係からなる推定値に終わるという意味では、いずれの測定法でも、水の絶対量が得られないという点では同一である。
話は飛ぶが、呉にあった巨大タンカーの造船所を見せてもらったことがある。鋼板の切り出し、鋼板の曲げ、そして溶接と、重機を別にすれば、あの精巧に見える船の形骸の殆どが熟練工の手作業だけで行われていた。建築現場を見たとき、一番にそれを思い出した。
名建築家と称えられる人がいる。安藤忠雄さんでも、隈研吾さんでも、その名建築の設計図面にはミリ単位で、梁の長さ、バルコニーの曲線が描かれていることであろう。しかし、タワークレーンが動き回る中、足下の危ない現場で、コンクリートパネルを組み上げるのは大工さんである。この組方で、寸法も姿も決まるのである。打ちっぱなしのコンクリートの色は生コンクリート屋さんで決まり、コンクリート表面の緻密さは、コンクリートを型枠に充填するコンクリート工の腕次第なのである。すると、私には、将棋の盤面における「歩」の動きで名建築が決まってくるようにも思えるのだが、いゃいや、名建築家の名を慕って、名立たる「歩将」が集まってくるのかもしれない。
1998年というから、今から10余年前、「姉歯建築士事務所」が起こした耐震疑惑事件があった。姉歯建築士は、コンピュータ計算でしか分からない結果に修正を加えて、構造計算書をでっち上げた。イーホウムズという確認検査機関が認証し、ヒューザーというマンション分譲販売会社がその物件を安い価格で販売したという構図だったと覚えている。正に建築業界を震撼させた事件であった。
大きな地震では、つぶれるかもしれないマンションを大金を出して購入した住民の怒りは当然である。変な味のパンを買わされたというのとは訳が違う。建築物には法規で二重三重に護られているはずだとの認識が、安心感が意識の何処かにあるのである。
建物の耐震強度を低く設計すれば、使う鉄筋の数を少なくし、コンクリート強度を低く、或いは、柱の太さや壁厚を少なくして、使用スペースを多くすることができる。従って、建物はそれだけ安い価格でできる。その強度偽装をチェックすべき検査機関がわざと見逃してくれるのである。
豪華で価格が低いマンションへの需要がある以上、また、透明性を欠く、コンピュータが弾くブラックボックスがこの建築確認行為の主要点を占めるときては、世の趨勢として、耐震偽装工作は起こりうるし、従って、多くの既存マンションなどへの波及、ひいては建設業界への波及は必死と見られたが、何故か、上述の建築士と会社だけを血祭りに、ことは収斂してしまった。
裁判の席上だったか、或いは追求する記者へのコメントだったか、姉歯建築士が言った。
「計算上、急に倒壊する、とか、そう言った設計にはなっていません。そもそも基準自体がかなりの厳しめのものになっているだけで…」 構造設計を知らない、素人に近い私にも気にはなる話である。果たして、偽装建築が耐震性を持って残存し、優れたお墨付きの建築が倒壊するということはないのか。
阪神淡路大震災の後、ビルや阪神高速道路の倒壊の、余りにもひどい惨状を受けて、土木、建築学会の報告会がよく開かれた。そこで私が聞いたのは、「安全係数を3にするのか、4にするのか」といった業界関係者の質問であった。物事が係数で決まってくるとは、構造の緻密な計算とは裏腹に、なんと、大雑把な考え方ではないか。
もし、安全係数を高くして、構造体の強度を増すのならば当然のことながら高い強度のコンクリートが必要とされ、鉄筋の数量も多くなる。しかし、部材の剛性が高くなると、地震にたいする柔軟性は少なくなる。鉄筋の数が多く密になると、そこに押し込むコンクリートには充填不良が起こって、欠陥ができる可能性もあるのである。
耐震建築の根幹である構造計算には、ブラックボックスに近いコンピュータ計算が鍵を握っているというなら、その中には想定される色んな地震への応力対応があるはずなのだが、想定外の地震の動きも起こりうると、だから全てにもう一度、安全係数を掛けて2倍3倍の強度にして措く、もうそこには設計士が最初に求めた、デザイン上の柔軟な耐震設計思想はあっても、埋もれてしまっているかもしれない。
パン屋さんがパンを作る規制は、衛生点検ぐらいで、機材や材料などは、常識範囲、消費者への保証は、味の旨いか、不味いかであろう。それに較べると、人の生命を左右する居住空間は、材料から始まって、耐震設計に至るまで、安全係数や法規制で固められ、権威で固められてはいるが、例えば、説明してきたような、コンクリート強度の受け入れ試験の不確定さを始め、現場で働く人の腕の巧みさが決め手となったり、ブラックボックスの多いコンピュータ計算に依存しているとか、外から見れば、直感的だが、権威の脆さも感じられて、否定された姉歯建築士設計のビルが、必ずしも、地震に弱いとは言い切れない一面もあるのではないかと、思ったりもしてしまう。
(2016.12)
|

