|
私が最初に就職した会社がガラスびんを製造している会社であった。私は研究員として、比較的自由に色々なことを学ばせてもらった。中に、ガラスの割れ方を見て、そのガラスびんが割れた原因を、自分なりに探求した経験があった。
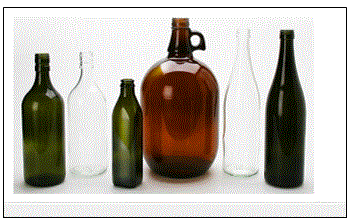 割れたびんの外観ではなく、割れたガラスの断面を見てみる。断面は滑らかだが、湖面にできる「さざ波のようなマーク」が割れの進む方向にできるから、割れの起点を探すためには、「さざ波のようなマーク」を逆に辿る。
割れたびんの外観ではなく、割れたガラスの断面を見てみる。断面は滑らかだが、湖面にできる「さざ波のようなマーク」が割れの進む方向にできるから、割れの起点を探すためには、「さざ波のようなマーク」を逆に辿る。
割れの起点をオリジンという。このオリジンに破壊をもたらした原因の痕跡がここにある。熱ショックだったのか、ものが衝突した衝撃に依るのか、はたまた、曲げを伴う強い外力を受けたためか。
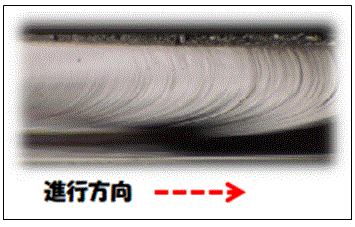 熱ショックの形状を1.に示す。さざ波マークも少なく、平坦で、ほとんどマークらしきものがないのが特徴といえば特徴。衝撃による破断の形状を2.に示す。オリジン模様はパッカーションコーンが見られる。殴った方の径が小さい。曲げの力を受けてできた割れは、いったん止まっている熱ショックのびりや、衝撃による小さな割れ跡から始まるのが特徴。
熱ショックの形状を1.に示す。さざ波マークも少なく、平坦で、ほとんどマークらしきものがないのが特徴といえば特徴。衝撃による破断の形状を2.に示す。オリジン模様はパッカーションコーンが見られる。殴った方の径が小さい。曲げの力を受けてできた割れは、いったん止まっている熱ショックのびりや、衝撃による小さな割れ跡から始まるのが特徴。
びんは、製びん機の型にガラスの塊(ゴブ)をいれ、口部に空気を入れてガラス本体を膨らませ、その真っ赤なガラスびんを除冷窯でゆっくり冷やしてできあがる。除冷窯をコンベャーに乗って出たところで、室温にまで温度が下がったびんに、ひび割れが入っていることがある。
割れの起点は、製びん機で造られたばかりの高温のびんガラスの肌が、それをコンベァーに誘導するガイドの細い冷たい導線に接触すると、できたばかりのガラスびんに「ビリ」ができて、除冷窯に入った処、或いは除冷窯コンベアーから出た処で、その「ビリ」跡から破損が進む。
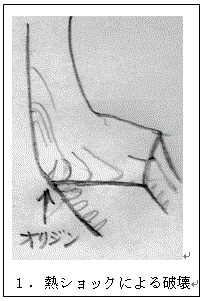 この急冷でできた起点の破損の形状は、殴られた衝撃できた激しい形ではなく、ほんの少しの盛り上がりが見られる上述の熱ショックの形状である。こういった観点から、「今回の割れの原因は、ガイドの線が冷たくって、その位置から割れが起こっている」と、製造に伝えたことがある。「不思議なことをいうなぁ」と、製びんの係長は私のいうことを認めて、ガイドの導線をバーナーで暖めるような改善をしたと言った。
この急冷でできた起点の破損の形状は、殴られた衝撃できた激しい形ではなく、ほんの少しの盛り上がりが見られる上述の熱ショックの形状である。こういった観点から、「今回の割れの原因は、ガイドの線が冷たくって、その位置から割れが起こっている」と、製造に伝えたことがある。「不思議なことをいうなぁ」と、製びんの係長は私のいうことを認めて、ガイドの導線をバーナーで暖めるような改善をしたと言った。
熱ショックによる割れの典型は、冷たいコップに熱い湯を注いだ時のコップの割れである。このコップを冷たい机に置くと、机にふれた表面のガラス層が縮もうとするが、内側の熱湯に触れたガラス部分は、熱く膨張したままなので、結局、表面のガラス層は縮めず、それだけ内側ガラス部分に引っ張られた状態となり、びん底に着いていた何だかの傷跡を起点に割れてしまう。
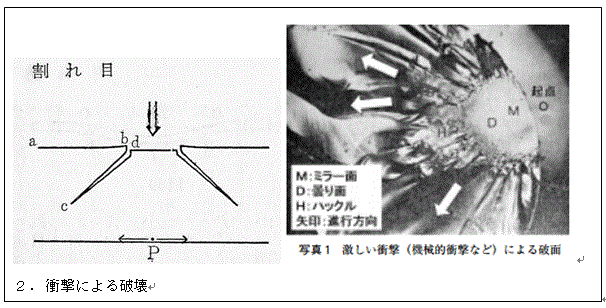 計装係に居た横洲さんは、「小牧君、製造現場はびんの割れで困ってるんや。全部は解っていなくとも、君が解っているところだけでも、割れのメカニズムを、皆に説明できんのかいなぁ。」と、親切心から言ってくれるのだが、実は巧く説明できるのは希なケースで、解らない現象が多すぎる。
計装係に居た横洲さんは、「小牧君、製造現場はびんの割れで困ってるんや。全部は解っていなくとも、君が解っているところだけでも、割れのメカニズムを、皆に説明できんのかいなぁ。」と、親切心から言ってくれるのだが、実は巧く説明できるのは希なケースで、解らない現象が多すぎる。
確かに、熱の歪みで割れる形の起点を持つものは、製造中に割れるのならまだしも、市中に出回ってから、酒の充填機や取扱中に(有ったビリを起点として)機械的な力で割れても、起点には熱の歪みでできた小さな割れ跡が残っているから、それは、製造に問題があったことになる。だから、割れた破片から、割れの起点に関係する模様を読み取ることが必要なのだが、起点の部分のガラス片がうまく残っていないこともある。
或いは、びんの高さ、口径にばらつきがあって、酒の充填機使用の際、機械的にこじることや、酒店の取り扱いでびんをぶつけることがあるかも知れない。その時は、ねじりや、衝撃跡が残るから、割れの破片がうまく回収でき、起点のマークを読み取ることができれば、取り扱い側のミスと指摘できる場合もあるかも知れない。
しかし、未だ旨く説明できない現象が多いからと、割れの説明会を社内で開けないでいたのだが、その一つがびんの「縦割れ」である。
やや肉厚のびんであったが、割れが起こっているのは除冷窯の出口で、コンベアーに運ばれてきたびんが割れるように見えるのだが、破断面を見ると割れに沿って徐冷窯に充満した白い粉の跡が断面の表面にはあるから、除冷窯に入った時点で既に表面には割れが走ったのである。更に割れの起点に辿ると、「熱ショック」でできたオリジンが、びん底がコンベアーの金網に接触する処にある。ところが、びん底は厚く除冷窯に入った時点ではガラスびんは未だ赤く熱いので、一般的には、少々の熱ショックでビリができても、熱いガラスが溶け込んで割れには発達しないので、これは矛盾である。
解からない、解からないと思っていたら、偶然真相が現れた。溶融窯が停止すると言うことになった。火を落とす前に、びんの着色の実験をしておこうということになった。
ガラスの原料に着色剤を入れて着色すると、その槽窯全体のガラスを再び無色の素地に戻すまでには数日かかる。その間の色むらのあるガラスは商品として使えない。着色剤が何処かに残って、無色のガラスを汚すからである。従って、溶けた無色のガラス素地を排出する窯の出口付近で、着色ガラス(着色フリット)を混ぜ込んで色ガラスを造れば、必要な期間だけ、簡単に色々な着色ガラスが得られるとして、そのテストを遣ってみるために、製びん機をもそのまま動かし続けた。するとどうだろう、均一には混ざりきらないガラス素地で、縦に色筋を見せるびんが造られた。それはいいのであるが、除冷窯を出たところで、この着色びんは、全部、縦に割れていたのである。
そうか、私は製造中のびんの縦割れの現象を、製びん後の、なんだかの熱ショックと見ていたが、実は、溶融窯でのガラス素地そのものの混ざり方にも問題があって、製造中のびんが縦割れにつながったと考えられる。だがしかし、製造中の素地の状態を、歪み検査器で観察し、程度を決めたとしても、その素地の改善をはかることには製造上の別の難しさがあるといえばあるのである。
広島ガラス社を止め、次に私の勤めた場所は、ガラス製品検査協会というところであった。輸出されるガラス製品を検査して、一定の品質を保証する協会だったので、時々、ガラス製品に関する特別な調査依頼もあった。
直径15センチメートルはあろうかという水晶球を持ってきて、「水晶球だというのだが、ガラス球かもしれないと思う。簡単に水晶かどうか見てもらえませんか。」借りた金の形にこの水晶球を置いていくというものらしい。
歪検査器にかけてみると、大きいのにもかかわらず殆ど熱歪らしきものはなかったから、ガラスだったら石英ガラスだったのかもしれない。珠の中には結晶の璧界面らしきものも見えず、水晶ならでるはずの光軸の向きに出る干渉縞も出なかった。
 少し昔の話、オーナメント(装飾品)として鉛ガラスが主流の時代があった。灰皿も厚くて重厚なものがあった。ガラスは少し厚くなると成形した後、熱歪みを取るのに室温まで徐々に冷却していく時間を多く取らなければならない。冷却時間が短いと強い熱歪みが残り、使用中に傷が付くとそこから真っ二つに割れることがある。こんな苦情は、歪み検査器を覗いてみるだけでわかる。透明なガラスが強い虹色がかって見えるからである。強い白色でも危ないのに、虹色が出るというのは、光路の長さにも依るが、置いておくだけで勝手に割れる危険状態にある。時々そんな歪みが原因で破損したガラスがクレームとして持ち込まれることもあった。
少し昔の話、オーナメント(装飾品)として鉛ガラスが主流の時代があった。灰皿も厚くて重厚なものがあった。ガラスは少し厚くなると成形した後、熱歪みを取るのに室温まで徐々に冷却していく時間を多く取らなければならない。冷却時間が短いと強い熱歪みが残り、使用中に傷が付くとそこから真っ二つに割れることがある。こんな苦情は、歪み検査器を覗いてみるだけでわかる。透明なガラスが強い虹色がかって見えるからである。強い白色でも危ないのに、虹色が出るというのは、光路の長さにも依るが、置いておくだけで勝手に割れる危険状態にある。時々そんな歪みが原因で破損したガラスがクレームとして持ち込まれることもあった。
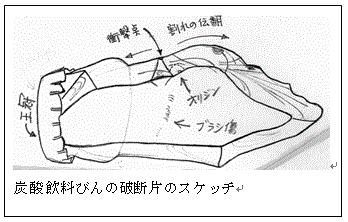 炭酸飲料メーカーから、びんの口部の破片を預かった。びんが割れて怪我をした被害者と係争中の物件だということだった。被害者は、「きつくぶつかってもいないのに中身の入ったびんが割れた」と言う。
炭酸飲料メーカーから、びんの口部の破片を預かった。びんが割れて怪我をした被害者と係争中の物件だということだった。被害者は、「きつくぶつかってもいないのに中身の入ったびんが割れた」と言う。
オリジンは、打ったはずの外部にはなく、びんの首の内側にあった。何故ビンの内側に、びんの製造中にはできない傷があるのか。多くの回収びんの首の内側を観察してみた。炭酸飲料ビンの首の内側には洗びんをブラシでやった擦り傷があり、中には小さなひび割れもあった。まず傷があって、その首に外から衝撃が加わると、内側のその傷を起点に簡単に割れることになる。その再現実験を試みた。以外に小さな衝撃で、同じ破断形状を示すものが現れた。
飲料品メーカーにその結果を報告した。メーカーとしては、びんは何かの角にぶつけて割れた。取り扱い不良が原因である。との見解が欲しかったようである。洗びん工程でできた傷が割れの直接原因という結論は望んでいなかったようであった。
オブントースターの前面ガラスが割れた、「その原因は?」という依頼があった。無論、ガラスの破片全てが持ち込まれていた。割れた板ガラスの破片から割れのオリジン(起点)を探してゆくと、オリジンの箇所が見つかった。破断面に熱割れのパタンが見えた。製造時、或いは加工時に何らかの熱的歪ができて、ガラス表面に小さな亀裂が入っていたところ、パンを焼く昇温時、または下降時に、例えば、冷却された風が吹き付け、オブントースターの前面ガラスはそのとき割れた、といったところであろうか。従って、原因は、前面ガラス製造時の欠点の見逃しであるとの判断をした。
 道を歩いていると、小型乗用車を降りた中年の女性が私に声を掛けた。「今、フロントガラスが粉々になった。前の自動車から何か飛んできたと現認していただけませんか」ご婦人は突然起きた事故に、気持ちが動転している風だった。
道を歩いていると、小型乗用車を降りた中年の女性が私に声を掛けた。「今、フロントガラスが粉々になった。前の自動車から何か飛んできたと現認していただけませんか」ご婦人は突然起きた事故に、気持ちが動転している風だった。
今のフロントガラスは安全ガラス(合わせガラス)となって、粉々に割れて視野をふさぐことはない。しかしこれは1970年ぐらいの頃である。未だ、フロントガラスに熱強化ガラスが使用されていた頃の話である。日本板硝子社から報告された文献があった。熱強化ガラスのフロントガラスが一度石で傷が付き、丁度その傷に、再び石が当たると、その箇所には微細な六角柱を残し、粉々に割れるというのであった。ということは、割れの外観を辿り、その六角柱を探し出せば、前の車が跳ね上げた石か何かを間接的に証明することになるかもしれないが、現実には、実験室でもない処で、粉状のガラスから微細な六角柱など探せるわけはない。しかも、私は前の車を見ていない。
「私は、前の車が石をぶつけたことも、いや、前の車を見てはいないので、何も現認はできませんが、とにかく車屋さんに連絡を取ってみてはいかがでしょうか。」と言うこと以外は、何の手助けもできなかった。
もう40年は昔の話である。こんな話が新聞に載っていた。動物園である。そこに設けた大きな板ガラスがある日、粉々に割られていたというのである。暴漢もガラスを割るために使われた器具も不明だとのことだった。多分強化ガラスであろう。この強化ガラスというのは、表面に圧縮応力が働き外力を跳ね返す強さがあるのだが、ガラス内部はその反対の引っ張り応力が働いており、隙あらば割れようとしている構造になっており、ここに最大の弱点を抱えていることは、ガラスの専門家以外にはあまり知られていない。
従って、表面にできた少しの傷、ガラス内部につながる端面の少しの欠けでも、板ガラス内部の強い引っ張り応力につながると、内面から激しい割れを誘発する危険性を常に孕んでいるのである。或る意味で、表面傷ができたものなら、自然崩壊を起こす可能性は十分あるのである。
前出の、ご婦人が乗っていた自動車のフロントガラスの場合も全く同様、前の車が跳ね飛ばした石でなくとも、自然崩壊に至った可能性も否定できないのである。
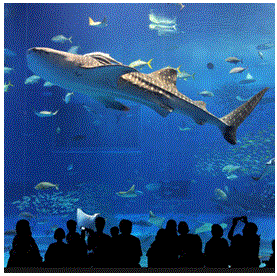 製びん工場ではこんなふざけた脅かしがあった。できたばかりのびんを除冷窯に入れずにそのまま室温まで冷やす。このびんは見た目には通常のびんと変わらない。ところがこのびんに小石を入れて軽く振るとどうなるか、爆発的に割れるのである。できたばかりのびんが冷却されるのは外表面で、びんの内面は熱く緩やかに冷却されるが、外表面に圧縮歪みを持ち、内面にはきつい引っ張り応力がかかったままになる。実は上記の板ガラスが強化される原理は、未だ熱い内に、板ガラスの両表面に冷たい空気を吹き付けるというものであり、板ガラスk内部には引っ張り応力が作用しているのである。
製びん工場ではこんなふざけた脅かしがあった。できたばかりのびんを除冷窯に入れずにそのまま室温まで冷やす。このびんは見た目には通常のびんと変わらない。ところがこのびんに小石を入れて軽く振るとどうなるか、爆発的に割れるのである。できたばかりのびんが冷却されるのは外表面で、びんの内面は熱く緩やかに冷却されるが、外表面に圧縮歪みを持ち、内面にはきつい引っ張り応力がかかったままになる。実は上記の板ガラスが強化される原理は、未だ熱い内に、板ガラスの両表面に冷たい空気を吹き付けるというものであり、板ガラスk内部には引っ張り応力が作用しているのである。
海遊館でジンベイザメが泳ぐ巨大水槽の円筒窓ガラスは、板ガラスを曲げて加工していると思う人は多いのではないか。しかし、あの円筒窓はガラスではなく、アクリル樹脂(プラスチック)なのである。アクリル板を積層して接着、硬化させて例えば25cm肉厚の円筒を現場で造り上げたものである。
(2017.01)
| 
