|
-紡糸ガラスノズル-
私に初めて与えられた研究課題が、開発中のガラスノズルの孔の周りに出る着色層の原因究明であった。
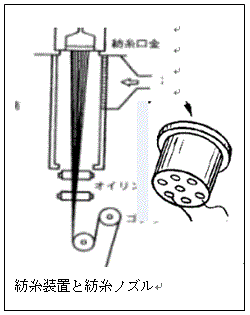 ポリエステル、ナイロンなどの合成繊維は、溶融状態にある樹脂をノズルの口金から押し出して紡糸する。その口金についているのが、紡糸ノズルと言う多数の細孔を持つ1cm直径の白金板であり、その細孔から糸が出てくるわけである。白金は高価な金属材料であるので、ガラス板に細孔を開けたノズルで代替出来れば好都合である。その代替品の紡糸ガラスノズルを、私たちの研究室で開発していたのである。
ポリエステル、ナイロンなどの合成繊維は、溶融状態にある樹脂をノズルの口金から押し出して紡糸する。その口金についているのが、紡糸ノズルと言う多数の細孔を持つ1cm直径の白金板であり、その細孔から糸が出てくるわけである。白金は高価な金属材料であるので、ガラス板に細孔を開けたノズルで代替出来れば好都合である。その代替品の紡糸ガラスノズルを、私たちの研究室で開発していたのである。
ガラスの板に糸の太さほどの細い孔を多数穿つことは、今なら石英ガラス板にレザー光を使うことで穿つことができるかもしれないが、当時は未開発の技術であった。この研究室で紡糸ガラスノズルの初期の開発段階は既に終わっていた。1センチ直径、厚さ1ミリのガラス盤に50個もの細孔を穿っていた。
どうすれば小さい穴を開けることができたのか。
ステンレスの細い線を1ミリ間隔で平行に並べ、各線は錘を付けて一定の張りを持つようにしてある。その平行した線群の上から0.3ミリ厚のカバーガラスを置き、再び平行の線群をその上に重ねる。これを繰り返し10段程度に積層物を造る。これをガラスの軟化点に近い700℃の炉に入れ、ガラス板を相互に軟化融着させて、積層体を造る。
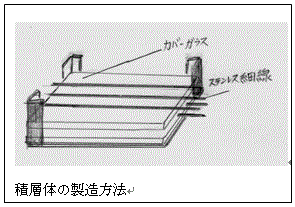 できた積層体を、平行線群と直行させて、およそ2ミリの幅にダイヤモンドカッターでスライスし、更にこれを研磨し、面取り機にかけて1センチ直径の円盤にする。この円盤に含まれる金属線は、この円盤を酸溶液に浸漬すると酸に溶かされて、ガラス盤に50個もの細孔ができる訳である。孔の直径は細い線の径と同じである。これでガラスノズルはできたのであるが、この金属線が抜けた穴を顕微鏡で観察すると、無色透明ではなく、まるで、人の目じりのような灰色の着色層が残るというのである。この着色層があっても穴は開いているので機能的には問題が無いのだけれど、孔にものが詰まっているとの感触を与えるのは良くない。この着色層とはそもそもなにものなのか、この着色層を取り除く方策は。
できた積層体を、平行線群と直行させて、およそ2ミリの幅にダイヤモンドカッターでスライスし、更にこれを研磨し、面取り機にかけて1センチ直径の円盤にする。この円盤に含まれる金属線は、この円盤を酸溶液に浸漬すると酸に溶かされて、ガラス盤に50個もの細孔ができる訳である。孔の直径は細い線の径と同じである。これでガラスノズルはできたのであるが、この金属線が抜けた穴を顕微鏡で観察すると、無色透明ではなく、まるで、人の目じりのような灰色の着色層が残るというのである。この着色層があっても穴は開いているので機能的には問題が無いのだけれど、孔にものが詰まっているとの感触を与えるのは良くない。この着色層とはそもそもなにものなのか、この着色層を取り除く方策は。
着色層ができる製造の条件が示された。①着色層は真空状態や還元雰囲気で焼成したときにでき、普通の焼成即ち酸化雰囲気のときにはできない。②スライドガラスはできにくい。
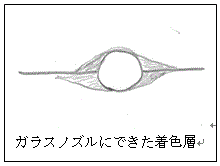 金属板とガラスが接着している琺瑯の分野では、その接着機構は既によく研究されていた。琺瑯の場合は、釉薬ガラスと溶融接着する過程で、金属板の酸化された部分がガラス内部融け込んでゆき、琺瑯としての接着を確実にする、そのような接着界面が存在するのである。
とすれば、ガラスノズルでは、むしろ融着するまでの酸化雰囲気で金属線が酸化され、融着温度になってガラス内に金属表層から溶け込んだ金属イオンが融け込む、この金属イオンによってガラスに着色層ができると考えるのが普通なのだが、何故か、還元雰囲気で融着させた方が、その酸化金属と思われる着色層が強く出る。この矛盾の為に、「着色層」の解消に向けた手が打てないのである。
金属板とガラスが接着している琺瑯の分野では、その接着機構は既によく研究されていた。琺瑯の場合は、釉薬ガラスと溶融接着する過程で、金属板の酸化された部分がガラス内部融け込んでゆき、琺瑯としての接着を確実にする、そのような接着界面が存在するのである。
とすれば、ガラスノズルでは、むしろ融着するまでの酸化雰囲気で金属線が酸化され、融着温度になってガラス内に金属表層から溶け込んだ金属イオンが融け込む、この金属イオンによってガラスに着色層ができると考えるのが普通なのだが、何故か、還元雰囲気で融着させた方が、その酸化金属と思われる着色層が強く出る。この矛盾の為に、「着色層」の解消に向けた手が打てないのである。
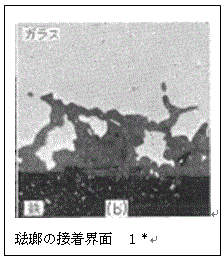
温度700℃に上げガラス板を融着するために、炉を手作りした。フランジ付きの蓋を持つ缶が、この炉のヒーターを巻いた磁器製の円筒内に入る。
この炉の缶を使って、その中に入れた薄板ガラスと細線からなる積層体を融着温度の700℃にして融着させるが、その際、缶内の雰囲気を、普通の空気から窒素ガスに入れ替える、或いは、真空に近く減圧する。極めつけは、還元雰囲気にするために水素ガスを入れることにした。金属線を酸化させないでおくと、琺瑯ガラスの理論によれば、界面ガラスに溶け込む金属イオンはあっても少なく、着色層を作ることはないであろう。
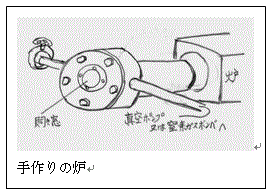 炉の缶内を水素ガスで充満させ、高温に過熱するので、爆発を起こしはしないかと心配したのではあるが、「なあに、水素ガスには圧を掛けて、炉の外に導いたガスを燃焼させておれば問題はなかろうよ。」と、部長は言う。
炉の缶内を水素ガスで充満させ、高温に過熱するので、爆発を起こしはしないかと心配したのではあるが、「なあに、水素ガスには圧を掛けて、炉の外に導いたガスを燃焼させておれば問題はなかろうよ。」と、部長は言う。
水素ガスを入れたその炉を既定通りの温度スケジュールで焼成した。試料を取り出して、びっくりした。積層体が真っ黒なのである。これですべてが判明した。このガラスには鉛が含まれていた。鉛ガラスは還元焼成すると、ガラスは黒くなるのである。従って、金属線は色に関係していなかったのである。目のような着色層は、ガラス板の軟化融着工程において、金属線を挟むガラス部分が最後まで雰囲気に曝されることになり、その部分がより還元されて黒くなっただけのこと、だったのである。
カバーガラスの製造会社に特注して、鉛を抜き、消泡剤としてアンチモンを入れたカバーガラスを取り寄せた。このカバーガラスで積層体を造ると、着色層に相当する部分には、ごく薄い黄色が出たが、問題視するような色ではなかった。
勤めて最初の研究課題で関係したこのガラスノズルは、諸般の事情で市販までには至らなかった。半世紀も前のことではあるが、その時も、自分の課題への取り組み方法には問題があると思った。着色層の原因が、金属とガラスの反応と視るまでに、カバーガラスの組成は調べておくべきではなかったか。といっても、ガラスに含まれた鉛成分が還元焼成で簡単に黒くなるとは、新人の私の知識にはなかったものなのではあったが。
この話には後日談がある。
ガラスびんに印刷を行っている印刷課長の要請で、印刷剥離の原因調査をしたことがあった。
 当時、牛乳瓶が特に多かったのだが、例えば、赤色の明治乳業という社名、180CCの容量の表示が、ガラス塗料で印刷されていた。スクリーン印刷といって、昔の学校の謄写版印刷を思って貰えばいいのだが、粉末ガラスの入った油性塗料を、牛乳瓶の肌に印刷し、それを650℃の窯に入れて焼き付けるのである。
当時、牛乳瓶が特に多かったのだが、例えば、赤色の明治乳業という社名、180CCの容量の表示が、ガラス塗料で印刷されていた。スクリーン印刷といって、昔の学校の謄写版印刷を思って貰えばいいのだが、粉末ガラスの入った油性塗料を、牛乳瓶の肌に印刷し、それを650℃の窯に入れて焼き付けるのである。
ところで、焼き付けする前に、印刷した塗料を先ず乾かすためにその瓶を乾燥炉に入れるのであるが、時に、印刷した塗料が、そこでパラパラと剥離するという。この乾燥炉では、印刷されたばかりの瓶が流れるコンベアの下でブタンガスが炊かれていた。担当者は、乾燥炉の温度を高くしょうとバーナーのガス量を上げると剥離数が増すので、仕方なく、ガス量を絞り、どちらかといえば過剰空気の燃焼で、低温状態で乾燥炉を運転せざるを得ないという。
そうすると不完全燃焼、すなわち還元状態が塗料を剥離させるという訳であるが、どうもよく分からない。が、還元状態の燃焼でいえば、例の水素雰囲気炉があることを想い出した。早速水素炎を点けて、その横で瓶を乾燥させてみた。驚いた、瓶に印刷した塗料がパラパラと墜ちるではないか。そしてその瓶肌には水素炎による水滴が付着していた。そうか、ガスの燃焼による水蒸気が関係していたのだった。塗料の付着成分はアマニ油で、その油が乾燥しきらぬ内に水蒸気が作用したわけだった。
すなわち、ガス量を絞り、低温焼成の場合は燃焼して発生する水分量が結果として少なく、まだしも剥離数を低くしていたというわけであったが、温度を上げようとしてブタンガス量を上げると、炉内に燃焼でできた水蒸気が増し、未乾燥の印刷塗料が瓶表面から剥離することにつながったのである。
印刷課の課長には、乾燥炉の温度を上げるためには、瓶にガスの炎や気流が直接当たることのない、隔壁のあるマッフル型の炉で解決できると、報告することができた。
何れの課題解決も水素炉がもたらした偶然の産物であって、私の技術者としての解析能力の甘さが自己評価として残る結果となったが、解決は解決と、研究部長が喜んでくれていたようで、それが嬉しかったことだけが今も心に残っている。
あれから50年が過ぎた。日本の紡績業界は興隆期を迎えた後の今、その1/3規模に縮減を余儀なくされている。当時、東洋レーヨン、帝人、倉敷紡績、旭化成、日本レーヨン(ユニチカ)などのブランドが輝き、日本経済を牽引していたが、今、紡績業で名前を残しているのは東レ(東洋レーヨン)くらいかも知れない。
紡績業界の低下は紡糸ノズルの需要低下につながっているかも知れない。インターネットで紡糸用ノズルを調べてみると、ノズルの材質は、白金やガラスでなく、主にステンレス鋼である。繊維の風味を左右する細孔のさまざまな形状は、発展著しいレザー光加工技術によっているということだ。
参照、引用文献
1*池 田 豊 「ガ ラ ス と 金 属 の 接 着 機 構 (I)」材 料 第17巻 第180号
(2017.02)
| 
