|
魔法びんを辞書で牽くと、サーモス(thermos ドイツのテルモス社が商品化に成功た「テルモス」に由来)、もしくは、真空びん( vacuum bottle )となっており、名前に“魔法”が入ってきたのは、熱が冷めないことを日本人がマジックのようだ、と思ったからに違いない。
それはそれで間違いない事実なのであるが、このガラス容器には、“魔法”という言葉が持つ、なにか、デーィズニー・ワールドにも似た、製品の夢がある。
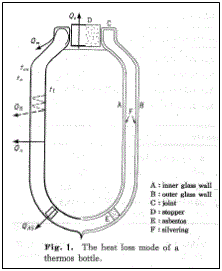 何故保温性が好いのか。ガラスの魔法びんでは、その構造は、右の図に説明するように、二重壁の間の層を真空にし、かつ、内側を鏡にして逃げる熱を防いでいる。内びんを支えるのは口部の外びんとの融着部と二重壁の底部に入れた断熱材の小片である。問題は、内、外の薄いびん(バルブ)を造って措き、口部の個所だけで融着させて、二重壁のガラスびんを造る工程が技術的にも手が込んでいることである。
何故保温性が好いのか。ガラスの魔法びんでは、その構造は、右の図に説明するように、二重壁の間の層を真空にし、かつ、内側を鏡にして逃げる熱を防いでいる。内びんを支えるのは口部の外びんとの融着部と二重壁の底部に入れた断熱材の小片である。問題は、内、外の薄いびん(バルブ)を造って措き、口部の個所だけで融着させて、二重壁のガラスびんを造る工程が技術的にも手が込んでいることである。
魔法びんの変遷
1953. 魔法びんと聞くと、私には、必ず浮かぶ光景がある。中学校の遠足である。女性徒が置いた水筒の置き方が悪かったのか、ぐっしゃと言う音がした。その女性徒、越田さんの顔がゆがんだ。高価な魔法ひんは1リットルほどの円筒形のブリキのケースに入っていたが、ちょっとしたショックで実に簡単に割れた。だから、魔法びんはとにかく割れやすい、大切に扱わなければならない商品であった。
1957. 電気冷蔵庫は、未だ高嶺の花、ちょっとした金持ちのお宅には製氷を入れる木製の冷蔵庫があった。その頃大型ジャーが出た。口部の直径は15センチはあろうかという円筒形の大型魔法びんであった。内側には薄い円筒状の金属の筒が入っていて、氷屋で買った、一貫目の長方形の氷をいれても、その衝撃では割れない構造を持っていた。氷を家に置いて措いて、好きなときに取りだして食べることができる。炊きたてのご飯を入れておけば、冷めず何時までも温かいご飯を食べることができる。「タイガー・ジャー」が有名ブランドではなかったか。これは、庶民に売れた。我が家では重宝していた。
当時は、二重ガラスびんの魔法びん生産は全てガラス職人の手作りの技であった。硬質ガラスのびんバルブも口吹きでできていた。内と外の二つのガラスびんを口部で溶接する作業も、職人のバーナー加工技術による。
1963.岡山大学の実験室である。大東マホービン社から出張された二人が、魔法瓶の自動製造化に向けて、機械の調整に励んでいた。ガラスびん(バルブ)を保持するホルダー(腕木)が10本ほど張り出していて、回転しながら作業工程を進めてゆく構造である。先ず、二重のガラスバルブをホルダーに装着するステップがあり。何ステップ目かに、ガスバーナがあって、ガラスびん口部を少し溶かす。次のステップでは、二重のガラスびんの口部を絞り、融着させるのである。こうしてできた魔法びんの形をしたガラス容器が、実験室に沢山転がっていたが、どうやら満足行くものはできていない様子だった。強度に乏しいのか、形状の滑らかさに欠けるのか。
日本電気ガラス社は特殊ガラスの専門メーカーであった。このガラス社のタンク窯で均質な硬質ガラスが溶融され、自動製びん機と同じ機械で、魔法びんのバルブが生産されるようになった。径においても、肉厚にあっても、均質なガラスバルブができた。従って、このバルブを使って、二重ガラスびんの魔法びんの生産の自動化が可能になったのである。人工吹きのバルブは均質さに欠けており、岡山大学の実験室では、魔法瓶製造の自動化が成功できなかった要因がここにあったことが判る。
かくして、魔法びん製造会社は、今や、びんバルブの製造から商品を造るのではなく、ガラスバルブは日本電気ガラス社に委託し、二重壁ガラスびんの自動加工と、渡銀加工、真空封着を行って、その魔法びん(中びん)を、金属もしくはプラスチックケースへ組み込む作業を、コンベアベルトのラインで管理することが主な仕事と成った。ケースは無論外注先から取り寄せである。
 栗原小巻のCMでおなじみだった大型魔法びん、エァーポットの「押すだけ」(右の図に示す)が、主力製品となった。傾けて湯を出すのではなく、上から押した空気圧で、コップ一杯程度のお湯をいつでも供給できるから、インスタント・コーヒに明るい雰囲気を反映させた、明るい職場で特に重宝された。
栗原小巻のCMでおなじみだった大型魔法びん、エァーポットの「押すだけ」(右の図に示す)が、主力製品となった。傾けて湯を出すのではなく、上から押した空気圧で、コップ一杯程度のお湯をいつでも供給できるから、インスタント・コーヒに明るい雰囲気を反映させた、明るい職場で特に重宝された。
雑貨店では、アラジン社の携帯魔法びんがよく売れていた。キルト地柄のプラスチックケースの赤い華やかさが受けていた。この携帯がよく売れたのは単なるデザインの所為ばかりではなく、軽くて衝撃に強かったからだと思う。
だがしかし、熱く新鮮なお湯を常に欲しいとの、理想を求めると、経済的な観点は差し措かれ、給湯器具は電気ポットに移ってゆく。その少し前、ガス給湯器の場合、家庭に浸透させてゆくためのキャッチフレーズは、「いつでも熱いコーヒが造れる熱湯のサービス」であったが、その性能か、香りに問題があったのか、結果、大型魔法びん、「押すだけ」が取って代わったばかりの、給湯の座であったのだが。
携帯では、ガラスの脆弱性を嫌って、ステンレス魔法びんが主力になる。ステンレスは金属では、熱伝導性能が低い。加工技術が進歩した結果、薄くできる二重ステンレスびんが可能になったために、保温性能が、ガラスの魔法びんと殆ど変わらなくなったからである。
こうして、形は魔法びんを踏襲しているが、その中びんには、ガラスが使われない時代が来た。
象印マホービンや、タイガーマホービン社はその主力製品を、電気ポット、炊飯器、コーヒメーイカー、パン作り器と、大手家電メーカーにない隙間商品に変えている。各家庭にある魔法びん数を調査したとき、各家庭で利用されない魔法びんが棚の奥で、2,3個は転がっているとして、日本での魔法びん生産に限界を見たためである。国内ばかりでなく、1990年130億円輸出されていた魔法びんは、2010年ではその7割減となった。
嘗て、輸出産業として華々しい成果を上げていた魔法びんは、大阪の地場産業であった。輸出に際しては、「輸出検査法」に縛られていた。実は、私は、この「輸出検査法」に基づいて、魔法びんの品質を検査をする側の、検査機関に所属していた人間であった。
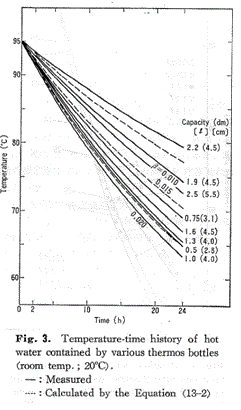 輸出する魔法びんの保温性を保証するために、温度検査がある。魔法びんのサイズによって異なるが、例えば内容量2リットルの場合、熱湯を入れ(厳密には95℃になった時点から)24時間後、その湯の温度が=65℃以上に保温されてなければならないと規定されている。だからこの温度検査の立ち会いには2日が必要になった。
輸出する魔法びんの保温性を保証するために、温度検査がある。魔法びんのサイズによって異なるが、例えば内容量2リットルの場合、熱湯を入れ(厳密には95℃になった時点から)24時間後、その湯の温度が=65℃以上に保温されてなければならないと規定されている。だからこの温度検査の立ち会いには2日が必要になった。
小さなサイズの魔法びんから大きなサイズの魔法びんまで、十把一絡げにして、その湯の温度降下の様子を右の図に示す。座標の横軸は経過時間(h)、縦軸は魔法びんの湯の温度(℃)である。この事実を基に、これを実験式で表し、その2時間経過時の温度T2と24時間後の温度T24の関係を表せば、次式が導かれた。
T24=(20+113000*A)/(1−2050*A)
A={(T2−20)/(T2+55)}12
上記、T24*=65℃となる2リットルの魔法びんの場合、上式より計算すれば、T2*=91.3℃が導ける。
すなわち、熱湯を入れた魔法びんは、(95℃になった時点から)2時間後、91.3℃より上の温度を示せば、従来の規定である、24時間後、その湯の温度が65℃以上にあり、その保温性は保証されることになる。
このような事実を積み上げて、輸出検査に関しては、魔法びんの検査時間は、2日間に亘らず、2時間に短縮されたのであったが、その検査の迅速化に、少しは貢献できたかもと自負が自分にはあって、関わらせていただいた時間は短かったのではあるが、今も、魔法びんやその業界には、親しみを感じるのである。
もう50年は昔の頃、中国で文化大革命が終わった頃の話しである。日本では、夢の3C、すなわち、カー、クーラー、カラーテレビなどが現実化しつつあったが、中国の大衆の夢は、「魔法瓶が欲しい」ということだった。従って、私の経験的感覚からすれば、中国人の生活水準は、日本人に較べて、20年は遅れていた。
従って、今や、日本ではあまり注目されることもない魔法びんではあるが、日本でも中国でもその生活水準の発展途上に於いては、庶民の夢のある製品だったのである。日本では、既に、その技術を眠らせてしまっている。魔法びん生産の時代は終わったのか。
今、不幸にして、アフリカや中東には難民が溢れている。多分、この人達に夢を持たせる商品としては、各自が携帯できる魔法びんがあるのではないか。どうだろう。日本が、難民を多く抱えている国への支援として、魔法びん製造工場を建て、その国の産業とすることで、人と技術と夢を育成していくことは。
(2017.08)
| 
