|
私は株をやらない。しかし、テレビの経済ニュースはよく見る。株価の上がり下がりを見ていると、例えば、鉄鋼株が下落していると、その解説にもあるように、「コロナ禍の追い打ちもあって、自動車産業、建設業が不振、ために国内鉄鋼メーカーの統合が加速されている」、とある。世界の経済の生の動きを見るようで、ニュースとしてはためになる様な気がする。
馬券を買ったこともないのだが、学生時代に馬に乗っていたからか、競馬中継はよく見る。本来の賭け事に首を突っ込まず、ただ、馬の疾走する姿をぼんやり眺めて喜んでいる。株価、経済に就いてもこれと同じ、私は、ただただ、傍観者として満足しているので、株投資や経済たるものの本質はよく解ってはいない。
経済論など学んだこともない。しかし、不思議なことに、人生80年の経験だけで、世の流れに愚痴をこぼしてみれば、検索キーワードに<エッセイ集>という限定は附くのだが、その検索順位は、<エッセイ集><銀行>①は240万件中で1位、何と、<エッセイ集><私の経済論>②も240万件中で1位というから、読者にとっては、私の戯言(ざれごと)に共感ができる部分はあるのかも知れない。
尤も、(エッセイ138)「銀行は何故怒らないのか」①をホームページに上げたとき、「これは人様に読んで貰えるようなものか」と少々心配になり、小学校からの友人で、銀行支店長経験者に「一度読んでみて、君の感想を聞かせて」と 頼んだことがあった。彼は、「君の言っていることは正しい。しかも銀行側に立ってくれている。これは僕らには有り難い。」と回答して呉れた。「そうか、この程度の経済論議は、私の常識で太刀打ちできる問題らしい。」と解釈して安心はしたのだが、肝心の、銀行が、日銀黒田総裁の独断に怒りを感じているかどうかを聞き質さなかったことに、この原稿を書いている今気付いた。
エッセイ138「銀行は何故怒らないのか」① の要点には、経済活動における潤滑剤のような銀行の機能が、今の社会から消えることに対する私の危機感もあったのだが、この記事①を掲載してからおよそ2年が経つ内にも、銀行業界に於いては、部署の統廃合は進み、店舗数の減少、銀行員の配置転換が行われ、また、預金者の口座の管理を有料化仕様にするとの動きもあり、結果的に、経済界における銀行の比重は重みを欠いてきたとの感もある。
その中、その根源となった、黒田日銀総裁の「異次元の量的緩和」による「ゼロ金利政策」に、何故、銀行が本気で怒らないのか、という点には、どこか不思議だなという気持ちが抜けなかった。「一体全体、銀行業界は、日銀の方策に対して、何故、怒りをぶつけないのか?」
さてその黒田日銀総裁の「異次元の量的緩和」である。2013 年、安倍のミクスと呼ばれた安倍政権の掲げる経済政策に呼応して、内需喚起のため2%のインフレ状態を人為的に造るとして、貨幣を増刷、そのお金で、日銀が市中銀行にあった国債を買い戻すという方法を使った。日銀が国債を買い戻すときに、その紙幣は銀行に渡り、市中銀行にはディーラとしての手数料も入る。何十兆円の規模の取引である。すなわち、市中銀行は政府が借金するごとに、新規国債を引き受けておれば、何の営業努力をしなくっても、莫大な利潤が発生する仕組みともなっている。
そうか、黒田日銀総裁の「異次元の量的緩和」に、大手銀行が正面から怒らぬ訳が、こんな処にあったのか。
市中に、新たに刷られた貨幣が流れ出るのである。従って、日本円の価値は下がり、為替市場は円安に振れる。当然のことながら、輸入物品は高くなる。紙幣の枚数が増えているので、比例して、国内産品も高い値段に移行することとなる。それを焦った消費者が物を買いに走る。国内インフレである。物が消費されれば、国内の製造業、小売業も忙しくなる。従業員の給与も上がる。消費マインドは住宅、レジャーにも向かう。企業が儲けると、国の税収が伸びる。赤字国債を少なくすることができる。“目出度し目出度し”である。
だが、現実には、黒田総裁の描いた“目出度し目出度し”の循環は起こらないままで10年近く来たのである。2%のインフレはおろか、国内景気は不況、デフレからも脱却できていないのである。しかも、コロナ禍による世界的不況。「異次元」というから短期決戦で掲げたはずの目標は、未だに旗を降ろせずにいる。“公約”が果たせぬままに、「量的金融緩和」はダラダラと続いている。こんな事態が許されていいのか。
不必要にお札を刷り続けるとどうなるか。私は、2013年10月のエッセイに次の文章を上げている。
「安倍ノミクス」とかで、日銀はお札の増刷を始めた。私は幼少期の苦い体験を思い出した。小学4年生の頃である。買い物遊びが流行っていた。店を構え自分の宝物などを売っているのだが、お金持ちは隣保の喧嘩大将で、品定めをしては買っていく。が、どうも儲かった気がしない。自分の商品は消えるのに、残るのは喧嘩大将がクレオンで百円と書いた紙切れである。私は思いついて、自分でお金を書くことにした。大量の新札に元締めの大将は怒った。当然である。商品が高騰したばかりでなく、持っていた札束の価値も半分になったのである。大将は、私を除け者にするといい、私は仲間に入れてもらえなくなったのである。
企業は商品価格を上げてバランスを取ることができるが、我々には、物価高騰の煽りばかりではなく、実際、現金と預金の実質目減りが始まっているのである。日銀増刷分に比べて分母が大きいから俄に目立たないだけである。何かと屁理屈をこねている安倍さんと黒田さんを除け者にしなければ、日本の経済秩序は危なくなることを私はあの喧嘩大将から学んでいるのである。 /(2013.10)
-(エッセイ4)技術士雑感アラカルト その6.私の経済論(2)②より転載-
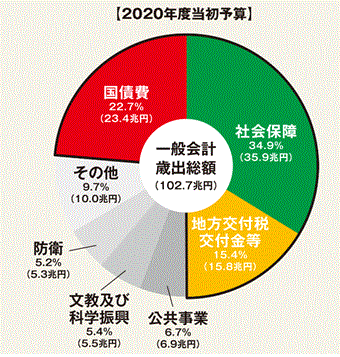 四半世紀の昔には、国は税収を超えるような多大の借金はしないと誓ったのである(1997年には財政構造改革法が制定され、2003年までに赤字国債の新規発行をゼロにする。)実に健全な誓いではないか。その背景には、田中角栄首相の「日本列島改造計画」が動き出した1970年から、道路や橋、埋め立てなどの「大型プロジェクト」中心の公共事業偏重の財政運営が続けられ、そのために「建設国債」や「地方債」が発行され、そのツケが雪だるま式に膨らんだからである。しかも造った“箱物”には、後の維持管理に費用がかかり続けるのである。この反省があった。
四半世紀の昔には、国は税収を超えるような多大の借金はしないと誓ったのである(1997年には財政構造改革法が制定され、2003年までに赤字国債の新規発行をゼロにする。)実に健全な誓いではないか。その背景には、田中角栄首相の「日本列島改造計画」が動き出した1970年から、道路や橋、埋め立てなどの「大型プロジェクト」中心の公共事業偏重の財政運営が続けられ、そのために「建設国債」や「地方債」が発行され、そのツケが雪だるま式に膨らんだからである。しかも造った“箱物”には、後の維持管理に費用がかかり続けるのである。この反省があった。
しかし、高齢化社会を迎え、社会福祉には益々お金がかかる、国が豊かになると、それを護る防衛費にもお金が必要となり、借金、すなわち国債でそれを賄うことになったのである。
今やその債務額の合計は1000兆円、毎年の国の税収70兆円の15倍、国家予算100兆円に占めるその国債の毎年の元本と金利の返済額は、23%になるという。
35%を占める「社会保障」とは、年金、医療、介護、子ども・子育て等のための支出である。高齢化社会となって、増え続ける「社会保障」費の問題は大問題である。姨捨山現代篇が語られ、話し合う空気が醸成されない内は、触ることのできない社会生活の本質がある。今回ここでは論じない。
2020年の国家予算は102.7兆円、税収は70.1兆円、従ってあとは借金と返済でやり繰りするが、その国債費は 23.4兆円である。毎年の予算のおよそ1/4が国債等の借金の(元本+利息)の返済に当てられるが、今後益々国債費たる借金の増加が予想される。
1000兆円の債務がどれほど大きなものかの例えに、日本人、赤子を含めて、一人当たり100万円の借金をしている、と言う。そこにあって、コロナ対策である。緊急事態だと言って、誰も使わない安倍のマスクの400億円出費に始まり、国民一人当たりに、10万円をばらまいたのである。この額120兆円と言うから、あとは健全財政という概念は日本から吹き飛んでしまった。「国民の皆様」が喜ぶ垂れ流しである。
もし今、経済の専門家と称する人がいるならば、国の最大の経済問題を解決に導く経路を是非、解説して欲しい。本質を語らず、株価の動向とか、今後の経済の見通しを蕩々と語っているようでは、専門家の称号が泣く、競馬場で聞く予想屋の類に過ぎないのではないか。
税収は、70兆円前後に限られているとなると、現在の10%の消費税をさらに上げて30%とすれば、20%増分は(1%の消費税値上げで2兆円の税収が期待できるとして)、2兆円×20で40兆円すなわち、毎年の税収は70+40=110兆円となる。借金なしの110兆円の予算が組めるから、多少の社会保障費に増額があっても、さらに借金の国債を発行せずとも良いという、健全な予算が組める。
だが、消費税を30%とした健全予算が組めたとしても、現在累積した、1000兆円の、元本が完済されるまでには、(基本的に60年分割の返済の形が取られているので)60年は掛かるとされる。
市街地に高層ビルが林立して、夜は華やかなネオンに包まれているとしても、借金を抱え続ける国の姿が正しいあり方とは思わない。税収が限られるとすると、普通は、消費税をアップするしか思い付かない。高消費税率で有名な北欧諸国、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの3カ国は25%、高福祉で幸せな国民生活をおくる国とされている。しかし、日本の目ざす国の姿と一致するのか。8%の消費税をたった2%アップするのに、軽減税率導入、やれ、ペイペイで支払えば5%のポイント還元など世間が騒然とした半年があったのである。これを、その10倍たる20%アップするなど、およそ不可能に思えないか。
いや、その1000兆円は、返さなくてもいいのだという、時々おかしな理論が世間を騒がす。MMT(現代貨幣理論(Modern Monetary Theory))というが、「自国の通貨を発行して借金できる国が財政破綻することはない。だから財政再建のために政府の支出を減らしたり税や保険料の国民負担を増やしたりしなくても、借金を膨らませて費用を賄えばいい」という理論らしい。
MMTの理論を聞いていると、2008年のリーマン・ショックまで、株式相場界を席巻していた「金融工学」という言葉を想い出す。不良債権があっても、優良債権と上手く組み合わせて証券化、投資商品にすれば安心して買うことができる。それは、確率統計的に見て、リスク分散されるので、飛行機で言えば、絶対に落ちないことが設計されているようなものだとか。
確率統計という数学も入ってきて解ったような解らない話であったが、信用力が劣る住宅ローンも債券も高利回りの投資商品となっていたところ、警戒したプロの投資家がこれら商品を売却し始めると、そこに大規模な投資をしていた大手投資銀行のリーマン・ブラザーズが、日本円で64兆円という莫大な負債を負って倒産し、その煽りで、世界中が強烈な景気後退に見舞われたことは、記憶に新しい。
私は、我が国が抱える経済問題の根源は、黒田日銀総裁の金融緩和策に問題があると考え、その非を自らの経験から指摘しょうと、無い知恵を絞りながら、私的経済論に挑戦してきた。が、ここに到って、「国の累積債務1000兆円の返済を、政府、経済専門家は一体どうすればいいと考えているのか」、それこそが、最大の懸案事項と考えるようになった。その解はあるのか。と考えてきて、ふと、(エッセイ138)銀行は何故怒らないのか① の中で半ば冗談のように出て来た思い付きが突如、異彩を放ってきた。
この日本の戦後からの復興を、今から半世紀前に起点を置いて、私の体験から考えてみよう。
「中華そば・ラーメン」は100円であったが今は500円である。従って、この間、物価インフレはあったのである。企業は儲かり、賃金は上った。大卒初任給は3万円が今では20万円。市民の生活水準はどうなったか。あの時、映画の中のアメリカ人の生活のレベルは、夢のまた夢であったが、今の日本人には、冷蔵庫、自動車の所有は当たり前である。スペースは少し小さいとしても、瀟洒なマンション生活ではないか。
家のローン、いゃ、奨学金返還はこの間、如何に楽であったか。収入が多くなっていくから、返還額が小さく見える。実は、国の借金の返済もこの原理ではないかと思う。インフレになれば総体的に、国債の総額は小さくなる。ここが黒田総裁の本当の狙いやも知れない。-(エッセイ138)銀行は何故怒らないのか① から引用-
我が国に於いては、現在の紙幣枚数が一応適切な枚数であるとして、同じだけの枚数を印刷する。紙幣が今の倍になったと想定をしてみる。紙幣の価値は1/2になるから、元20円の卵には、40円払って購入となる。為替相場は1ドル100円であったが、1ドル200円となり、輸入チョコレート100円のものは、200円となる。国債1000兆円の返済額は額面のままの1000兆円返済すればいいから、元の半額でよくなったことになる。黒田日銀総裁の狙いは確かに、ここにある。私が奨学金の返済を、インフレ化において苦労しなかった訳がここにある。
サラリーマンの給与は、労働の実質価値から2倍になり特段の損はしないかも知れない。公共料金の支払いも倍額になり、土地価格も2倍の値札を付けることになる。年金は、場合によっては2倍の振り込み額に変更になるかも知れないが、しかし、私の1000万円記入の貯金通帳は、実質500万円になってしまう。持っている現金の価値も1/2になるから、高齢者は、黒田日銀総裁の紙幣増刷のインフレ政策には絶対反対を唱えなければならない。
少し前まで、観光地は外国人で溢れ、私はうんざりしたものだが、そのインバウンド事業は4兆円の税収を稼ぎ出していた。ひょっとして10兆円位までを目論んでいた観光産業はコロナ禍で当面税収は見込めない。当然政府は、税収を上げるに大きく寄与する産業、技術の育成に血眼だと思う。
二昔前には、電子立国ジャパンという半導体に賭けた夢があった。また、東芝は、世界最大の原子力発電事業者になるはずであったが、一昔前の福島第1原発事故で世の雲行きが変わり、本社の屋台骨を解体するほどの経済的打撃を受けて、この事業から撤退した。最近では三菱重工が、支援を続けたジェット旅客機「三菱スペースジェット(旧MRJ)」の開発を事実上凍結した。この間、税収を稼ぎ出す産業の輩出を待っていたかも知れない、黒田日銀総裁の思惑が報われなかった不幸な面は、ひょっとしてあったかも知れない。
それでは1120兆円の国債の返済はどうするのか。安倍元首相の経済政策は“安倍ノミクス”と称されたが、国興しは工業生産からとの概念が染みついた私の頭では、安倍さんの何が経済政策なのか、実は当時よく解らなかった。が、今思うに、黒田日銀総裁の助けを借りた、「金融緩和」で物価上昇をおこし、国内産業を活発にして税収も伸ばそうとした、そのものが“安倍ノミクス”だった。
首相たるものが国発展の展望を示し、工業技術の育成に努めた経済通産省が具体的なビジョンを出して産業を興す手助けをし、財務省が国債完済への道筋を付ける、これが富国へのオーソドックスな行程である。
その意味では、菅首相が出した、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」という脱炭素社会達成プランは、人類の崇高な目標を目ざし、かつ、富国への行程を刻もうとするオーソドックスなものである。が、気懸かりは、30年先は余りにも遠いし、達成への段階プランが何一つ説明されていないことだ。
夢のような月へのアポロ計画でさえ、ケネディが発表当時には、ソ連であったが、有人宇宙船は宇宙のある軌道を飛行していたのである。私なら、循環型社会を100%達成する技術開発し産業化する。例えば、廃棄物、副産物を全て材料、エネルギーに変える。それと平行して、国土を、災害、環境、福祉に強いコンパクトシティー-に造り変えていくなど、この策を打ち出す。
仕方がない。さらに具体的な私の考えを書いておこう。富国にはつながらないが、1120兆円の国債は完済できる。
1兆円の金持がする犯罪の罪は1兆円を没収して免責にする。こんな金持ちの犯罪人を日本国内で1120人見つけ出せばいいのである。さしあたって、レバノンから逃げ帰って来るかも知れないゴン元会長はこの候補である。没収したお金で、日銀金庫に保管されている国債証券1120兆円を買い取れば、これで国の債務は0となる。皮肉なことに、これは上記のMMTの理論の範疇ではないのかと思ったりもする。
ただし、国債証券の代わりに、日銀の金庫に戻った1120兆円の札束を、国や日銀は何かに利用することなく、全部焼却しなければならない。なぜなら、国債を購入名目に、今まで日銀が新たに刷ってきたと同額の札束であり、不健全で不名誉なバランスシート上に現れた産物であつた。この札束減らしこそが、黒田日銀総裁の「異次元緩和」を元に戻すための絡繰り(からくり)に他ならないのだから。
(2020.11)
参考文献
ホームページ 山田博文のNetizen越風山房
参照
①(エッセイ138)銀行は何故怒らないのか
②(エッセイ 4)技術士雑感アラカルト その6.私の経済論(2)/その8.私の経済論(1)
| 
