|
ホームページである、私のエッセイ集「ゴンちゃん倶楽部」であるが、検索ランキングで見れば、このエッセイを読んで下さる方が多いのは解るが、果たして自分の意図がうまく伝わったかどうかまでは解らず、本当に理解されたのだろうかと、ふと心配になることはある。そんな時、知人の数人の方からは、講評、コメントがメールか何かで直接戴ける。例えば、次のようなコメントをいただくことがある。
(エッセイ 218)高齢者の心模様 を指して、このエッセイは人生の何たるかを書こうとしている。私は、これをエッセイの本流と捉えているが、例えば、(エッセイ 219)再び馬に乗る(5.馬に乗り続ける理由) は、亜流だと思う。乗馬教室の進級について具体的に書かれている。いつもテーマについて詳細な記述があるのが貴方のエッセイの特徴で、それが読者の知識欲に訴えるようで、読み甲斐はあるのだが、反面、本流からは少し外れるのは仕方のないことなのかなぁ。
この方のコメントが契機となって、私は私のエッセイの原点に立ち返ってみることになった。
小学校への入学前、私が6歳頃の出来事である。
家の東側に、今から見ると、大して大きくない庭があった。私は、その庭の土の上に木の割り箸を、ちょうど電車の線路のように、つなぐように幾本も埋めていた。せいぜい50センチほどの長さの鉄道路線である。そこを走る電車の玩具はないのだが、私はそこに踏切を造りたかったのである。
当時、電車が交差する道路があると、そこには必ず踏み切りがあった。電車が踏み切りに近づいてくると、警報が鳴り、警手が長い竹竿を下ろし、来る電車に向かって白い旗を振る。電車が通過すると、警手は竹竿の遮断機を上に揚げ、人や車を再び往来させるのである。
竹竿の遮断機の斜めの上げ下げ運動は、竿の片側の支点にある船の操舵のような木の輪に警手が人力を掛けて廻すことで生じる回転力を利用している。それを真似て、これも竿を真似たその一本の割り箸の端に近いところに針金を通し低い支柱と結ぶと、遮断機とおぼしきものはできた。割り箸の竿で、遮断機の斜めに上がる動作だけは真似ることができた。
電車の線路を挟んで、対向する側には警手はいないが、遮断機がある。その竹竿も、警手がこちらの竹竿を揚げれば、同時に上に揚がる。その仕掛けは、警手側の竿の端部と対向する竹竿をつなぐワイヤーロープがあって、このワイヤーロープは線路の下をくぐって二つの竹竿をつないでいる。だから、私も対向する二つの割り箸竿の端部を凧糸で繋げてみた。
だが、警手側に相当する割り箸の竿を揚げてみると、対向する割り箸の竿は揚がるどころか、凧糸が唯、弛むのである。なんで本物の遮断機のように、私の模型の一組の二つの竿は連動して上に揚がらないのか。
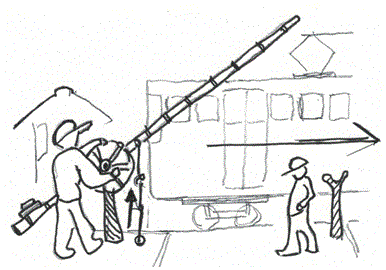
私の悩む様子を父は黙ってみていた。そして、「健男、見に行こう」と、家から10分ばかりのところにあった実際の踏切に連れて行った。私達は二つの竹竿をつなぐワイヤーロープの働きを見に来たのである。そうか、警手側にあるロープは竹竿の端部に結び付けてあるのではなく、警手が廻す操舵の回転軸より前の部分に取り付けられていたのである。
警手が竿を揚げると、ロープは引っ張り上げられる。すると、対向側にある竿は、端部がそのワイヤーロープで引っ張り下げられて、上に揚がるのである。
対向する二つの竿が同時に揚がる原理はこうだったのかと解ったことは面白かつたのだが、私の心に残ったのは、実際の踏切に連れて行く前にも、後にも、説明がましいことを一切言わなかった父の態度であった。
この出来事より数年前、私は5歳、父に対して同じような思いをもったことがある。今度は、出来事の有った時期ははっきりしている。大阪大空襲というから、1945年3月の出来事である。父は大阪梅田にある会社に勤めていて、その大空襲の凄さを、その焼け跡の姿で、自分の母に見せておきたいと思ったらしい。
私と祖母は西宮から電車でやってきて、大阪梅田で父と落ち合い、瓦礫と化した梅田周辺を歩き始めた。崩れたビルは瓦礫の小山の呈をなして至る所にあった。その灰色の空間を多くの人が一列になって、ただ黙って歩いていた。
動物園のように色彩の華やかさも、面白い生き物、乗り物があるわけではない。ただ歩くだけでは私は直ぐに疲れてきた。その内に昼ご飯の頃となり、父は、私の母親が托した小包を開き、その中にあった蒸しパンの一つを私に渡した。
私は「要らない」と、言った。家では、蒸しパンの上に、赤いジャムか何かが乗ったものしか、私は食べなかったのだ。父親は、「まあ、食べてごらん」というように、その、野菜の緑が乗った蒸しパンを強く勧める。仕方がないので、私はそれを口にした。驚いた、美味しいのだ。思わず、「もう一つ」と言った。
父親は確かに笑っていた。然し、言葉にしては何にも言わなかった。父は説明せずに黙っているのである。私は、この父の教え方は面白いと、5歳の子供心に、確かに思ったのである。
これは中学生になったばかりの頃の話である。
みんなの人気者M君が、突然、「俺は、あのKさんが一番綺麗だと思う」と、言ったのである。だから、私は、そのよそのクラスの女生徒Kさんを見に行ったのである。
ちょうど昼食が終わった頃だった。赤い弁当箱を仕舞おうとしていたKさんは、廊下の窓に現れた私達の視線に戸惑ったような、困った表情を見せていた。私には、Kさんは、M君が取り立てて言うほどの、特別な人には見えなかった。
しかし、それから半月、私には、そのKさんが、輝いて見え始めたのである。私はもうKさんの前には恥ずかしくて立てないのである。その心の中に起こった、あまりの変化の激しさに私は戸惑った。
それは恋だと解るのだが、恋に変わった境目が、どう解析しても解らなかった。まるで季節の春が、気が付けば夏になっているようなものだと、自分なりに解釈して、納得したりもした。
ある時、といっても30歳を越えた頃、私は、自分が経験した生活哲学、人生の閃きのようなものを、エッセイという形を取って、面白おかしく描くことに徹しようと決めたのである。そうすると、おかしいもので、ものを書くことが続き始めたのである。
即ち、自分のエッセイという書き物については、本流、亜流という言葉で言い換えるなら、人生の意義や不条理な悲しさを描くというよりは、始めから、そんなに熟成させなくても書ける、亜流で「面白いもの」を採って行こうと心に決めたのである。
具体例には、(エッセイ1)続そういうことか、(エッセイ2)或る日、突然にわかる などを挙げることができる。
(2023.04)
参考エッセイ
(エッセイ 218)高齢者の心模様
(エッセイ 219)再び馬に乗る(5.馬に乗り続ける理由)
(エッセイ 43)終 戦 の こ ろ(その三 父の死)
((エッセイ 1)続そういうことか
((エッセイ 2)或る日、突然にわかる
| 
